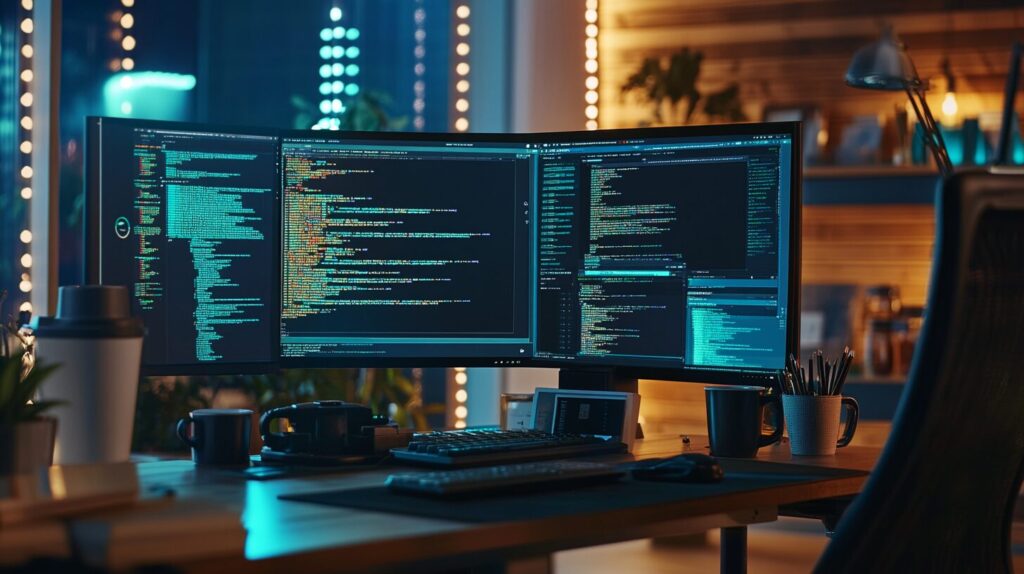フリーランスは直接契約の方が圧倒的にメリットが多い!?メリデメを徹底解説

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
フリーランスとして仕事をしていると、仲介業者を通じた契約に頼ることが多くなりがちです。その中で、「もっと報酬を上げたい」「自分の条件で働きたい」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
そんな時に有効な手段として、直接契約が挙げられます。クライアントと直接契約を結ぶことで、余計な手数料を削減し、報酬アップや柔軟な交渉が可能になるなど、さまざまなメリットを得られるでしょう。
そこで今回の記事では、直接契約のメリットとデメリットを解説していきます。
フリーランス・個人事業主の直接契約とは?
フリーランスや個人事業主が、仲介業者を通さずにクライアントと1対1の関係で結ぶ契約を「直接契約」と呼びます。
直接契約では、業務内容や報酬などの条件を自分自身で交渉できるため、フリーランスにとって自由度が高いメリットがあります。さらに、手数料や仲介費用がかからないため、報酬の取り分が増えることも大きな魅力です。
ここでは、直接契約の形態として一般的な「委任契約」「準委任契約」「請負契約」について、それぞれの特徴と間接契約との違いも含めて解説していきます。
間接契約との違いは?
フリーランスや個人事業主にとって、契約形態には「直接契約」と「間接契約」の2つがあります。
間接契約とは、仲介業者やプラットフォームを介してクライアントと取引を行う契約です。
典型例でいうと、クラウドワークスやランサーズなど、クラウドソーシングサイトを利用する場合が挙げられます。
間接契約では、仲介業者が報酬の支払いやクライアントとの交渉を管理するため、手続きが簡略化されますが、その分、報酬から仲介手数料が差し引かれます。
一方、直接契約では、報酬全額を受け取ることができ、自身の条件で契約を結ぶ自由がありますが、契約内容の確認や支払手続きなど全て自分で行う必要があります。
つまり、間接契約は、業務のやり取りや支払い手続きなどの面倒な部分を仲介業者に任せることで、手軽に案件を進める一方で、その代償として手数料がかかり、報酬が減るというデメリットがあります。
一方、直接契約では報酬の全額を手にでき、自分のペースで契約条件を調整できる柔軟性がありますが、その分、契約管理や支払いのトラブル対応など、全てを自分で行う責任が伴います。
どちらの契約形態を選ぶかは、フリーランスとしての働き方やリスク管理の意識、また手間をどこまで負担できるかによって決まります。
委任契約
委任契約は、受託者(フリーランス・個人事業主)が特定の行為を行うことを依頼者(クライアント)が委任する契約です。委任契約の特徴は、具体的な成果物を要求せず、一定の行為を行うことに対して報酬が支払われる点です。
例えば、法律相談を行う弁護士や、税務処理を依頼する税理士などの業務は、委任契約に該当します。この契約では、依頼者は業務遂行に対する結果よりも、行為そのものに価値を置くため、業務の成果物が必ずしも期待通りでなくても、報酬が支払われます。
しかし、受託者は善管注意義務を負っており、業務遂行において一定の注意を払う義務があります。
準委任契約
準委任契約は、業務の遂行に対して報酬が支払われる契約であり、特にITの運用保守業務などでよく見られます。
例えば、システムエンジニアが企業のITインフラの運用やメンテナンスを行う場合、準委任契約で業務を遂行します。この契約では、一定の期間や時間ごとに報酬が支払われることが多く、作業内容や達成する成果よりも、作業プロセス自体に報酬が支払われます。
例えば、クラウドサーバーの監視業務を月単位で担当し、障害対応やシステムのパフォーマンスを保つ業務は、成果物として具体的なアウトプットがないため、準委任契約が適しています。
準委任契約では、クライアントが求めるシステムの安定稼働を目指すことが主な目的となり、過程が重視されます。
請負契約
請負契約は、フリーランスが具体的な成果物やプロジェクトの完了を条件に報酬を得る契約形態です。
IT業界では、アプリケーション開発やウェブサイト制作などが請負契約の代表例にあたります。例えば、クライアントが新しいスマホアプリを開発したいと依頼し、そのアプリが完成し納品された時点で報酬が支払われる形式です。
請負契約では、フリーランスは成果物の品質や納期に責任を持つ必要があり、成果が期待通りでない場合には修正や再作業が求められることがあります。そのため、フリーランスにとってはリスクも高い一方で、結果を出すことで高額な報酬を得られる可能性が高い傾向にあります。
成功報酬型とも言える請負契約は、プロジェクト完了にコミットできるエンジニアにとっては、大きなチャンスとなるでしょう。
フリーランス・個人事業主の直接契約のメリット
フリーランスや個人事業主がクライアントと直接契約を結ぶことには、報酬や条件面でさまざまなメリットがあります。
主な特徴は、仲介業者を通さないため、報酬の手取りが増えるだけでなく、契約内容を自分で交渉し、クライアントに希望を直接伝えることができる点です。
ここでは、具体的なメリットについて3点、紹介していきます。
仲介手数料・サービス利用料がかからない
フリーランスが仲介業者やクラウドソーシングプラットフォームを利用する場合、報酬の一部が手数料として差し引かれるのが一般的です。
例えば、クラウドソーシングサービスでは、受注した案件の報酬から10~20%程度のサービス利用料が差し引かれることがあります。しかし直接契約では、こうした手数料がかからず、報酬の全額がフリーランスの手元に入るため、同じ仕事量でも収入が増えるというメリットがあります。
また、仲介手数料がないことで、報酬額の交渉がより柔軟になります。例えば、業務にかかる時間や難易度に応じてクライアントと適切な報酬を直接話し合うことができ、手数料を気にせずに契約を結べるのが直接契約のメリットともいえます。
仲介を介さないことで、取引がよりシンプルかつ効率的に進行するため、仕事の効率も向上するでしょう。
契約内容を自分自身で交渉できる
直接契約のメリット2つ目は、契約内容を自分自身で交渉できる点です。
仲介業者を通す場合、決められた契約条件に従わなければならないケースが多い傾向にありますが、直接契約では、報酬や納期、業務内容など、自分の希望に合わせた条件をクライアントと話し合えます。
例えばフリーランスのエンジニアの場合、直接クライアントと契約を交わす場でプロジェクトの進行スケジュールや開発環境の選定について、自身の働きやすい条件を伝えることが可能です。業務の範囲が広すぎる場合には調整を依頼したり、報酬を上げる交渉も間接契約よりは容易にできます。
また、長期的な契約を提案し、安定した収入を確保するための話し合いも可能です。自分で交渉できることにより、理想の働き方や条件に近づけられるため、仕事に対するモチベーションも高まるでしょう。
希望する条件を詳細に伝えやすい
直接契約では、希望する条件をクライアントに直接伝えることができるため、業務の進行がスムーズになるケースが多いです。
仲介業者を挟んだ間接契約の場合、フリーランスの意向が十分に伝わらないことがあり、結果としてミスマッチが生じるケースもありますが、直接契約ではそうした問題を回避できます。
さらに、報酬や納期に関する交渉も、直接話し合いを行うことで、互いに納得のいく契約を結べるでしょう。
クライアントとの信頼関係も築きやすく、今後の長期的な取引につながることも多い傾向にあります。
フリーランス・個人事業主の直接契約のデメリット
直接契約には多くのメリットがある一方で、フリーランスや個人事業主にとっては負担やリスクも伴います。
ここでは、直接契約に伴う主なデメリットを詳しく見ていきます。
営業や単価交渉などを全て自分自身でこなす必要がある
フリーランスが直接契約を行う場合、営業活動から契約内容の交渉、仕事の獲得に至るまで全て自分で対応する必要があります。
特に新規クライアントを獲得するためには、継続的に営業活動を行う必要があり、それにかかる時間や労力は少なくありません。
例えば、ITエンジニアであれば、ポートフォリオの作成やSNSでの自己アピール、業界イベントへの参加など、仕事を得るための準備を怠らないことが求められます。
また、単価交渉も重要な業務の一つです。報酬が低く設定されている場合には、自分でクライアントと交渉し、適正な価格に引き上げるスキルが必要です。
しかし、営業や交渉に不慣れな場合、仕事を得られないことや、適正な報酬を得られないリスクがあります。こうした営業や交渉の負担を軽減するためには、事前に相場を調査し、交渉術を磨くことが大切です。
自分自身で契約を締結する必要がある
直接契約では、契約書の作成や内容確認を全て自分で行う必要があります。
仲介業者を利用する場合、標準的な契約書が用意されることが多いため、手続きは簡単ですが、直接契約ではそうはいきません。特に、契約内容に不備があった場合、フリーランスが法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、業務範囲が曖昧であったり、支払
条件が明確でなかった場合、後から追加作業を要求されたり、報酬の支払いが遅延するリスクがあります。
このようなトラブルを避けるためには、契約書をしっかりと確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。また、業務の範囲や納期、報酬の支払い条件を明確にしておくことも欠かせません。契約を結ぶ際には、曖昧な表現を避け、具体的な内容を取り決めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。電子契約サービスを活用して契約の締結をスムーズに行うことも、効率的な方法の一つです。
悪徳業者や詐欺のリスクがある
直接契約では、悪徳業者や詐欺に遭うリスクも伴います。
仲介業者を通さないため、クライアントの信頼性を自分で確認する必要があり、特に初めて取引する相手の場合は、未払いのリスクや、不適切な契約条件を押し付けられることもあるでしょう。契約後にクライアントが報酬を支払わずに音信不通になるケースや、最初は高報酬を提示されても後で報酬が大幅に減額されるケースも実際に存在します。
対策としては、事前にクライアントの信用調査を行うことが効果的です。過去の取引実績や評判を確認するために、業界のネットワークを活用したり、クライアントからの紹介案件を優先することが有効です。
また、契約時には必ず書面で詳細な契約内容を取り決め、前払い報酬や分割払いを取り入れることで、リスクを軽減できます。
さらに、怪しい条件や過度に良い話には慎重になることが大切です。不明瞭な点がある場合は契約を進める前に確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しておきましょう。
直接契約する際の注意点
フリーランスや個人事業主がクライアントと直接契約を結ぶ場合、トラブルを避け、業務をスムーズに進めるためには、契約書の内容が非常に重要です。
特に業務委託契約書には、後で問題になりそうなポイントをしっかりと記載しておく必要があります。
業務委託契約書に必要事項を明記する業務委託契約書は、業務の進行に関する条件を明確にするための重要な書類です。
業務委託契約書に記載すべき事項を明確にしておくことで、フリーランスとクライアントの双方にとって、安心して取引ができる環境を整えられます。
契約内容に関する具体的な項目をしっかりと確認した上で、次に説明する要素を取り入れてから契約を締結しましょう。
契約形態
契約書には、契約形態を明確に記載しましょう。
「委任契約」「準委任契約」「請負契約」などの形態を指定することで、業務範囲や成果物に対する責任が変わります。
特にIT分野では、アプリケーション開発のようなプロジェクトベースの仕事では請負契約が一般的ですが、運用保守業務などでは準委任契約が選ばれることがあります。
契約形態の違いに応じて、フリーランスが負うべき責任やリスクが変わるため、必ず確認し、双方が納得できる契約形態を選択しましょう。
契約期間
契約期間を設定することで、業務がいつからいつまで行われるのかを明確にできます。
例えば、ウェブ開発プロジェクトの場合、1か月単位や6か月単位で契約を締結し、その期間内に業務を完了させるという形で記載します。また、契約更新の有無についても明示することで、長期的な関係を築く際に役立つでしょう。
契約期間を曖昧にしてしまうと、クライアントとの間で「いつまでに業務を終了させるのか」という点でトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。
業務内容
業務内容は、契約書の中で最も重要な項目にあたります。
フリーランスが行うべき業務の具体的な範囲を詳細に記載することで、契約後の認識違いを防ぐことができます。
例えば、ウェブ開発を依頼された場合、「サイト設計」「コーディング」「デバッグ」など具体的な作業をリスト化して明記します。
業務内容を曖昧にしてしまうと、クライアント側から不必要な作業を要求されたり、追加業務が発生しても報酬に反映されないというトラブルの原因になるため、気をつけましょう。
報酬条件や支払いのタイミング
報酬の金額だけでなく、支払いのタイミングについても契約書に明確に記載しましょう。
支払い方法(銀行振込、クレジットカードなど)や、支払いがいつ行われるのか(納品後○日以内など)を具体的に定めておくことで、未払いリスクを減らせます。
長期プロジェクトの場合、月ごとの分割払いにするか、成果物納品後の一括払いにするかを事前に決めておくと良いでしょう。支払い遅延が発生した場合の対応策も契約書に盛り込んでおくことで、金銭トラブルの未然防止が可能です。
成果物の著作権
ITやデザイン業務において、納品した成果物の著作権が誰に帰属するかを明記することも重要です。
フリーランスが作成したコードやデザインの著作権を自分が保持するのか、クライアントに譲渡するのかを契約書で明確にしておくことで、後の著作権に関するトラブルを避けることができます。
例えば、ウェブサイトのデザインを納品した場合、納品後もそのデザインを再利用できるかどうかは、契約内容によって異なるため、事前にしっかりと取り決めておく必要があります。
再委託の可否
フリーランスが業務を他者に再委託できるかどうかも、契約書に明記しておく必要があります。
なお、再委託とは、フリーランスや個人事業主がクライアントから受けた業務の一部または全部を、別の第三者に委託することを指します。
再委託を許可する場合、信頼できる協力者に業務の一部を任せることで効率的に作業を進めることが可能です。ただし、再委託が禁止されている場合は、全ての業務を自分でこなさなければならず、業務量が増えるリスクがあります。
特に委任契約や準委任契約では、依頼者(委任者)が受任者個人の能力や専門性に期待して業務を依頼する契約であるため、再委託は原則として禁止されています。
大規模プロジェクトなど、再委託を許可してもらうことで、より柔軟に対応できる場合もありますが、クライアントに了承を得る必要があるため、契約時に確認しましょう。
秘密保持
業務上知り得た情報の取り扱いについて、秘密保持義務を契約書に記載することは必須です。
特にIT分野では、顧客のデータや開発に関する機密情報を扱うケースが多く、情報の漏洩を防ぐために秘密保持契約(NDA)を結ぶことが一般的です。
例えば、ソフトウェア開発の依頼を受けた際、クライアントのシステム仕様や顧客情報を取り扱う場合があります。知り得た情報を第三者に漏らさないよう、フリーランスは責任を持つことを契約書に明記しておくことが重要です。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、納品物が契約内容と合致しない場合に生じる責任を指します。
例えば、クライアントが要求する仕様に基づいてシステムを開発したものの、納品物がその仕様を満たしていなかった場合、フリーランスは修正や再作業を行う義務が生じることがあります。
契約不適合責任をどの範囲まで負うのかを明確にしておくことで、フリーランスとクライアントの間でのトラブルを防ぐことができます。「納品後一定期間内であれば無償で修正対応を行う」という条項を設けるケースも一般的です。
禁止事項
契約書には、フリーランスやクライアントが遵守すべき禁止事項を明記することも重要です。
例えば、IT分野であれば納品物を無断で第三者に提供したり、クライアントの競合他社と取引したりすることを禁止する条項を設けることが多い傾向にあります。
禁止事項をあらかじめ設けておくことで、フリーランスとクライアントの関係が公正に保たれるとともに、ビジネス上の利益が守られます。違反があった場合の罰則や契約解除の条件についても契約書に記載しておくことで、予期せぬトラブルに備えられるでしょう。
損害賠償
契約書には、損害賠償に関する条項を設け、契約違反が発生した場合の対応を明確にしておく必要があります。
例えば、フリーランスが納期に遅れた場合や、納品物が仕様に合わずクライアントに損害を与えた場合には、損害賠償を請求される可能性があります。
逆に、クライアント側の責任で契約が履行できなかった場合にも、フリーランスが損害賠償を請求できるように、双方の賠償義務について取り決めておきましょう。
直接契約に向いているフリーランス・個人事業主はこんな人!
フリーランスや個人事業主として、クライアントとの直接契約には多くのメリットがありますが、それに伴う責任も増えます。
そのため、全てのフリーランスが直接契約に適しているわけではありません。
ここでは、直接契約に向いているフリーランスの特徴を紹介します。
営業や交渉事が得意
直接契約では、営業や交渉力が重要なスキルとなります。
仲介業者を介さないため、自分自身でクライアントを探し、提案を行い、報酬や業務内容の条件を交渉する必要があるからです。例えば、フリーランスのデザイナーが自分でクライアントにアプローチし、ポートフォリオを提示しながら報酬や納期を交渉する場面が考えられます。こうした営業活動を積極的に行い、自分の価値を相手に伝えることが得意な人は、直接契約で多くのチャンスをつかめるでしょう。
なお、営業活動に不慣れな人は、対策としてオンラインでの自己ブランディングを強化することがおすすめです。ウェブサイトやSNSを活用して、実績やスキルをアピールする場を作ることで、営業力を補完することができます。
また、交渉の基本を学び、報酬や契約条件についての交渉力を鍛えることも大切です。
契約処理や請求業務など事務処理能力がある
フリーランスが直接契約を行う際には、契約書の作成や請求書の発行、納税手続きなど、多くの事務作業が発生します。こうした事務処理能力に優れている人は、直接契約での業務を効率的に進めることができるため、直接契約にも向いているといえます。
事務処理能力に不安がある方は、対策として、請求書の発行や契約管理をサポートするクラウドツールを利用すると、事務作業の負担軽減が可能です。さらに、契約書の基本知識を学び、トラブルを避けるための法的リスクに対する対応力を高めておきましょう。
エージェントに支払う手数料が勿体ないと感じている
直接契約を行う最大のメリットのひとつは、エージェントや仲介業者に支払う手数料をカットできる点です。
クラウドソーシングサービスやエージェントを利用すると、報酬の10〜20%が手数料として差し引かれることが一般的です。そのため、これらの手数料がもったいないと感じる人は、直接契約に切り替えることで、報酬の取り分を大きく増やすことができます。
例えば、フリーランスエンジニアがエージェントを通じて契約すると、1ヶ月の報酬が50万円の場合でも、5万〜10万円が手数料として差し引かれてしまいます。一方で、同じ仕事でも直接契約を行えば、手数料分を全て自分の収入とすることができ、年単位で考えると大きな差が生まれます。
人脈が広く、仕事のツテがある
広い人脈を持ち、仕事のツテが多いフリーランスの方は、直接契約での仕事獲得がスムーズに行えます。
中でも信頼できるクライアントからの紹介やリピート案件がある場合、仲介業者を通さずに安定的に仕事を得ることができるため、直接契約に向いているでしょう。過去に取引のあったクライアントから次のプロジェクトを直接依頼されるケースは、人脈があるフリーランスの典型的なメリットです。
人脈を作るためには、既存のクライアントとの信頼関係を深め、継続的な取引ができるような努力を怠らないことが大切です。また、業界イベントや交流会などに積極的に参加し、新しい人脈を広げることで、さらなる仕事のチャンスを増やせるでしょう。
訴求できるスキル・実績がある
自分のスキルや実績に自信があり、それを訴求できる人も、直接契約に向いています。
クライアントにとって、フリーランスを直接契約するメリットは、その人が持つ特定のスキルや実績が魅力的であるからです。例えば、SEOに強いウェブライターや、高度なプログラミングスキルを持つエンジニアなど、専門性が高いスキルを持っている場合、直接クライアントから依頼が来やすくなります。
対策として、自分の実績を明確にアピールできるポートフォリオや事例を用意することが効果的です。
また、クライアントに対して具体的な成果を示すことで、次の契約につながりやすくなります。
フリーランス・個人事業主が直接契約する為に準備すること
フリーランスや個人事業主が直接契約を成功させるためには、事前の準備が欠かせません。
スキルを明確に把握し、クライアントに効果的にアピールするためのポートフォリオや契約書のひな形を準備しておきましょう。また、直接交渉に向けてクライアントとの連絡や面談も必要です。
ここでは、具体的に準備すべき項目について詳しく解説します。
スキルの棚卸しをする
まずは、自分のスキルや実績を整理することが重要です。
スキルを整理することで、自分がどのような仕事を提供できるのか、クライアントにアピールできるスキルセットを明確に把握できるようになります。
例えば、ITエンジニアの場合、プログラミング言語の知識やプロジェクト管理経験、特定のツールに精通しているかどうかをリストアップしておくと良いでしょう。また、過去の成功事例やクライアントからの評価をまとめておくことで、具体的な実績として示すことができます。
定期的に自分のスキルを更新し、新しい技術や資格を取得した際には即座に反映させるようにしましょう。また、スキルの優先順位を付け、どの分野で自分が特に強みを持っているのかを整理することで、クライアントへの訴求ポイントを明確にできます。
ポートフォリオを作成する
スキルの棚卸しが完了したら、次にポートフォリオを作成します。
ポートフォリオは、クライアントに自分の実績やスキルを具体的に示すための履歴書のようなものです。ウェブデザイナーやライター、プログラマーなど、視覚的な成果物や具体的な実績がある場合、これを分かりやすく整理して提示することで、クライアントに自分の価値を理解してもらいやすくなります。
例えば、ウェブデザイナーであれば、過去に制作したサイトのスクリーンショットやリンクを掲載し、デザインの意図や使用したツールについて説明することが効果的です。
対策として、ポートフォリオはオンラインでも簡単にアクセスできるよう、ウェブサイトやPDF形式で用意しておくと良いでしょう。
また、業務内容に応じて、クライアントごとにカスタマイズしたポートフォリオを用意することで、よりターゲットに合った提案が可能になります。更新も定期的に行い、常に最新の実績を反映させることが大切です。
業務委託契約書の雛形を作成する
直接契約を結ぶ際には、業務委託契約書が必要です。
クライアントごとに一から業務委託契約書を作成するのは手間がかかるため、あらかじめひな形を用意しておくことが望ましいでしょう。契約書には、業務内容・納期・報酬・支払い条件・著作権の帰属・秘密保持・損害賠償など、重要な事項を明記しておきます。
例えば、プログラミングの案件では、ソースコードの著作権をフリーランスが保持するのか、クライアントに譲渡するのかを明確にしておく必要があります。
インターネット上には、業務委託契約書のテンプレートが無料で手に入るサイトもあるため、自分の業務内容に適した契約書をカスタマイズしておきましょう。
契約書に関して不安がある場合は、弁護士に確認してもらうのもおすすめです。大規模なプロジェクトや高額な契約では、法的なリスクを十分に理解した上で契約を結ぶ必要があります。
クライアントへ連絡・面談をする
直接契約を結ぶためには、クライアントとのコミュニケーションが欠かせません。
まず、クライアントに自分をアピールするための連絡を行い、できれば面談をセッティングしておくと良いでしょう。
直接会うことが難しい場合でも、ZOOMなどのオンラインビデオ会議や電話、チャットを通じて、業務内容や契約条件について詳細に話し合うことが大切です。
例えばWebライターの方であれば、記事の執筆内容や納期について、事前にしっかりとすり合わせを行うことで、後のトラブルを防げます。
なお、クライアントと連絡を取る際には、メールやメッセージで明確に内容を伝え、記録として残しておくことも良い方法です。面談では、契約書に基づいた具体的な提案を行い、クライアントの要望をしっかりと把握しておきましょう。
また、事前に業務内容を整理し、相手が求める価値を提供できるよう準備をしておくことが大切です。
まとめ
今回の記事では、フリーランスが直接契約を選ぶ際のメリットとデメリットについて解説しました。
結論をお伝えすると、「直接契約は自由度が高い反面、しっかりとした準備とリスク管理が求められる」です。
直接契約の最大のメリットは、仲介手数料がかからず、報酬を全て自分のものにできる点や、契約内容を自由に交渉できる点にあります。
また、クライアントとの信頼関係を築くことで、長期的なパートナーシップを確立するチャンスも広がります。
しかし、営業や契約処理などの事務作業、法的リスクの管理など、自分自身で対処しなければならない責任が増えることも事実です。フリーランスとして成功するためには、今回の記事で説明したメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った契約形態を選びましょう。
自分の状況やスキルに合った契約方法を選び、直接契約をうまく活用すれば、フリーランスとしてのキャリアをさらに広げられるでしょう。
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。