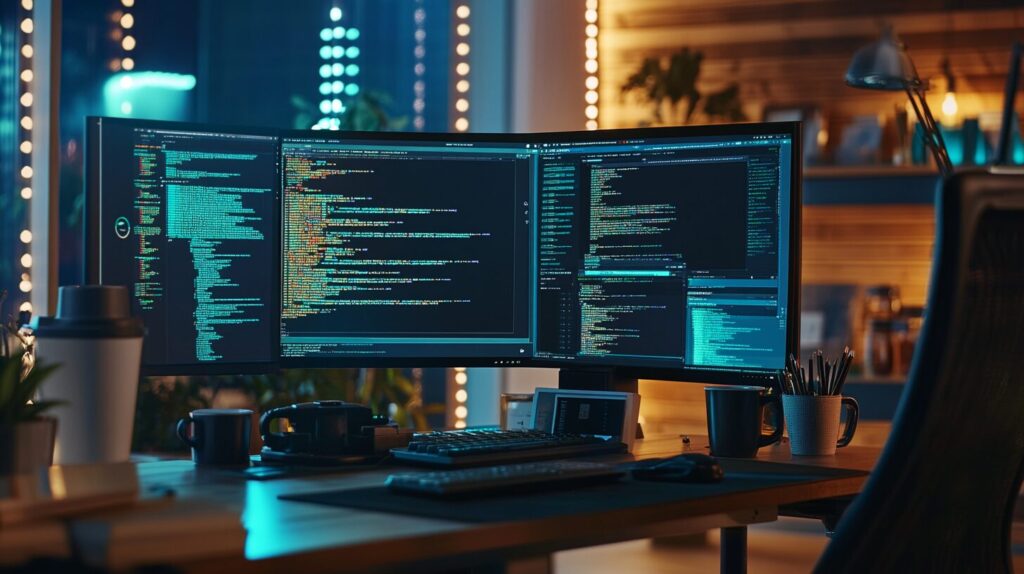フリーランスエンジニアの雇用形態完全ガイド|正社員・派遣との違いと契約リスクを徹底解説

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
モバイルアプリやウェブサービス、企業の基幹システムなど、IT業界の領域は広がり続け、その現場を支えるエンジニアの役割も多様化しています。そうした背景のなかで、会社に雇用されるのではなく、自らの裁量で案件を選び、自由なスケジュールで働くフリーランスエンジニアという働き方が注目を集めています。正社員や派遣社員に比べ、収益の上限を引き上げやすいメリットがある一方で、社会保険の問題や契約リスクなど、会社員時代には経験しなかった課題に直面する可能性も少なくありません。
ここでは、フリーランスエンジニアの雇用形態や法的な位置づけ、正社員や派遣社員との具体的な違い、契約時に注意すべきリスク、さらに長期的に安定したキャリアを築くポイントについて詳しく解説します。これから独立を考えている方や、すでにフリーランスとして活動していて契約周りの知識を整理したい方など、多くのエンジニアに役立つ情報を網羅的に取り上げていきます。
フリーランスエンジニアとはなにか
企業に雇用されないエンジニア
フリーランスエンジニアとは、企業に正社員や派遣社員として雇用されるのではなく、自らが事業主となり、業務委託契約や準委任契約を結んで報酬を得るエンジニアの働き方を指します。企業のオフィスに常駐している場合でも、正社員とは異なる法的立場であることが最大の特徴です。企業と対等な契約関係を結ぶ一方で、労働基準法などの労働者保護は受けにくく、社会保険や税金といった面で自己管理が求められます。
多くの場合、フリーランスエンジニアは個人事業主として開業届を提出し、国民健康保険や国民年金に加入する形で活動します。青色申告などで節税を行いながら、複数の案件を並行してこなすことも可能です。これは、会社員時代には得られない収入の伸びや、勤務地や働く時間の自由度を手にすることを意味する一方、案件の獲得や契約リスクの管理など、さまざまな課題も同時に発生します。
特徴的な契約形態
フリーランスエンジニアは「雇用契約」ではなく「業務委託契約」や「準委任契約」を結ぶため、企業からの指揮命令を受ける労働者としての立場とは異なります。理想的には、働く場所や時間、作業手段をエンジニア自身の裁量で決定し、納品物や成果物に対して報酬を得る形です。企業によっては常駐型のフリーランスという形で、見た目には社員同様に働く場面も多いのですが、法的に見ると指揮命令系統から外れているのが原則となります。
もっとも、現場での実態が社員と変わらないほどの管理を受けていると、偽装請負が疑われる場合があります。このあたりは正社員や派遣社員と大きく異なるポイントであり、契約書の内容や就業実態がどこまで独立性を保っているのかが注目されます。
正社員との違い
雇用契約か業務委託契約か
正社員は企業と労働契約を結び、就業規則や人事評価、社会保険、給与体系などが整備された環境のなかで働きます。企業は雇用する責任として、厚生年金や健康保険の折半負担、残業代の支払いなど、労働基準法に基づいた義務を負います。そのため、正社員は雇用の安定や福利厚生の充実といったメリットを得られますが、勤務地や業務内容を企業に決められるという制約も伴います。
これに対してフリーランスエンジニアは労働契約ではなく、業務委託契約をベースとしています。労働基準法が直接適用されないため、残業代や有給休暇の概念もなく、成果物の納品や稼働時間などを自由に決定できる代わりに、社会保険や年金などは自分で手配しなければなりません。収入が高ければ会社員より稼げる半面、不調な時期には収入が激減するなど安定性に欠けることも多いです。
組織内での位置づけ
正社員の場合は企業の一員としてプロジェクトに参画し、評価や昇給のシステムを通じてキャリアを積み上げるのが一般的です。フリーランスエンジニアはその企業の組織には属していないため、人事評価や役職などは存在しません。代わりに、プロジェクトベースで報酬を得て、一定期間の業務が完了すれば契約終了となるか、あるいは更新を行う形になります。
組織文化へのコミットや長期的な安定を求める人は正社員を好む傾向がありますが、自分のペースでスキルを高めたり、複数の案件を同時並行で進めたりしたい人にはフリーランスの柔軟さが魅力となるでしょう。ただし、企業の正社員と同じようにフルタイム常駐していると、企業の就業規則に準じた働き方を無理に求められるケースもあり、偽装請負リスクが指摘されることもあるため注意が必要です。
派遣社員との違い
派遣契約と雇用契約の関係
派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先企業へ出向いて働く形態を取ります。この場合、給与や社会保険は派遣元企業が管理し、派遣先企業は業務指示を行う立場にあります。労働者としての権利保護は派遣元の責任で行われるため、残業代や有給休暇などは派遣社員にも適用されます。
フリーランスエンジニアの場合は企業に雇用されるわけではなく、あくまで業務委託を受けて独立した立場で仕事をする点が派遣社員との大きな違いです。どちらも勤務地や業務の指示が派遣先やクライアントによって与えられる場面は似通っていても、法的には全く別の契約形態です。
労働者派遣法との関係
派遣社員は労働者派遣法によって保護され、派遣先企業で働く際の制限や待遇に関するルールが定められています。一方、フリーランスエンジニアはこの保護を受けず、あくまで業務委託契約や準委任契約がベースとなるため、労働法の適用を受けるわけではありません。派遣元企業から給与が支払われるわけでもなく、就業場所や時間を細かく指示されれば偽装請負が指摘される可能性も高まります。
そのため、フリーランスでありながら実質的に派遣社員のような働き方をしている場合、法的に問題がないか確認することが大切です。明確に業務の進め方を自分で決められる状態であればよいですが、企業の就業規則に合わせて勤怠管理されているなどの要素があれば、労働者とみなされるリスクがあります。
業務委託契約と偽装請負
本来の業務委託のあり方
業務委託契約は、成果物やサービスの提供に対して報酬を得る形の契約を指します。フリーランスエンジニアが企業から業務を請け負うとき、納品物の品質や納期、報酬額などを契約書で定義し、それに沿って作業を進めるのが本来の姿です。作業場所や時間を基本的にフリーランスエンジニア側が自由に決定でき、成果物が完成すれば契約を終了または更新するといった流れになります。
この形態なら労働者性は発生せず、企業もフリーランスも対等な関係で成果をやり取りします。ただ、企業が作業手順を細かく指示し、就業時間を厳格にコントロールし、勤怠を管理する状態になると、業務委託ではなく労働契約に近いとみなされやすくなります。こうした状態が偽装請負として指摘されると、企業は派遣法違反などを問われる可能性があり、フリーランスとしての独立性も失われるため、注意が必要です。
指示命令が強すぎると偽装扱いに
偽装請負が発生する典型的なパターンとしては、フリーランスエンジニアがクライアント企業のオフィスで常駐し、プロジェクトマネージャーなどから日々のタスクや作業手順を細かく指示され、企業の就業規則に準じた勤怠管理や残業指示を受けているケースが挙げられます。この場合、実態は雇用と変わらないため、「ならば社会保険や労働基準法の適用も本来必要ではないか」と見なされ、偽装請負と判断されるリスクがあります。
フリーランスエンジニアの側も、無意識のうちに企業の命令系統に組み込まれてしまわないように契約時に業務範囲や納品物をしっかり定め、作業手段や時間の裁量を保つ努力が必要です。必要以上の勤怠管理や細部への干渉がある場合は、早めに契約書を見直すなどの対策を講じましょう。
フリーランスエンジニアの社会保険と税金
厚生年金と健康保険は対象外
フリーランスエンジニアは企業に雇用されていないため、厚生年金や健康保険の対象になりません。代わりに国民健康保険と国民年金への加入が基本で、保険料や年金保険料は全額自己負担となります。収入が上がるほど保険料も高くなるため、給与天引きが当たり前の会社員時代よりも、税金や社会保険に対する意識と管理が求められます。
報酬額が高い年には税金や保険料の負担が重くなる一方で、翌年度の収入が落ち込んだ場合でも保険料がすぐには下がらない仕組みがあるため、キャッシュフローの見通しを誤ると資金繰りに困ることがあるでしょう。こうしたリスクを軽減するため、あらかじめ納税用の資金を分けておくなどの計画性が大切です。
雇用保険と労災保険の対象外
フリーランスエンジニアは雇用保険の対象外となるため、失業した際に失業手当を受け取ることはできません。企業との契約が打ち切られれば収入は途切れ、次の案件を探す間の生活費は自力で確保しなければなりません。これがフリーランスとしての最大のリスク要因でもあるため、案件を複数持つことや貯蓄を用意することなど、常に不測の事態に備えた対策を講じておく必要があります。
また、業務上の事故や負傷に対しても労災保険が適用されず、医療費や休業補償は自己負担です。一人親方労災保険の特別加入などを検討したり、民間の所得補償保険に入ったりすることで、万が一のリスクを軽減できるかもしれません。ITエンジニアは現場作業のケガが少ない印象があるとはいえ、長期入院や突然の疾病などへの備えは重要です。
雇用保険と失業リスク
収入が途切れる危機
フリーランスエンジニアが抱える失業リスクは、案件の打ち切りやプロジェクト終了が突然訪れる点にあります。会社員なら人事異動や部署変更などで仕事を続けられる場合も多いですが、フリーランスは契約終了とともに報酬がゼロになる可能性が大きいです。このリスクに対抗するには、常に複数の案件パイプラインを作り、営業活動に力を入れる必要があります。
リピート案件や長期契約で安定収入を確保しておくことも一案です。ただし、ひとつのクライアントに依存しすぎると、そのクライアントが倒産したり予算カットをしたりした際に大きな打撃を受けます。リスク分散と収益の拡大を両立するには、高単価案件を狙うだけでなく、顧客層を複数に広げることが鍵となります。
契約形態のメリットとデメリット
フリーランスならではの自由
フリーランスエンジニアが業務委託契約を選ぶ最大のメリットは、自分が得意とする技術や興味のある領域に集中して活動できることです。就業場所や稼働時間も比較的柔軟で、リモート案件を中心に組み合わせれば国内外を問わずいろいろなプロジェクトに参加できます。会社員には難しい報酬の上限を超えやすいことも、大きな魅力と言えるでしょう。
一方で企業からの安定給与や福利厚生がなく、病気や育児などで休みを取ると収入が止まるリスクがあります。売上が伸びると税金や社会保険の負担が増え、事業拡大のタイミングで法人化を検討するにしても新たなコストが発生します。こうしたメリットとデメリットを総合的に判断し、自分のライフプランやキャリアステージに合うかどうかを考えることが重要です。
フリーランスエンジニアのキャリア構築
技術力と営業力
フリーランスエンジニアとして成功するためには、高い技術力はもちろん、案件を獲得するための営業力やコミュニケーション力も欠かせません。エンジニア同士のコミュニティで情報交換を行ったり、勉強会やカンファレンスで登壇することで知名度を上げ、新たな依頼を受けるチャンスを増やすのも効果的です。エージェントをうまく活用すれば営業面をサポートしてもらえる反面、仲介手数料の負担がある点も踏まえておきましょう。
また、単にプログラミングをこなすだけでなく、要件定義や設計段階からコンサルティングに関わるエンジニアは高単価を提示しやすい傾向にあります。マネージャーやディレクターに近いポジションまでカバーできる総合力を身につけることが、安定的なキャリア構築の鍵となります。
法人化による事業拡大
フリーランスとして活動を始めて収入が安定し、大きな案件を複数抱えるようになったら、法人化を検討する人も多いです。法人化すると「代表取締役」として社会的信用が高まるほか、節税や雇用の柔軟性も広がる可能性があります。一方で法人住民税や決算書作成などの義務が増え、社会保険への加入義務も生じます。
法人化によって一人で対応しきれないほどの案件をチームで請け負ったり、外注先として他のフリーランスを使うなどの手段を取れば売上をさらに伸ばせるかもしれません。ただし、純粋にエンジニアとしての作業がしたい人にとっては、経営者の立場になることが負担にもなるため、自分のキャリア方針やライフスタイルとのバランスを考慮して決断する必要があります。
エージェントを活用する際の注意点
仲介手数料と契約制限
フリーランスエンジニア専門のエージェントは、企業とのマッチングや契約調整、報酬の支払いなどを代行してくれるため、営業が苦手な人にとっては有益です。ただし、エージェントを通す場合は仲介手数料が差し引かれたり、一定期間は同じクライアントと直接契約ができないなどの制約が発生することもあります。自分がどの程度自由度を求めるのか、エージェントのサポート範囲と手数料率を比較検討してから契約を結ぶことが重要です。
長期的に見ると、エージェントを通して信頼関係を築いてから直接取引に移行したいと考える人もいますが、契約書に「直接契約禁止」の条項が含まれている場合には注意が必要です。違反すると違約金を請求される可能性もあるため、事前にしっかり説明を受け、自分の目的に合うかどうかを見極めましょう。
偽装請負のリスク
労働者性の判断ポイント
偽装請負が問題になるのは、企業がフリーランスエンジニアを雇用しない形を取っているのに、実態としては労働契約と変わらない指揮命令関係がある場合です。たとえば、企業が勤怠管理を行い、業務のやり方を詳細に指示し、フリーランスが自分の裁量で作業を進められない状態にあるなどが挙げられます。
労働者性を判断する際には、報酬の算定方法や時間管理、作業場所の拘束、機材の貸与状況などさまざまな視点から見ることになります。もし偽装請負と認定されれば、企業側は派遣法違反などの法的リスクを負うだけでなく、フリーランスエンジニア側も社会保険未加入などの問題が明るみに出る恐れがあります。双方にとって不利益な結果となり得るため、事前の契約段階で独立性を維持できるかどうかをきちんと確認することが大切です。
リモート案件の増加
時差や言語のハードル
リモートワークが増えると、フリーランスエンジニアは地理的制約がなくなるため、海外企業や地方のクライアントなど多彩な選択肢にアクセスできます。ただし、時差や言語、文化の違いによるコミュニケーションギャップが発生しやすく、プロジェクト管理にも工夫が求められます。日本国内であってもリモート下では情報共有が不足しやすいので、オンライン会議やタスク管理ツールを駆使してこまめに進捗を共有し、納期遅延や齟齬を防ぐ必要があります。
また、リモート案件だからこそ労働者性の判断が曖昧になりがちですが、時間の拘束や指示内容が細かく規定されると、実質的に労働契約と同等になってしまうリスクがあります。納品物ベースのやり取りを徹底する、成果物を明確に定義するなど、契約上の独立性を示す工夫が必要となります。
複業・副業エンジニアという選択
会社員を続けながらのフリーランス活動
副業が解禁される企業が増えたことで、正社員として安定収入を得ながら週末や夜間にフリーランスの案件を受けるエンジニアも増加傾向にあります。これによりリスク分散が図れる一方、労働時間が大幅に延びるため体力や健康管理が課題となりやすいです。また、副業を禁じる企業もまだあるため、就業規則や競業避止条項をしっかり確認しておかないとトラブルに発展しかねません。
一方、副業エンジニアとしてフリーランス活動を続けるうちに、案件の規模が拡大し本業の収入を上回るケースも出てきます。そこで思い切って独立を選ぶか、あくまで副業として留めるかを判断するためには、自身のキャリアプランや家族の状況などを含めた総合的な検討が欠かせません。
報酬の交渉術
提案力と根拠づけ
フリーランスエンジニアが報酬交渉を行う際には、自分がプロジェクトにもたらせる価値を具体的に説明し、企業が納得できる根拠を示すことが重要です。たとえば、過去の実績でどれだけ開発期間を短縮できたか、コスト削減に貢献したか、技術的ハードルの高い課題をどのようにクリアしたかなど、具体例を用いて提案すると相手も評価しやすくなります。
また、あらかじめ業界の相場や周囲のエンジニアの報酬水準をリサーチしておき、自分のスキルレベルと照らし合わせた上で交渉に臨むと、的外れな金額を提示して断られるリスクを減らせます。逆に、安売りしすぎると自分の首を絞めるだけでなく、業界全体の相場を下げてしまう可能性もあるため、慎重なバランス感覚が求められます。
国際的な視点と先端技術への追随
海外企業との契約
英語のコミュニケーションが可能であれば、海外のスタートアップやテック企業から直接案件を受注し、高報酬を得る機会が増えます。特にAIやブロックチェーン、クラウドなどの先端技術領域では、欧米を中心に需要が高く、日本国内よりもエンジニアのレートが高いことが多いのも注目点です。
ただし、海外との契約書は英文で作成されることが多く、準拠法や裁判管轄をどう設定するかなど、国内案件と比べて複雑な問題が増えます。国際送金の手数料や為替レートの変動、時差によるコミュニケーションロスなども考慮する必要があります。いきなりハードルが高いと感じる場合は、海外向けのエージェントや仲介サービスを利用すると手続きがスムーズになるでしょう。
保険と年金への備え
小規模企業共済やiDeCoの活用
フリーランスエンジニアが将来の年金や老後資金に不安を感じる場合、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった制度を活用する方法があります。小規模企業共済は国の機関が運営しており、毎月の掛金を積み立てることで、退職金的な意味合いの共済金を受け取れます。iDeCoは自分の拠出した掛金を自ら運用し、60歳以降に年金や一時金として受け取る仕組みで、掛金は全額所得控除の対象になるため節税メリットも大きいです。
ただ、運用リスクや受け取り条件も存在するため、制度の特徴をよく理解したうえで導入することが望まれます。一定以上の所得があるフリーランスエンジニアなら、これらの制度によって所得税や住民税を抑えながら老後資金を形成できる可能性があります。
法人化のタイミング
事業規模の拡大と社会的信用
フリーランスとして売上が拡大し、クライアントも大手企業や長期案件が多くなると、個人事業主のままでは信頼性や金融取引の面で不便を感じることがあります。法人化すれば法人名義で契約を結びやすくなり、大規模プロジェクトにも参入しやすくなる可能性があります。また、利益が一定額を超えると法人税のほうが個人事業主の所得税よりも税負担が小さくなる場合もあります。
ただし、法人化すると代表取締役として厚生年金や社会保険への加入義務が発生し、事務コストや決算の手間が増えます。どのタイミングで法人化するかは、収入額や将来の雇用計画、ビジネス拡大の見通しなどを総合的に判断する必要があります。エンジニアリング作業に集中したい人が安易に法人化すると、経営管理に時間を取られ、かえって非効率になる可能性もあるでしょう。
労働者性が争われるケース
雇用か請負かの線引き
フリーランスエンジニアが企業に長期間常駐し、就業規則や勤怠管理に実質的に従っている状態だと、後になって「実際には雇用契約だったのでは」と争われることがあります。これは企業側だけでなくフリーランス側にもリスクとなり、社会保険未加入や残業代未払いなど、さまざまな問題が浮上するきっかけとなります。
訴訟や労働基準監督署の調査などで労働者性が認定されると、企業は過去にさかのぼって未払賃金や社会保険料を求められるケースがあります。フリーランスエンジニアも本来は厚生年金に加入すべき立場だったという扱いになり、確定申告や保険手続きが複雑化するかもしれません。トラブルを避けるには、契約段階で独立事業主としての地位を明確にし、指揮命令や勤怠管理に関する条項を整理しておくことが大切です。
フリーランスエンジニア同士のコラボレーション
大型案件への共同対応
個人のスキルだけで対応困難な大規模プロジェクトでも、複数のフリーランスエンジニアがチームを組むことで受注できる可能性が高まります。デザインやフロントエンド、バックエンド、インフラなど、それぞれの得意分野を持つメンバーが集まり、案件ごとに効率よく役割を分担すれば、単価アップにつなげられることも多いです。
ただし、チーム内での契約関係を明確にしておかないと、収益分配や著作権の扱いなどで揉めるリスクがあります。契約主体を法人化してメンバーを業務委託で雇う形にするか、フリーランス同士で共同請負契約を結ぶかなど、法的な整備をしっかり行うことが重要です。マネジメントの役割を誰が担うのかも曖昧にすると、スケジュールや品質管理が混乱してしまう恐れがあります。
契約書に盛り込むべき要点
紛争を防ぐための取り決め
フリーランスエンジニアが企業と契約を結ぶとき、後々のトラブルを回避するために以下のような内容を確実に盛り込んでおくことが望ましいです。まず、契約の目的や業務範囲を具体的に記載し、納品物や成果物が何かを明確に定めます。次に、報酬の額や支払い条件(支払サイトや振込手数料の負担など)もはっきり書いておきます。著作権や知的財産権の帰属先、機密保持義務、競業避止条項の有無なども要チェックです。
納期の設定や瑕疵担保責任、契約解除の条件なども詳細に規定することで、万一の遅延や成果物不備があった際の対応がスムーズになります。企業が用意したひな形だけで進めると、フリーランス側に不利な条文が含まれている場合もあるため、可能であれば弁護士や行政書士にレビューを依頼すると安心です。
まとめ
フリーランスエンジニアの雇用形態は、正社員や派遣社員とは大きく異なる「業務委託契約」をベースとしており、企業との契約リスクや社会保険の問題、偽装請負などの法的リスクが常に存在します。正社員や派遣社員のように安定した給与や厚生年金の保護はないものの、働く時間や案件選びの自由度が高く、スキルや実績次第で報酬を大きく伸ばせる可能性もあるのが特徴です。
安定性を得るためには、複数の案件を確保したり、エージェントを活用したり、あるいは法人化によって組織として大規模プロジェクトに参入するなど、多面的な戦略が求められます。さらに、契約書の条項や社会保険の選択、税務管理などビジネス面の知識を磨くことで、トラブルを回避しながらキャリアを拡大できます。自分のスキルセットと働き方の希望、そしてライフステージを総合的に考えつつ、フリーランスエンジニアとして長期的に活躍するための基盤を整えることが何より重要となるでしょう。
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。