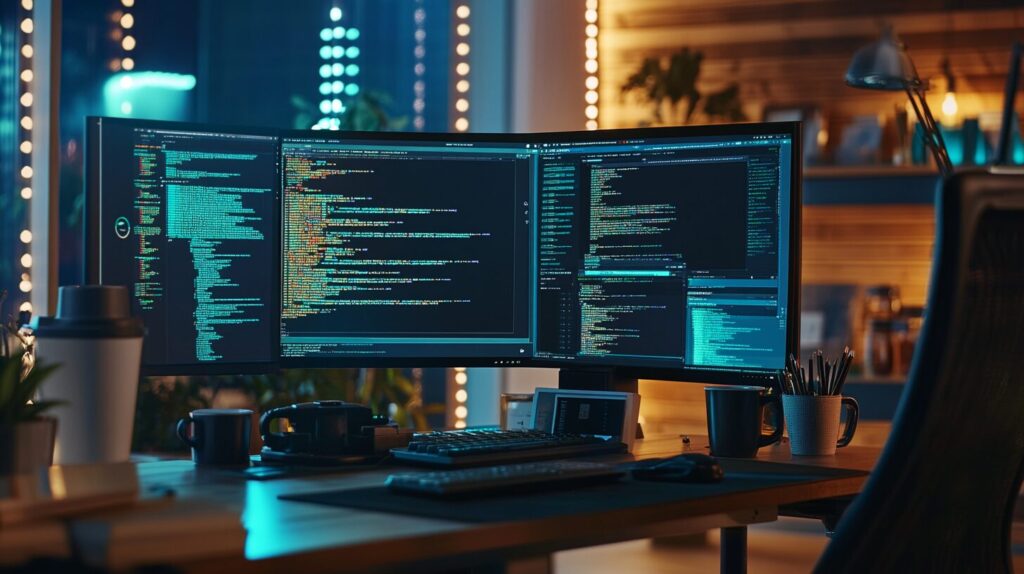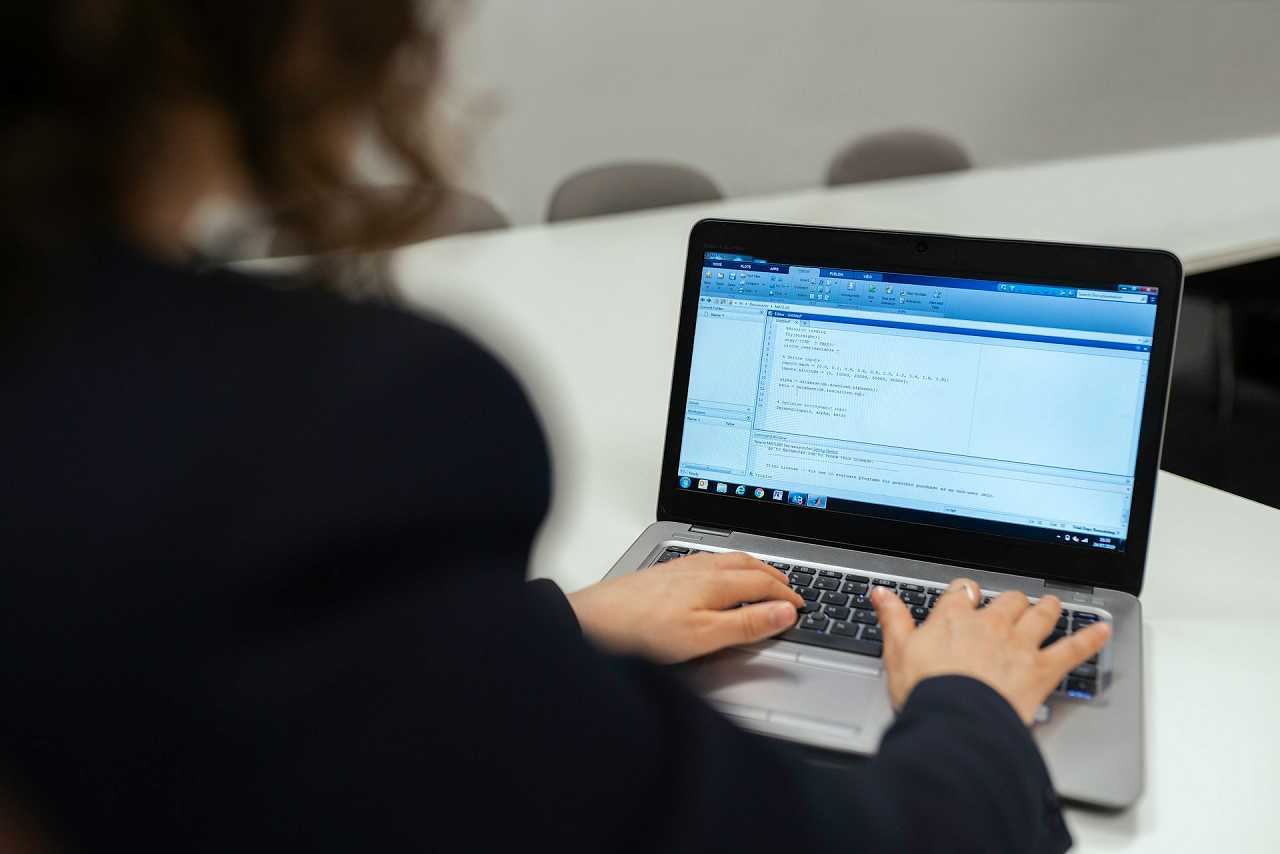個人事業主が事業用口座から生活費を引き出した時の仕訳方法は?仕訳例や確定申告での処理方法を解説

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
個人事業主として事業を運営する中で、事業用口座から生活費を引き出す場面に直面することは少なくありません。
しかし、その仕訳方法や確定申告での処理について正確に理解しておくことが重要です。
本記事では、事業主勘定の基本から、具体的な仕訳例、さらに確定申告での処理方法までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、事業用口座からの引き出しや経費処理の基本が理解でき、税務処理のトラブルを避けるための知識が得られます。
本記事で解説する税務処理のポイントを押さえ、正確な会計処理と税務対策を行うための知識を身につけましょう!
<この記事を読むとわかること>
- 事業主貸勘定と事業主借勘定の基本的な使い方
- 生活費や国民健康保険料の具体的な仕訳方法
- 家賃や水道光熱費の家事按分とその仕訳例
- 法人化(法人成り)のメリットと自分の給与の経費処理
- 確定申告での事業主勘定の処理方法
事業用口座から生活費を引き出した場合の勘定科目は?
個人事業主として活動していると、事業用資金を生活費に充てたい時がよくあります。
例えば、突発的な事故や病気、一時的に事業が停止してしまった時などの緊急時です。
このような場合に、借金ではなく事業用口座の資金を一時的に生活費に充てることができるのをご存知でしょうか。
ここでは、事業用口座から生活費を引き出した場合の勘定科目について詳しく解説します。
事業主勘定とは
事業主勘定とは、個人事業主が事業資金とプライベート用の資金を明確に区別するために使用する会計処理の一つです。
これは「事業主貸(じぎょうぬしかし)」と「事業主借(じぎょうぬししゃく)」の2つの勘定科目から成り立ちます。
事業主貸は、事業資金を個人的な用途に使用する場合に使用される勘定科目です。
例えば、事業用の銀行口座から生活費を引き出す場合や、事業用の資産を個人使用に転用する際に用いられます。
これは事業の経費とはならないため、適切に記録することが重要です。
一方、事業主借は個人資金を事業に投入する際に使用します。
例えば、個人的な貯金から事業の運転資金に充てる場合や、個人の資産を事業用に購入する際に使われます。
事業主が事業に対して資金を貸し付ける形になるため、これも正確に記録する必要があります。
このように、事業主勘定は事業用と個人用の資金の流れを整理し、事業の財務状況を正確に把握するための重要な手段です。
生活費は事業主貸勘定を使用する
個人事業主が生活費を支払う際には「事業主貸」勘定を使用することが重要です。
事業主貸として処理することで、生活費が事業の経費に含まれることを防ぎ、正確な経営状況を把握できます。
具体的な仕訳例として、事業用の預金から生活費として100,000円を引き出した場合、以下のようになります。
- 借方:事業主貸 100,000円
- 貸方:普通預金 100,000円
上記のように記録することで、生活費が事業の経費に混入することを避け、税務申告時の申告漏れを防ぐことが可能です。
事業主貸勘定の仕訳例
ここからは、わかりやすいようにいくつかの具体例をもとに仕訳の例を見ていきましょう。
生活費として20万円を引き出した場合
個人事業主が事業用口座から生活費として20万円を引き出す場合、この支出は事業の経費ではなく個人の支出に分類されます。
そのため、「事業主貸」勘定を使用して仕訳を行います。
<仕訳例>
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用項目 |
| 事業主貸 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 | 生活費引き出し |
この仕訳によって、事業用口座から引き出された金額が事業の経費ではなく、事業主の個人的な支出として記録されます。
国民健康保険料1万円を事業用口座から支払った場合
個人事業主が事業用口座から国民健康保険料1万円を支払った場合の仕訳は、以下のようになります。
国民健康保険料は個人の生活に関する費用であり、事業の経費として扱わないので「事業主貸」でOKです。
<仕訳例>
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用項目 |
| 事業主貸 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 | 国民健康保険料支払 |
この仕訳では、借方に「事業主貸」を記入し、貸方には「普通預金」を記入します。
これにより、事業用口座から国民健康保険料が支払われたことが記録されます。
社会保険料は確定申告で所得控除の対象となる
なお、個人事業主が支払う社会保険料は、確定申告において所得控除の対象となります。
所得控除を適用することで、課税所得を減少させることができ、結果として納めるべき所得税が軽減されます。
仕訳の際にミスがあると、こういった所得控除の制度がうまく活用できない可能性があるので、社会保険料の項目についてはしっかりと把握しておきましょう。
参考までに、所得税控除の対象となる社会保険は以下の通りです。
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 介護保険料
- その他の公的医療保険料
事業主貸で仕訳をする時は家事按分に注意
個人事業主が事業主貸で仕訳をする際には、「家事按分(かじあんぶん)」についてしっかりと理解しておくことが重要です。
家事按分は、個人事業主やフリーランスが自宅を事務所として使用する場合に、事業とプライベートの費用を分けて計上するための手法です。
家賃や電気代、水道代、インターネット料金など、事業と家庭の両方で使われる費用を事業用と個人用に分割して経費として計上します。
家事按分の割合は、以下の基準で決定します。
- 使用面積:自宅のうち事業用として使用している面積を基に按分
- 使用時間:事業用として使用している時間の割合を基に按分
最も一般的な方法は使用面積を基にする方法です。
家事按分は少しわかりづらい項目でもあるので、以下で具体的な例をもとに見ていきましょう。
自宅と事業用を兼用している場合の家賃
まずは、自宅と事業用を兼用している場合の家賃の家事按分についてです。
例えば、全体の面積が100㎡で、そのうち20㎡を事業用として使用している場合、按分割合は20%となります。
この場合の家賃の按分方法は以下の通りです。
- 全体の家賃:月額10万円
- 按分割合:20%
- 事業用の家賃:10万円 × 20% = 2万円
- 個人用の家賃:10万円 × 80% = 8万円
なお、按分割合は合理的であり、税務調査の際に説明できるように根拠を明確にしておくことが重要です。
家賃10万円の引き落としの仕訳例
家賃が10万円の引き落としの場合、仕訳表には以下のように記載することになります。
<仕訳例>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用項目 |
| 2024/05/29 | 地代家賃 | 20,000円 | 普通預金 | 20,000円 | 事務所使用分 |
| 2024/05/29 | 事業主貸 | 80,000円 | 普通預金 | 80,000円 | 家賃個人用分 |
上記の例だと、事業用部分は経費として計上され、個人用部分は事業主貸として処理されます。
つまり、事務所使用分の20,000円が所得控除の対象となります。
自宅と事業用を兼用している場合の水道光熱費
続いて、自宅と事業用を兼用している場合の水道光熱費の家事按分について見ていきましょう。
個人事業主が自宅を事業所として使用している場合、水道光熱費(電気代、ガス代、水道代など)の一部も事業用経費として計上可能です。
水道光熱費の按分は、「使用時間」と「使用面積」に基づいて按分していくことになります。
例えば、全体の使用面積が100㎡で、そのうち30㎡を事業用として使用している場合、按分割合は30%です。
月の水道光熱費が月額2万円の場合の按分は以下の通りです。
- 全体の水道光熱費:月額2万円
- 按分割合:30%
- 事業用の水道光熱費:2万円 × 30% = 6,000円
- 個人用の水道光熱費:2万円 × 70% = 14,000円
つまり、この場合だと事業用の光熱費の6,000円が所得税控除の対象となります。
所得税率は所得額により異なりますが、所得税率が20%の場合だと、事業用として計上された水道光熱費6,000円によって、所得税が1,200円減少します。
微々たる差かもしれませんが、こういった金額も積もり積もれば非常に大きな金額になってくるので、仕訳をする際はなるべく家事按分を適用しましょう。
個人事業主は自分の給与を経費にできる?
ここまで解説してきたように、個人事業主は様々な項目を経費として確定申告の際に申請できます。
一概に「個人事業主の方が最終的な税金が安くなるからお得!」とは言えませんが、所得が増えれば増えるほど節税の余地は多くなってきます。
では、自分の給与自体を経費にすることはできないのでしょうか。
自分の給与は経費にできない
結論からいうと、個人事業主はいかなる理由があっても自分の給与を経費として計上することはできません。
法的には、個人事業主は事業と個人が一体化したものとみなされます。
したがって、事業主自身への支払い(給与)は自己への支払いと同じとされ、経費として認められません。
個人事業主が経費として計上できるのは、事業に関連する以下のような支出です。
- 事業用の備品や消耗品
- 事務所の家賃や光熱費(按分計算が必要な場合もあり)
- 交通費や通信費
- 広告宣伝費
- 外注費や従業員への給与
ただし、従業員が家族である場合「青色事業専従者給与」として申請し、税務署の承認を受けた場合は経費にできます。
給与を経費にしたいなら法人化を検討
自分の給与を経費にしたいのなら法人化(法人成り)を検討しましょう。
法人化することで、事業と個人が法律上別の存在となります。
法人は独立した法人格を持つため、法人が事業主(社長や役員)に支払う給与は法人の経費として計上可能です。
これにより、法人の利益を圧縮し、法人税の負担を軽減できます。
ただし、法人化した際の税務処理の複雑さは個人事業主の比ではありません。
法的責任も増大するので、小さな申告漏れであっても「過少申告加算税」や「延滞税」が発生してしまいます。
そのため、そこまで多くの所得ではない場合、法人化はおすすめできません。
なお、一般的に所得が800万円を超えたあたりからが法人化の狙い目とされています。
プライベートのお金で事業の必要経費を立替払いしたら?
個人事業主になったばかりの時などには、資金がまだ十分ではないこともよくあります。
このような場合、プライベートのお金を事業の必要経費に充てることが可能です。
では、こういったケースではどのように仕訳をしていくべきなのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
事業主借勘定を使う
個人事業主がプライベートのお金で事業の必要経費を立替払いした場合、適切に会計処理を行うためには「事業主借勘定」という勘定科目を使用します。
事業主借勘定は、事業主が個人的な資金を事業に充てた際に用いられる勘定科目です。
この勘定を使用することで、事業資金と個人資金を明確に区別し、正確な経費管理が可能になります。
事業主借勘定は、主に次のような状況で使用されるのが一般的です。
- 個人資金の立替払い:事業の経費を個人の口座から支払った場合、その支出を「事業主借」として記録します。
- 個人資金の事業投入:事業用口座に個人資金を入金した場合、その入金を「事業主借」として記録します。
事業主借勘定を使用することで、個人と事業の資金の流れを正確に把握することができ、税務上の問題を防ぐことが可能です。
事業主借勘定の仕訳例
では、事業主借勘定の具体的な仕訳例を見ていきましょう。
ここでは、以下の2つのケースでの仕訳例を解説します。
- プライベートの口座から事業用口座へ5万円入金した場合
- 仕事で使う書籍をプライベートの口座から支払った場合
プライベートの口座から事業用口座へ5万円入金した場合
個人事業主がプライベートの口座から事業用口座へ5万円を入金した場合、この取引を記録するための仕訳は以下の通りです。
<仕訳例>
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用項目 |
| 事業主借 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 | プライベートからの入金 |
この仕訳では、事業用口座に入金された5万円を「事業主借」として記録し、個人の資金が事業に投入されたことを示します。
仕事で使う書籍をプライベートの口座から支払った場合
個人事業主が仕事で使用する書籍をプライベートの口座から購入し、その費用が1万円だった場合、この取引を記録するための仕訳は以下の通りです。
<仕訳例>
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用項目 |
| 事業主借 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 | 書籍購入費用 |
この仕訳では、プライベートの口座から支払った書籍の費用1万円を「事業主借」として記録し、事業のために個人資金が使用されたことを示します。
確定申告での事業主勘定の処理方法
前項で事業主勘定について紹介しましたが、事業主勘定の処理方法はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、確定申告の際の事業主勘定の処理方法についてご紹介します。
決算修正の時点で相殺する
確定申告を行う際、個人事業主は「事業主貸」と「事業主借」の勘定を適切に処理する必要があります。
決算修正の時点でこれらの勘定を相殺することで、事業の実態を正確に反映した決算書を作成することが可能です。
なお、相殺後の差額は「元入金(もといれきん)」に振り替えます。
これにより、翌年度の元入金が正確に計上され、次期の開始残高に反映できます。
例えば、決算時点で以下のような残高があったとしましょう。
- 事業主貸:50万円
- 事業主借:30万円
この場合の仕訳は以下の通りです。
<仕訳例>
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用項目 |
| 元入金 | 20万円 | 事業主貸 | 50万円 | 事業主貸の相殺 |
| 事業主借 | 30万円 | 元入金 | 30万円 | 事業主借の相殺 |
これにより、事業主貸と事業主借の差額20万円が元入金に調整され、翌期の資金繰りがしやすくなります。
決算書上で残高があっても問題ない
事業主貸や事業主借の勘定科目は、決算書上で残高が残っていても問題はありません。
これらの勘定科目は、個人事業主の事業と個人の資金の流れを明確にするために使用されるため、残高があることはむしろ自然なことです。
残高が残っていると「適切な会計処理ができていないのでは?」「税務署に指摘されたらどうしよう」と不安になるかもしれませんが、適切な処理を行っている限り、心配する必要はありません。
重要なのは、これらの勘定を適切に処理し、その残高が発生した理由を明確に記録しておくことです。
正確な記録と適切な説明ができれば、税務上の問題は発生しないのでご安心ください。
フリーランスの案件探しはエンジニアスタイルがおすすめ!
ここまで説明してきたように、個人事業主は仕訳の方法によっては一般的な会社員よりも節税しやすい働き方です。
最近では、資産運用ブームが巻き起こっていることもあり、資産の運用幅の広い個人事業主やフリーランスというのは非常に人気になりつつあります。
しかし、フリーランスになるにしても「どうやって仕事を探したらいいのかわからない…。」という方も多いでしょう。
そんな方はぜひ一度「エンジニアスタイル」をご利用ください!
エンジニアスタイルは、数ある案件検索サイトの中でも業界最大級の30万件以上の求人掲載数を誇ります。
また、リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。
契約前のサポートはもちろん契約後もアフターサポートが充実しているので初心者でも安心なのも嬉しいポイント。
登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルのご利用を検討してみてください!
まとめ
本記事では、個人事業主が事業用口座から生活費を引き出した際の仕訳方法について詳しく解説しました。
事業主貸や事業主借の勘定科目は、個人事業主の事業と個人の資金の流れを明確にするために不可欠な知識です。
これらの勘定科目を適切に処理することで、正確な会計処理が可能となり、税務上のトラブルを防ぐことができます。
本記事を通じて、個人事業主の皆さんが正確な経費計上と税務申告を行い、事業運営を円滑に進めるための知識を深める一助となれば幸いです。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。