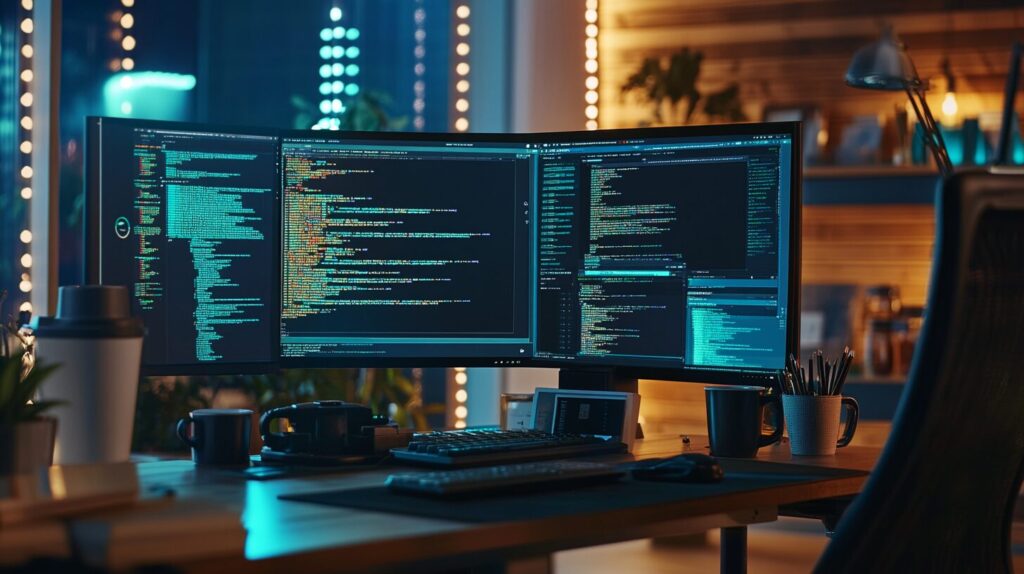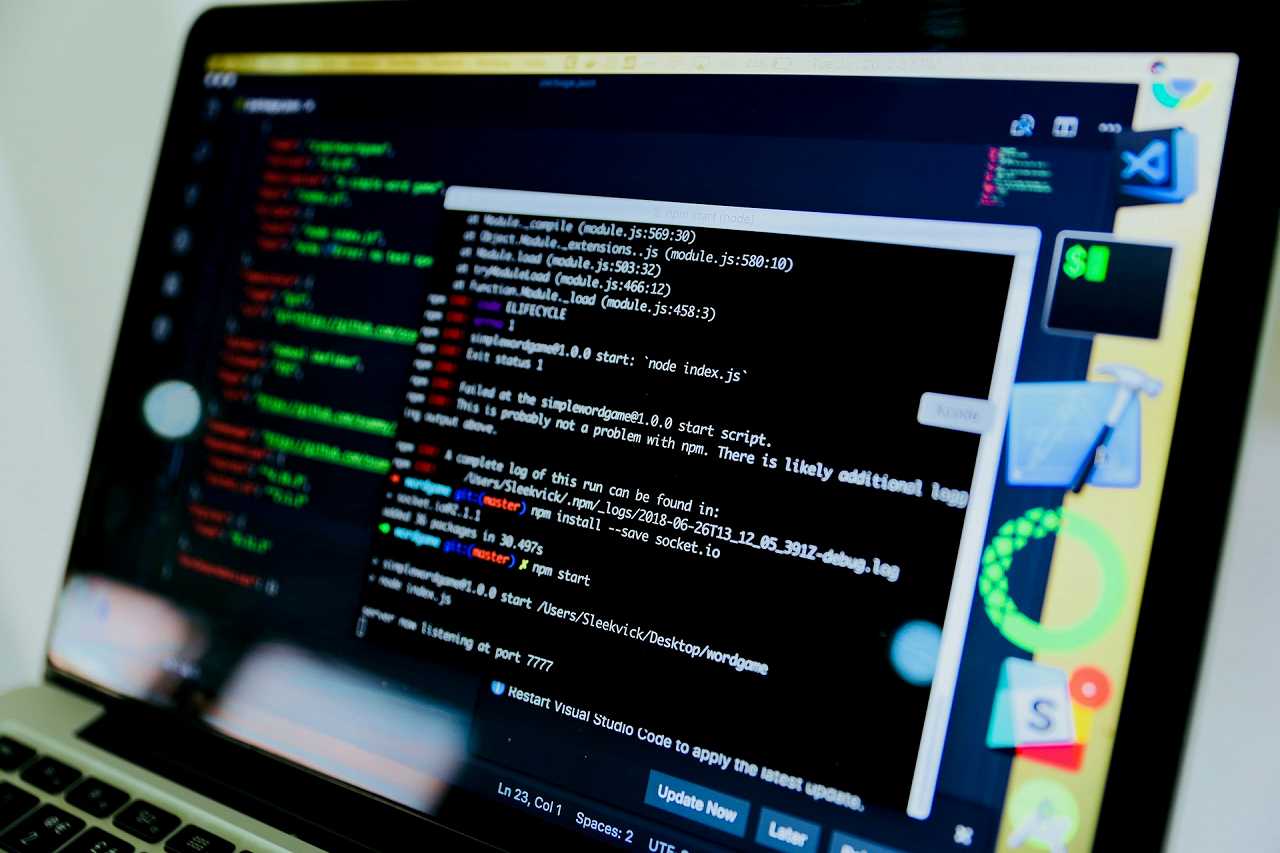業務委託なのに社員扱いは違法?企業が業務委託を選ぶメリットと偽装請負がよくある3つのケース

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
フリーランスのエンジニアとして働く上で、業務委託契約に関する知識は非常に重要です。業務委託契約は、企業とフリーランスが特定のプロジェクトやタスクに基づいて契約を結び、フリーランスが独立して業務を遂行する形式です。しかし、時には企業が業務委託契約を悪用し、実際には雇用契約として扱われるケースも少なくありません。これを「偽装請負」と呼びます。
偽装請負は、企業がコスト削減や労務管理の負担を減らすために、労働者を業務委託契約の形式で雇用し、実際には従業員と同様に指揮命令を行う状況です。このような状況は、フリーランスエンジニアにとって不利な立場に立たされることが多く、法的なリスクも伴います。
本記事では、偽装請負の概要や企業が業務委託を選ぶメリット、そしてよくある偽装請負のケースについて詳しく解説します。また、偽装請負が法律に違反する理由やその影響についても触れ、フリーランスエンジニアが注意すべきポイントを明らかにします。さらに、フリーランスエンジニアが安心して仕事を探すためのおすすめの方法についても紹介します。
偽装請負とは?
偽装請負とは、フリーランスエンジニアが契約上では業務委託として契約されているにもかかわらず、実際には企業の従業員と同様の働き方を強いられる状況を指します。これは労働法規に反する行為であり、法的にも大きな問題となります。フリーランスエンジニアにとっては、自分の働き方が正当な業務委託契約として認められるかどうかを理解し、確認することが非常に重要です。
業務委託契約なのに実態は雇用
業務委託契約とは、企業とフリーランスの間で特定の業務を遂行するために結ばれる契約です。この契約形態では、フリーランスが独立して業務を遂行することが期待されています。しかし、実態として雇用契約と変わらない場合があります。
例えば、フリーランスが企業の指示に従い、決まった時間にオフィスに出勤し、企業の設備や資材を使用して業務を行う場合、これは雇用契約と見なされる可能性があります。このような状況では、フリーランスエンジニアは企業の従業員と同様の管理下で働くことになり、実質的には雇用関係にあると判断されることがあります。
フリーランスエンジニアが独立して業務を行うことが期待される業務委託契約ですが、実際には企業の従業員と同様に働かされることがあります。企業がフリーランスに対して勤務時間や業務の進め方を細かく指示し、企業の管理下で業務を遂行させる場合、それは偽装請負に該当します。このような状況では、フリーランスエンジニアが自らの裁量で業務を進めることが難しくなり、実質的には雇用契約と変わらない状況に置かれます。
偽装請負の判断基準は指揮命令関係の有無
偽装請負を見分けるための重要な基準の一つが「指揮命令関係」の有無です。フリーランスが企業の指示命令に従って業務を行う場合、それは業務委託契約ではなく雇用契約として扱われるべきです。この指揮命令関係が存在するかどうかが、偽装請負を判断する際の重要なポイントとなります。
指揮命令関係とは、企業がフリーランスに対して業務の内容や進め方、勤務時間などを細かく指示し、管理することを指します。業務委託契約の場合、フリーランスは自己の裁量で業務を進めるべきですが、企業が具体的な指示を出し、その指示に従わせる場合、それは雇用関係と見なされる可能性があります。
このような場合、企業は労働基準法や社会保険法などの規制を回避するために、表面的には業務委託契約を結んでいるものの、実態としては雇用契約と変わらない状況を作り出していることになります。フリーランスエンジニアとしては、契約の内容と実態が一致しているかどうかを常に確認することが重要です。具体的には、企業から細かく業務の進め方や手順について指示されているか、決まった時間に出勤し、特定の時間内に業務を行うことが求められているか、企業の設備や資材を使って業務を遂行しているか、といった点に注意する必要があります。
これらの要素が揃っている場合、フリーランスエンジニアは実質的に企業の従業員と同様に働いていると判断される可能性があります。このため、契約を結ぶ際には、契約内容が業務委託契約として適正かどうかを慎重に確認し、不明点がある場合は専門家の助言を求めることが重要です。偽装請負のリスクを避けるために、自身の労働条件と契約内容をよく理解し、必要な措置を講じることが求められます。
会社が雇用より業務委託を選ぶメリットは?
企業が業務委託契約を選ぶ理由はいくつかあります。以下に、主なメリットを解説します。企業が雇用契約ではなく業務委託契約を選ぶ背景には、コスト削減や柔軟な業務運営を実現するための様々な要素があります。これらのメリットを理解することで、フリーランスエンジニアとしての立場からも、企業の意図や契約の背景をしっかりと把握することができます。
残業代を支払う義務がない
企業が業務委託契約を選ぶ大きな理由の一つは、残業代の支払い義務がないことです。業務委託契約には労働基準法が適用されないため、企業はフリーランスに対して残業代を支払う必要がありません。
労働基準法では、労働者が一定の労働時間を超えた場合に残業代を支払う義務があります。具体的には、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働に対して、企業は通常の賃金の割増率を適用して残業代を支払う必要があります。しかし、業務委託契約ではこの規定が適用されません。このため、企業はフリーランスに対して長時間の労働を求めても、追加のコストを負担せずに済むのです。これにより、企業は労働コストの管理が容易になり、経費削減が図れます。
フリーランスエンジニアにとっても、自分の裁量で労働時間を決められるという利点がありますが、同時に契約内容をしっかりと確認し、適切な報酬が支払われるように注意する必要があります。例えば、長時間労働が常態化しているにもかかわらず、適切な報酬が得られていない場合、フリーランスとしての収入が安定せず、生活に支障をきたすことがあります。そのため、契約書には労働時間や報酬に関する具体的な取り決めを明記し、曖昧な表現を避けることが重要です。また、業務が予想以上に長時間になる場合には、追加の報酬を請求する権利があることを契約に明示しておくことも大切です。
業務委託は労働基準法が適用されない
労働基準法は労働者の権利を保護するための基本的な法律ですが、業務委託契約には適用されません。このため、企業は労働時間や休憩時間の管理、残業代の支払いなどの義務を負わずに済みます。
労働基準法が適用されないことで、企業はフレキシブルにフリーランスとの契約を結び、必要な業務を効率的に進めることができます。例えば、企業はプロジェクトの進捗や納期に応じてフリーランスを活用することができ、業務の需要に応じて契約期間や条件を調整することが可能です。また、労働基準法による制約がないため、企業はフリーランスに対して柔軟な働き方を提供できる一方で、フリーランス自身も労働時間や作業場所を自由に選択することができます。
しかし、この柔軟性がフリーランスにとって必ずしも有利とは限りません。フリーランスエンジニアは、自身の労働条件をしっかりと管理し、契約内容に沿った業務を遂行する責任があります。例えば、プロジェクトの進行中に発生する追加作業や急なスケジュール変更に対応するためには、柔軟な労働時間管理が必要です。フリーランスは、自分の時間を効率的に使い、無理なく業務を遂行できるように計画を立てることが求められます。
また、企業との契約内容が曖昧な場合や、不利な条件で契約を結んでしまうと、フリーランスエンジニアが過度に労働を強いられる可能性があります。したがって、契約を結ぶ前に、労働条件や報酬について十分に交渉し、明確な取り決めを行うことが重要です。さらに、フリーランスエンジニアは、必要に応じて法律の専門家や労働組合などの支援を受け、自身の権利を守るための対策を講じることが求められます。
社会保険料を支払わなくて良い
雇用契約の場合、企業は従業員の社会保険料を負担しなければなりませんが、業務委託契約ではその義務がありません。これにより、企業はコストを削減することができます。
社会保険料の負担は企業にとって大きな経費となります。社会保険には健康保険、厚生年金保険、雇用保険などが含まれ、これらの保険料は企業と従業員が折半して支払うのが一般的です。従業員が増えるほど企業の負担も増加するため、社会保険料は企業の人件費に大きく影響します。しかし、業務委託契約では企業がこれらの保険料を負担する必要がなくなります。フリーランスは自分自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を全額自己負担する必要があります。
これにより、企業はフリーランスを雇用する際のコストを大幅に削減できるのです。企業は人件費の削減を図りつつ、フリーランスの専門知識やスキルを活用することができます。一方、フリーランスエンジニアにとっては、社会保険や健康保険の加入については自己責任で行う必要があるため、契約を結ぶ際にはその点をしっかりと考慮することが重要です。フリーランスとして働くことを選ぶ場合、月々の保険料負担を考慮し、収入の一部を確保しておく必要があります。また、社会保険に加入しないことで得られる保障が減少するため、必要に応じて民間の保険に加入することも検討すべきです。
労災保険への加入義務がない
業務委託契約の場合、企業は労災保険への加入義務がありません。これもまた、企業が業務委託契約を選ぶ理由の一つです。
労災保険は、従業員が業務中に事故や病気にかかった場合に保障する制度です。企業は従業員の安全を守るために労災保険に加入し、労働者が業務中に怪我をしたり病気になったりした場合に、治療費や休業補償などの支援を提供します。しかし、業務委託契約では、フリーランスエンジニアが自らの責任で保険に加入する必要があります。これにより、企業は労災保険の負担を避けることができます。
企業にとっては、労災保険の負担が軽減されることは大きなメリットです。労災保険料は企業が全額負担するため、従業員数が多いほど保険料の総額も増加します。業務委託契約を結ぶことで、このコストを削減し、財務面での負担を軽減することができます。
一方、フリーランスエンジニアとしては、自身の安全を守るために、適切な保険に加入しておくことが望まれます。業務中の事故や病気に備えるために、民間の労災保険や傷害保険に加入することを検討する必要があります。また、フリーランスとして働く場合、自分自身の健康管理や安全対策にも十分に注意を払い、リスクを最小限に抑える努力をすることが求められます。
契約を打ち切りやすい
企業にとって業務委託契約のもう一つのメリットは、契約を打ち切りやすいことです。雇用契約に比べて、業務委託契約は企業が柔軟に契約を終了できる点が大きな特徴です。企業は業務の必要性に応じて契約期間を設定し、必要がなくなれば簡単に契約を終了することができます。この柔軟性は、企業にとって非常に大きな利点となります。
「解雇権濫用法理」が適用されない
雇用契約では「解雇権濫用法理」が適用され、企業が正当な理由なしに従業員を解雇することはできません。この法理は、労働者の保護を目的としており、企業が労働者を不当な理由で解雇することを防ぐためのものです。具体的には、解雇の理由が不当であれば、労働者は解雇無効を主張することができ、場合によっては職場に復帰することも可能です。
しかし、業務委託契約ではこの法理が適用されないため、企業は比較的簡単に契約を終了することができます。業務委託契約では、フリーランスと企業の関係は対等な契約関係と見なされるため、この法理は適用されません。フリーランスエンジニアは企業の指示を受ける従業員とは異なり、自分の裁量で業務を進める独立した事業者とみなされます。そのため、契約終了に関しても従業員ほどの保護は受けられないのが現状です。このため、企業は必要に応じて契約を終了しやすくなります。
フリーランスエンジニアにとっては、契約終了のリスクを理解しつつ、安定した仕事を確保するための戦略を持つことが重要です。例えば、複数のクライアントと契約を結び、収入源を分散させることで一つの契約終了による影響を最小限に抑えることができます。また、契約終了に備えて、常に新しい案件を探し続けることや、スキルを向上させることで市場価値を高める努力も重要です。
契約期間を短く設定することが多い
業務委託契約は契約期間が短く設定されることが多いため、企業は必要な期間だけフリーランスと契約を結び、業務が終了したらすぐに契約を終了することが可能です。短期契約の業務委託は、企業にとって非常に柔軟性が高いです。プロジェクトや業務のニーズに応じてフリーランスと契約を結び、必要がなくなれば契約を更新しないという形で対応できます。
企業はプロジェクトの進行状況や市場の動向に応じて、適切なタイミングで契約を終了し、新たなフリーランスと契約を結ぶことができます。これにより、企業は無駄なコストを削減し、効率的に業務を進めることができます。例えば、繁忙期には多くのフリーランスを契約し、閑散期には契約を終了することで、労働コストを最適化することが可能です。
フリーランスエンジニアとしても、短期契約のメリットを活かして多様なプロジェクトに参加し、経験を積むことでスキルを向上させるチャンスとなります。短期契約により、様々な業界や企業のプロジェクトに関与することができ、自分のスキルセットを広げることができます。また、異なるプロジェクトで得た経験は、自身のポートフォリオを充実させ、次の案件獲得に役立ちます。
しかし、短期契約のデメリットとしては、収入の不安定さや次の案件を見つけるための時間と労力が挙げられます。フリーランスエンジニアは常に新しい案件を探し続け、契約期間中に次の仕事を確保するための努力を怠らないことが求められます。安定した収入を得るためには、継続的な学習によるスキルアップと人脈構築が不可欠です。
以上のように、企業が業務委託契約を選ぶ理由には多くのメリットがありますが、その一方でフリーランスエンジニアとしても契約内容や条件を十分に理解し、自身の権利と責任をしっかりと把握することが求められます。適切な契約を結び、企業との良好な関係を築くことが、成功への道筋となります。
偽装請負がよくある3つのケース
偽装請負は、フリーランスのエンジニアが知らず知らずのうちに巻き込まれる可能性がある問題です。業務委託契約として扱われているにもかかわらず、実態は企業の従業員と同様の働き方を強いられるケースが多く見受けられます。以下に、よく見られる偽装請負のケースを紹介します。これらのケースに該当する場合、フリーランスエンジニアとしては警戒心を持ち、自分の権利を守るための行動を取ることが求められます。
フリーランスの業務委託契約で偽装するケース
フリーランスエンジニアが業務委託契約を結ぶ際、実際には企業の従業員と同様の働き方を強いられるケースがあります。例えば、決まった時間にオフィスに出勤し、企業の指示に従って業務を遂行する場合、これは偽装請負に該当する可能性があります。
このようなケースでは、フリーランスエンジニアは企業の指示に従い、企業の設備や資材を使用して業務を行うことが求められます。実態としては企業の従業員と同じ扱いを受けながら、契約上は業務委託契約となっているため、労働基準法や社会保険の適用を逃れるための偽装行為と見なされます。企業はこの方法を用いることで、労働者としての権利保護を受けさせず、コスト削減や管理の簡略化を図ろうとすることが多いです。
フリーランスエンジニアとしては、自分の労働環境が適切かどうかを常に確認し、不当な扱いを受けている場合は早急に対応することが重要です。具体的には、契約内容と実態が一致しているか、企業からの指示が具体的で従業員と同様の管理を受けていないかなどを確認する必要があります。
労働者派遣を業務委託などに偽装するケース
企業が労働者派遣契約を業務委託契約に偽装するケースもあります。派遣労働者が企業の指示の下で働く場合、実態は派遣契約であり、適切な手続きを経る必要があります。しかし、業務委託契約として偽装することで、企業は派遣法の規制を逃れようとします。
派遣労働者が企業の指示に従って働く場合、労働者派遣法に基づいて許可を得る必要があります。しかし、業務委託契約に偽装することで、企業は派遣労働者としての法的義務を回避しようとするのです。これにより、派遣法による保護が受けられない労働者が発生し、不当な扱いを受けるリスクが高まります。
このようなケースでは、フリーランスエンジニアは企業の指示の下で働くことを求められ、派遣労働者としての権利が侵害される可能性があります。例えば、派遣法による労働時間の制限や安全衛生の規制が適用されないため、労働条件が悪化するリスクがあります。フリーランスエンジニアとしては、契約内容を詳細に確認し、派遣契約と業務委託契約の違いを理解しておくことが重要です。
労働者供給を業務委託などに偽装するケース
労働者供給契約を業務委託契約に偽装するケースもあります。これは、企業が労働者を他の企業に供給し、労働者がその企業の指示の下で働く場合です。この場合も、実態は労働者供給であり、適切な契約と手続きを経る必要があります。
労働者供給契約では、労働者が供給先企業の指示の下で働くため、供給元企業と供給先企業の間で適切な契約が必要です。しかし、業務委託契約に偽装することで、企業は供給契約の法的義務を回避しようとします。これにより、労働者の権利が侵害される可能性があります。
このケースでは、フリーランスエンジニアが供給先企業の指示に従って働くことが求められますが、契約上は業務委託契約として扱われるため、労働者としての権利保護が不十分となる可能性があります。企業が労働者供給契約の法的義務を回避するためにこの方法を選ぶことで、労働者は適切な労働条件や法的保護を受けられなくなるリスクが高まります。
フリーランスエンジニアとしては、自身が関与する契約が労働者供給契約ではなく、正当な業務委託契約であるかを確認することが重要です。契約内容に不明点や不安がある場合は、専門家に相談し、適切な対応を取ることが求められます。
以上のように、偽装請負には様々な形態があり、フリーランスエンジニアが注意を怠ると不当な扱いを受けるリスクがあります。自分の権利を守るために、契約内容を詳細に確認し、実態と一致しているかを常にチェックすることが大切です。
偽装請負は法律違反になる
偽装請負は、フリーランスのエンジニアが意図せず巻き込まれる可能性のある問題ですが、これは法律に明確に違反する行為です。偽装請負が発覚した場合、企業は多くの法的リスクを抱えることになります。ここでは、主な法律違反とその影響について詳しく解説します。
労働基準法違反
労働基準法は労働者の権利を保護するための基本的な法律であり、企業はこれを遵守する義務があります。しかし、偽装請負が行われた場合、企業はこの法律に違反することとなります。
過去に遡って残業代等を請求される可能性
偽装請負が発覚した場合、企業は過去に遡ってフリーランスに対して未払いの残業代やその他の手当を支払う義務が生じる可能性があります。これは、偽装請負により実態が雇用契約と見なされるため、労働基準法に基づく賃金の支払いが求められるからです。このような場合、企業は過去の労働時間に基づいて計算された残業代を一括で支払う必要があり、これにより大きな経済的負担を強いられることがあります。
また、フリーランスの立場から見ても、過去に受け取るべきだった賃金が未払いとなっているため、企業に対して請求を行う権利があります。これにより、フリーランスは適正な報酬を受け取ることができますが、企業側にとっては大きな財務リスクとなります。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性
さらに、労働基準法に違反した場合、企業は法的制裁を受けることになります。具体的には、労働基準法違反が確認された場合、企業は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。これにより、企業は刑事責任を問われることとなり、社会的な信用を失うリスクもあります。
このような法的制裁は、企業の経営にとって大きな打撃となります。罰金や懲役刑が科されることで、企業の財務状況が悪化し、さらには従業員や取引先からの信頼を失う可能性があります。このため、企業は偽装請負を行わないよう、適切な労働契約を結ぶことが求められます。
職業安定法違反
偽装請負は職業安定法にも違反する可能性があります。職業安定法は、労働市場の安定と労働者の保護を目的としており、企業が労働者を不当な条件で雇用することを防ぐための法律です。
厚生労働大臣による指導・助言・改善命令等の対象
職業安定法に違反した場合、企業は厚生労働大臣による指導・助言・改善命令の対象となります。これにより、企業は業務運営の見直しを迫られることがあります。具体的には、企業は労働環境の改善や契約内容の見直しを求められ、これに従わない場合はさらなる法的制裁を受ける可能性があります。
厚生労働大臣による指導や助言は、企業に対して労働条件の改善を促すための措置ですが、改善命令が発せられると企業の業務運営に直接的な影響を与えます。このため、企業は指導や助言を真摯に受け止め、速やかに改善策を講じる必要があります。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性
さらに、職業安定法違反の場合、企業は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。これは、職業安定法が労働者の保護を強化するために設けられた厳しい制裁規定です。企業がこのような制裁を受けることになれば、経営陣や株主にとっても大きな問題となり、企業の存続に影響を与える可能性があります。
また、このような法的制裁を受けることで、企業は社会的な信用を失い、従業員や取引先からの信頼を失うリスクも高まります。職業安定法違反が明るみに出ることで、企業の評判が大きく損なわれる可能性があります。
労働者派遣法違反
偽装請負が労働者派遣法にも違反する場合があります。労働者派遣法は、派遣労働者の権利保護を目的としており、企業が労働者を適切な条件で派遣することを義務付けています。
無許可の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象
労働者派遣法に違反し、無許可で派遣を行った場合、企業は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。労働者派遣法は、派遣業務を行う企業に対して厳格な許可制を設けており、無許可での派遣行為は法律違反と見なされます。
このような法的制裁は、企業にとって大きなリスクとなります。無許可での派遣行為が発覚した場合、企業は罰金や懲役刑の対象となり、さらに労働者派遣業務の継続が困難になる可能性があります。これにより、企業の経営に深刻な影響を与えることがあります。
また、労働者派遣法違反が明るみに出ることで、企業の社会的な信用が損なわれ、取引先や顧客からの信頼を失うリスクも高まります。企業はこのようなリスクを回避するために、適切な許可を取得し、法令を遵守することが求められます。
以上のように、偽装請負は労働基準法、職業安定法、労働者派遣法など複数の法律に違反する行為であり、企業はこれに伴う法的リスクを十分に理解し、適切な対応を取ることが重要です。フリーランスエンジニアとしても、自身が関与する契約が合法かつ適正であるかを確認し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。
フリーランスの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ
フリーランスエンジニアが仕事を探す際には、「エンジニアスタイル」が非常におすすめです。エンジニアスタイルは、国内最大級のフリーランスエンジニア向け求人・案件サイトであり、多くのフリーランスエージェントが提供する優良な案件を一括で比較・検索できる便利なプラットフォームです。
特に、リモートワークなどのこだわりの条件から案件を検索することが可能であり、応募も1クリックで完了します。これにより、応募後は連絡を待つだけで済む簡便さが大きな魅力です。また、エンジニアスタイルでは会員登録後にAIがユーザーの登録情報を分析し、個々の条件に最適な案件を提案してくれます。これにより、自分にぴったりの仕事を見つけやすくなっています。
さらに、初回のフリーランスエージェントとの面談に対してAmazonギフト券3,000円がプレゼントされるなど、フリーランスとしてのキャリアを支援する多くのメリットがあります。また、フリーランス向けのイベントやオフ会に無料で参加できる機会も提供されており、エンジニア同士の交流を深めることができます。
まとめ
本記事では、偽装請負の概要とその判断基準、企業が業務委託を選ぶメリット、よく見られる偽装請負のケース、そして偽装請負が法律違反になる理由について詳しく解説しました。フリーランスエンジニアとして活動する上で、これらの知識は非常に重要です。偽装請負とは、企業が業務委託契約を悪用し、実際には雇用契約として扱われる状況のことを指します。これにより、企業は労働基準法や社会保険料の支払いを避けることができますが、フリーランスエンジニアにとっては労働者としての権利が侵害されるリスクがあります。企業が業務委託契約を選ぶ理由には、コスト削減や契約終了の柔軟性が挙げられますが、これが不適切に行われると偽装請負となり、法的なリスクを伴います。偽装請負は、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法に違反し、企業には過去に遡って残業代などを請求されるリスクや、罰金、懲役刑の可能性が生じます。フリーランスエンジニアは、契約内容と実態が一致しているかを確認し、法律に基づいた正当な契約を結ぶことが必要です。信頼できる案件サイトを利用し、適切な契約を結ぶことが、偽装請負のリスクを避けるための第一歩です。エンジニアスタイルのような信頼性の高いプラットフォームを活用し、キャリアアップを目指していきましょう。
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。