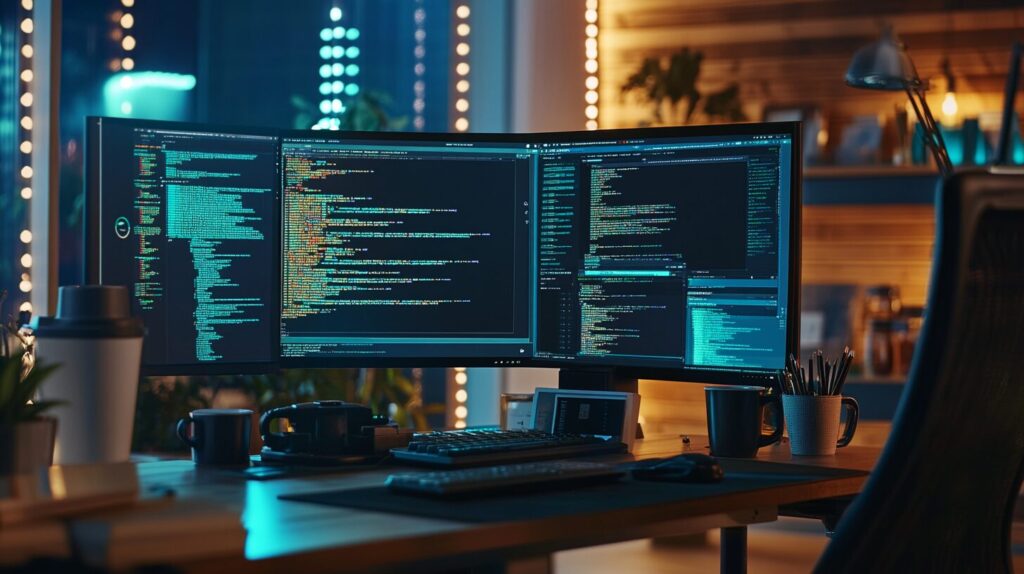業務委託契約の損害賠償とは?損害賠償の範囲と上限額を詳しく解説!

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
業務委託契約を結ぶ際、損害賠償に関する取り決めはとても重要です。
特にフリーランスや企業にとって、どのような場合に損害賠償が発生し、どの範囲まで責任を負うのかを理解することは、予期せぬトラブルを防ぐための鍵となります。
本記事では、業務委託契約における損害賠償について詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 損害賠償の基本的な考え方を理解できる
- 契約書における損害賠償の範囲や上限額について学べる
- 債務不履行や帰責事由に関する知識が得られる
- 損害賠償条項の重要性と作成時のポイントがわかる
本記事を通して、業務委託契約におけるリスク管理を強化し、契約トラブルを回避する知識を身につけましょう。
業務委託契約とは?
| 契約形態 | 業務の目的 | 報酬が発生するタイミング | 具体例 | 備考 |
| 業務委託契約 | 業務全体の遂行または成果物の納品 | 業務の遂行または成果物納品時 | フリーランスの業務一般 | 請負契約や委任契約の総称 |
| 請負契約 | 仕事や成果物の「完成」が目的 | 成果物が完成した時 | 建築工事、システム開発 | 完成品が必要。未完成の場合報酬なし |
| 委任契約 | 法律行為の遂行 | 業務を遂行した時 | 弁護士や税理士の業務 | 法律行為に関する業務。結果より過程重視 |
| 準委任契約 | 法律行為に限らない業務遂行 | 業務を遂行した時 | コンサルティング、経理業務 | 結果を保証せず、業務遂行が目的 |
業務委託契約とは、依頼者が受託者に対して特定の業務を委託し、その業務の遂行に対して報酬を支払う契約形態です。
フリーランスや個人事業主がクライアントからの仕事を引き受ける際、最も一般的に使用される契約形態でもあります。
ただし、業務委託契約にもさまざまな種類が存在するので注意が必要です。
そこでここでは、業務委託契約の種類の一つである「請負契約」と「委任契約」について詳しく見ていき、一般的な雇用契約との違いについても解説していきます。
請負契約との相違
請負契約は、業務委託契約の一種であり、受託者が特定の仕事や成果物を完成させることを約束する契約です。
例えば、建物の建設やウェブサイトの制作など、具体的な成果物の納品が条件となる場合がこれに当たります。
請負契約の特徴は、「成果物の完成」が報酬支払いの条件となることです。
つまり、依頼された仕事が完了し、依頼者がその成果物を検収し承認することで報酬が発生します。
このため、仕事の過程ではなく、最終的な結果や完成物に対して責任を負う点が、請負契約の大きな特徴です。
また、途中で問題が発生しても依頼者に過失がない限り、受託者は成果物を完成させなければ報酬を請求できません。
この点が後述する委任契約との違いです。
委任契約との相違
委任契約は、依頼者が受託者に対して特定の業務や行為の遂行を依頼する契約ですが、請負契約と異なり、成果物の完成を約束するものではありません。
受託者は業務を遂行する義務を負いますが、その結果に対する責任は問われないことが多いです。
例えば、法律業務やコンサルティング業務など、受託者の専門的な知識やスキルを活用して遂行する業務が委任契約に該当します。
また、委任契約の中には「準委任契約」という形態があります。
準委任契約は、特定の行為を依頼する点では委任契約と同じですが、特に技術や専門性を伴わない一般的な作業や事務処理などが対象です。
例えば、事務作業やデータ入力などが準委任契約の代表例といえます。
委任契約や準委任契約の最大の違いは、結果ではなく「行為そのもの」に対して報酬が支払われる点です。
依頼された業務を遂行した時点で、結果にかかわらず報酬が発生するため、受託者は作業の過程に責任を持ちますが、その結果に対する責任は軽減されます。
雇用契約との相違
| 業務委託契約 | 雇用契約 | |
| 目的 | 業務の遂行または成果物の提供 | 労働の提供 |
| 契約の形態 | フリーランスや個人事業主が企業と対等な立場で契約 | 企業が労働者を雇い、指揮命令に基づいて労働を提供 |
| 報酬の発生 | 業務の遂行や成果物の提供に応じて報酬が支払われる | 時間や労働に対して定期的に給与が支払われる |
| 指揮命令 | 業務の遂行方法や時間の管理は自由 | 企業が労働者に指揮命令を出し、業務を管理 |
| 法的保護 | 労働基準法の適用なし | 労働基準法、社会保険、労災保険などの法的保護あり |
| 社会保険 | 自分で加入(国民健康保険、国民年金など) | 企業が社会保険、厚生年金に加入 |
雇用契約は、業務委託契約や請負契約・委任契約とは根本的に異なる契約形態です。
雇用契約では、労働者(受託者)が企業(依頼者)の指揮命令のもと、一定の時間や場所で業務を遂行する義務を負います。
このため、雇用契約においては労働基準法が適用され、労働時間、休憩、残業手当、社会保険などが保障されます。
つまり、雇用契約は労働者の権利を保護する法的枠組みがしっかりと整っているのが特徴です。
一方、業務委託契約では労働基準法が適用されず、受託者は業務遂行の手段や時間の管理について自由度が高い反面、企業からの指示命令を受けない独立した立場にあります。
業務の過程よりも、成果や遂行自体に対して責任を負うのが業務委託契約の特徴です。
このように、業務委託契約は雇用契約とは異なり、受託者が依頼者に従属せず、業務の自由度が高い契約形態であるため、フリーランスや個人事業主にとって利用されやすい形態となっています。
損害賠償とは?
業務委託契約では、何らかのトラブルまたは過失によって契約履行が不可能となった場合、損害賠償を請求される可能性もあります。
ただし、損害賠償を請求されるような深刻な事態に陥るケースは極めて稀です。
しかしながら、業務委託契約において、リスクとして損害賠償が発生し得ることは知っておいた方がよいでしょう。
ここでは、業務委託契約における損害賠償とは何かについて条文をもとに詳しく解説します。
債務不履行(民法415条1項本文)
民法第415条1項本文によると、債務不履行とは、契約上の債務を履行しなかった場合、つまり契約で約束された業務を遂行できなかった場合に損害賠償を請求できる制度です。
条文では、次のように規定されています。
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」
この「債務不履行」に基づく損害賠償請求の要件とは、業務遂行ができなかったこと、もしくはその業務が遂行不能であることです。
例えば、業務委託契約において指定された期限までに成果物を納品できない場合や、業務そのものを完了できない場合がこれに該当します。
このとき、相手方に生じた損害について賠償義務が発生します。
帰責事由(民法415条1項但書)
ただし、すべての債務不履行が直ちに損害賠償責任を伴うわけではありません。
民法第415条1項但書では、「帰責事由」が損害賠償の免責条件として規定されています。
「ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
つまり、債務者に「帰責事由」がなければ、損害賠償を請求されないことになります。
帰責事由とは、債務不履行が債務者の責任によるものであるかどうかを判断する基準であり、具体的には債務者の故意や過失、不可抗力(例えば自然災害など)によるものが免責の理由です。
契約内容や取引慣行に基づいて、債務者に過失があれば賠償責任が生じますが、過失や故意がなければ損害賠償の責任を負わない可能性もあります。
業務委託契約書における損害賠償の詳しい内容とは?
業務委託契約において、損害賠償条項は、双方が契約違反や不履行に対してどのような責任を負うかを定める重要な部分です。
では、業務委託契約における損害賠償の内訳はどうなっているのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
債務不履行時の損害賠償の範囲
損害賠償の範囲は民法第416条に基づいて、通常損害と特別損害に分けられます。
通常損害は、業務の遅延や不履行によって直接生じる損害で、予見可能な範囲内の損害のことです。
例えば、納品が遅れた場合の対応コストや業務が遅延したことによる損害などがこれに該当します。
特別損害は、予見可能であった特別な事情に基づく損害で、これを予見していた場合のみ賠償の対象になります。
次に、具体的なシチュエーションに基づいて損害賠償の範囲を見ていきましょう。
受託者のミスが原因で、委託者に損害が生じた場合
受託者の業務遂行においてミスが発生し、その結果、委託者に損害が生じた場合、受託者は損害賠償責任を負うことになります。
この場合、損害賠償の範囲は委託者が被った財産的損害(例:不良品の納品による再制作費用)や、業務の中断による損害などです。
つまり、委託者は受託者のミスによって発生した損害を通常損害として請求することができます。
受託者の納品が納期に遅れた場合
業務委託契約において納品の遅延は重大な問題です。
納期に遅れることによって委託者が被った損害(例:プロジェクト全体の遅延による取引先へのペナルティなど)は、通常損害として賠償の対象となります。
つまり、納期遅れによって委託者のビジネスに深刻な影響が発生した場合、受託者はその損害を賠償する義務を負います。
ただし、不可抗力(天災や予測できない事情)による遅延であれば、損害賠償責任は免除される可能性が高いです。
委託者が受託者の機密情報を流出させた場合
受託者が業務を遂行するために委託者から機密情報を受け取っている場合、その情報が外部に漏洩した場合の損害賠償は大きな問題となります。
情報流出によって委託者が被った損害(例:顧客の信用失墜、ビジネスチャンスの喪失)は、通常の財産的損害に加えて、場合によっては名誉や信用に関する損害も含まれかねません。
こうした場合、損害賠償の範囲は広範囲に及ぶことがあるので、契約書で具体的なペナルティや損害賠償額が事前に規定されることが多いです。
損害賠償条項がない場合、民法の規定が適用される
業務委託契約書に損害賠償条項が記載されていない場合、損害賠償に関する取り決めは民法の規定に基づいて処理されるのが通例です。
具体的には、民法第415条および第416条が損害賠償の根拠として適用され、債務不履行によって発生する損害に対して賠償が請求されることになります。
この場合の損害は、先述したように「通常損害」と「特別損害」に区分され、それぞれの扱いが異なります。
債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害):すべて損害賠償の対象
通常損害とは、債務不履行が発生した際に、一般的に予見される範囲で生じる損害のことです。
契約が履行されなかった場合に通常発生する損害すべてを対象としており、例えば納品の遅延による逸失利益や、発注ミスによる再作成費用などがこれに該当します。
民法第416条1項により、通常損害は損害賠償の対象となり、契約書に明記されていなくても自動的に民法に基づいて適用されます。
<通常損害の対象の例>
- 納品遅延:販売の遅延、次の工程の遅延など
- 業務ミスによる再作業費用:不良品の再制作費用、修正作業費用など
- 成果物の品質不足:契約で定められた品質基準を満たさないことによる損害
- 契約通りに業務が遂行されなかった場合:予定通りに業務が行われず、業務進行に影響を与える損害
特別の事情によって生じた損害(特別損害):当事者がその事情を予見すべきであった場合に限り、損害賠償の対象
特別損害とは、特別な事情に基づいて発生する損害であり、通常の契約履行においては予見されない損害のことです。
例えば、納品が遅れたことで特定の大口契約が失われた場合や、委託業務の失敗が原因で大規模なトラブルが発生した場合などです。
特別損害が損害賠償の対象となるには、当事者がその特別な事情を「予見し得たかどうか」がポイントになります。
つまり、受託者が特別なリスクを予見できた場合には損害賠償の責任を負いますが、予見不可能な場合には免除される可能性があります。
<特別損害の対象の例>
- 納品遅延による取引契約の喪失:取引先との契約破棄、次の受注が減少するなどの特別な損害
- 業務失敗による大規模プロジェクトの中断:プロジェクト全体の中断、関連する取引の停止
- 機密情報漏洩による信用失墜:顧客や取引先の信用喪失、ブランドイメージの低下
- 特定の重要な契約が破棄されるリスクがある場合:重要な契約のキャンセルや取引先との関係悪化
損害賠償の上限
仮に、業務委託契約で相手方に損害を発生させてしまった場合、具体的にどの程度の損害賠償額が請求されるのでしょうか?
損害賠償の請求額については、ケースバイケースとしか言いようがありませんが、基本的に以下の4つの基準に基づいて算出されます。
委託料を上限として
損害賠償額を「委託料の総額を上限」とするのは、最も一般的な手法です。
例えば、契約の全体の委託料が1,000万円であれば、損害が発生してもその賠償額は1,000万円を超えないと定めることになります。
民法第420条では、損害賠償の予定額について以下のように規定されています。
「違約金は、賠償額の予定と推定する。」
これは、あらかじめ契約で賠償額を決定しておくことができるというもので、委託料を損害賠償額の上限として設定することは、この条文に基づいて合理的といえるでしょう。
賠償の原因となった個別契約の金額を上限として
プロジェクトごとに個別契約が結ばれている場合は、「個別契約の金額」を損害賠償額の上限にする方法もあります。
例えば、ある業務で500万円の契約がある場合、その業務に起因する損害は500万円を上限とするという規定です。
民法第416条では、先述したように損害賠償の範囲が定められており、通常損害と特別損害が区別されています。
この条文に基づいて、損害賠償額を個別契約の範囲内で設定することは、契約ごとに生じるリスクを細分化し、特定の業務にのみ影響が及ぶようリスクを限定する方法です。
特に大規模なプロジェクトでフェーズごとに契約が分かれている場合、この方法を使うことで受託者が過度な責任を負わないように調整できます。
直近◯ヵ月(又は年)の取引金額を上限として
損害賠償額を直近の取引金額に基づいて設定する方法もあります。
これは、契約期間が長期にわたる場合や、複数年契約が行われる場合に有効です。
例えば、「直近6か月の取引金額を上限にする」といった条項を設けることで、契約全体ではなく特定期間内の損害に対する賠償を制限できます。
また、長期契約や継続的な取引がある場合に、受託者が過度なリスクを負わないように設定するケースがよく見られます。
違反行為があった月の前月の委託料(消費税込)の20%
損害賠償額をさらに具体的に設定する方法として、違反行為が発生した月の前月の委託料(消費税込)の20%という形で上限を設けることもあります。
これは、委託料が一定額である場合や、特定の月ごとの支払いがある契約に適しており、具体的な数値で賠償額を設定することで、リスクの範囲をさらに限定的に管理できる点がメリットです。
ただし、必ずしも20%に固定する必要はありません。
あくまでも、20%という数値は賠償額が極端に高額になるのを防ぎつつ、一定の責任を負う仕組みとして多く採用されているだけです。
業務委託契約書で損害賠償条項を定める際の注意すべき項目
業務委託契約書における損害賠償条項は、契約違反やトラブルが発生した際のリスクを管理し、双方が負う責任を明確にするために極めて重要です。
ここでは、損害賠償条項を定める際に注意すべき点を民法の規定を基準に解説します。
損害賠償条項に基づく損害賠償の範囲が妥当かどうか民法の規定を基準として判断する
損害賠償条項を設定する際には、その範囲が民法の規定に基づいて適切かどうかを確認することが重要です。
具体的には、民法第415条および第416条が基準となります。
- 「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
- 「1.債務不履行によって生じた損害の賠償は、通常生ずべき損害をその範囲とする。
2.特別の事情によって生じた損害は、債務者がその事情を予見し、または予見することができたときに限り、賠償の範囲に含まれる。」
上記の民法の規定に基づき、損害賠償条項における賠償範囲は「通常損害」を中心に定めることが基本となります。
また、特別損害については、契約書に予見可能性があった場合のみ賠償範囲に含まれることを明記しておくとよいでしょう。
例えば、「特別な損害については、事前に予見できた場合に限り賠償の対象とする」といった条項が有効です。
損害賠償の上限規定に注意する
損害賠償の上限を設定することも、リスクを限定するために重要です。
上限規定を設けることで、過大な賠償請求から受託者を保護し、予期せぬ損害額の拡大を防げます。
上限規定に関する民法の条文は以下の通りです。
「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
2.違約金は、賠償額の予定と推定する。」
そのため、上限規定に盛り込むべき項目としては、以下のような文言が適切です。
- 損害賠償額の上限:「本契約に基づく損害賠償の上限額は、契約全体の委託料を限度とする。」
- 個別契約に基づく上限設定:「本契約の各個別業務に基づく損害賠償額は、当該個別契約の委託料を上限とする。」
- 例外条項(重大な過失の場合):「重大な過失または故意に基づく損害については、上限規定の適用は除外される。」
- 期間による上限設定:「直近6か月の取引金額を基準として損害賠償額を上限とする。」
このように損害賠償の上限を設定し、具体的な文言を契約書に盛り込むことで、トラブル発生時のリスクを低減可能です。
フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ

フリーランス向けのクラウドソーシングサービスを展開しているランサーズ株式会社の調査によると、フリーランスの数は2021年時点で労働人口の約22.8%を占めています。
年々フリーランス人口も右肩上がりで増え続けているので、ビジネスマンの2人に1人はフリーランスという時代も到来するかもしれません。
しかし、「フリーランスになっても自分1人で仕事を見つけられる気がしない…。」と考えてなかなか最初の一歩が踏み出せない方も多いでしょう。
そんな時はぜひエンジニアスタイルをご利用ください!
エンジニアスタイルは、数あるフリーランスサイトの中でも業界最大級の30万件以上の求人掲載数を誇ります。
また、リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。
契約前のサポートはもちろん契約後もアフターサポートが充実しているので、初心者でも安心なのもうれしいポイント。
登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルのご利用を検討してみてください!
まとめ
業務委託契約における損害賠償は、契約を結ぶ際に非常に重要な要素です。
本記事では、業務委託契約がどのように請負契約や委任契約と異なるか、損害賠償の範囲や上限、そして損害賠償条項を定める際の注意点について詳しく解説しました。
損害賠償に関しては、契約書の内容次第でトラブルを防ぎ、リスクを軽減することが可能です。
業務委託契約の締結時には損害賠償条項をしっかり確認し、適切なリスク管理を行いましょう。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

1992年生まれ、北海道出身。トレンドスポットとグルメ情報が大好きなフリーライター。 衣・食・住、暮らしに関する執筆をメインに活動している。 最近のマイブームは代々木上原のカフェ巡り。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。