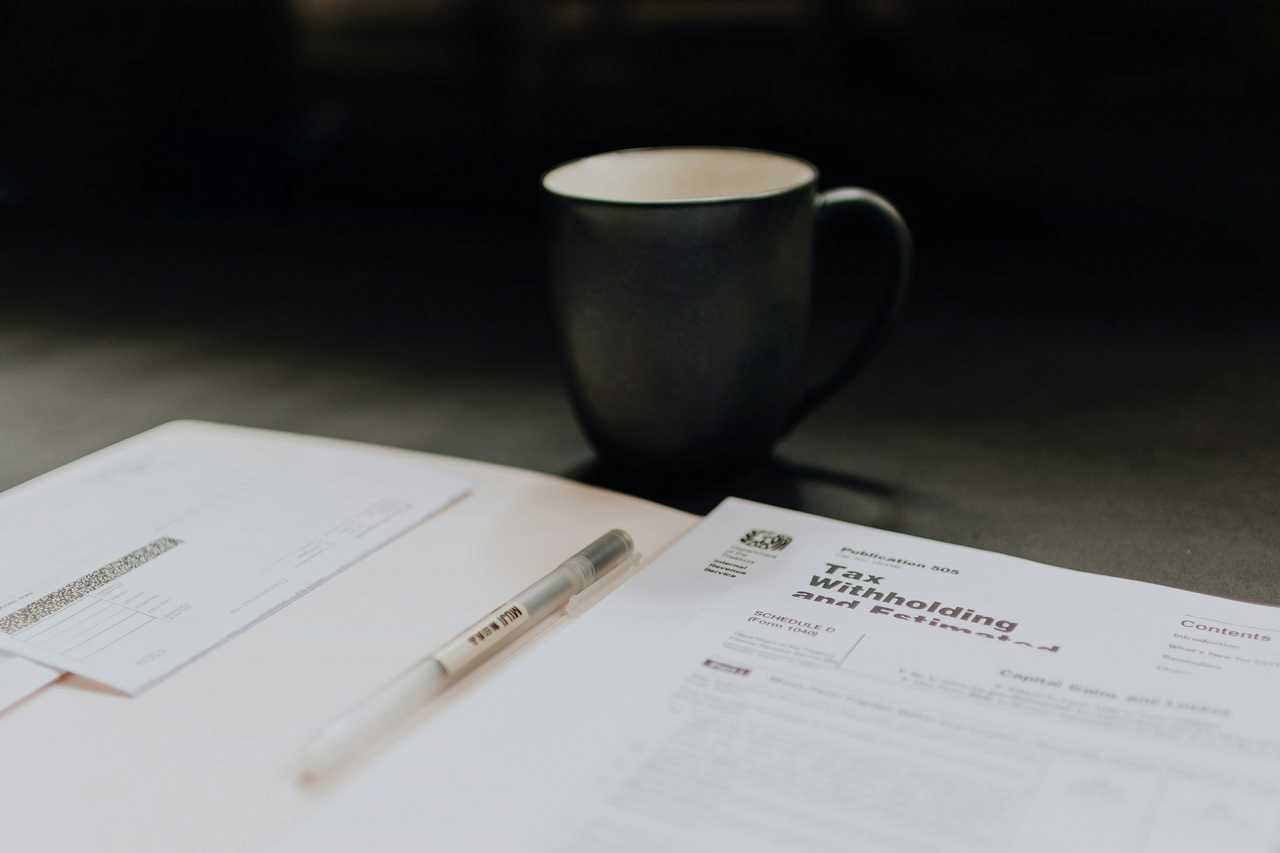フリーランスの語源は中世のヨーロッパ?フリーランスと似た意味の言葉や日本のフリーランス事情を紹介

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
フリーランスという働き方は、近年ますます注目を集めています。
そこで本記事では、フリーランスの語源やその歴史から、現代におけるフリーランスの意味、そして日本や海外でのフリーランスの実態について詳しく解説します。
また、フリーランスとして働くメリットとデメリットについても触れ、実際にフリーランスとして働く際の注意点や役立つ情報をお届けします。
最後までお読みいただければ、フリーランスの全貌が明らかになり、あなた自身のキャリア選択に役立つ知識が得られることでしょう。
フリーランスに興味がある方、これからフリーランスを目指そうとしている方にとって、貴重な情報源となるので、ぜひ最後までお読みください!
<この記事を読むとわかること>
- フリーランスの語源とその歴史
- フリーランスと似た意味を持つ言葉の違い
- 日本と海外におけるフリーランスの現状
- フリーランスとして働く際のメリットとデメリット
- フリーランスとして成功するためのヒントやアドバイス
そもそもフリーランスとは
フレキシブルな働き方ができるフリーランスですが、そもそもフリーランスとは一体何を指すのでしょうか?
「会社に所属しないで働いている人」というなんとなくな意味はわかっていても、具体的に説明を求められると、意外に説明できない人の方が多いと思います。
ここでは、フリーランスの意味について見ていきましょう。
企業などに所属せず仕事に応じて自由に契約する働き方
| 特徴 | メリット | デメリット | |
| フリーランス | 企業に所属せず、プロジェクトごとに契約 | ・柔軟な働き方 ・いろんな仕事に挑戦 ・自分のペースで働ける | ・収入が不安定 ・自己管理の負担 ・社会保険や福利厚生の自己負担 |
| 個人事業主 | 税務署に開業届を提出し、正式に事業を開始した人 | ・事業の全てをコントロール ・経費を自由に計上 | ・収入が不安定 ・経営の全責任 ・社会保険や福利厚生の自己負担 |
| 会社員 | 企業に所属し、雇用契約に基づいて働く | ・収入が安定 ・社会保険や福利厚生が充実 ・労働法による保護 | ・勤務時間や場所の固定 ・自由度が少ない ・人間関係に左右される |
簡単にいえば、フリーランスとは企業などに所属せず仕事に応じて自由に契約する働き方をしている人のことです。
フリーランスは自分のスキルや知識を活かして、様々なクライアント(依頼主)と個別に契約を結び、プロジェクトごとに仕事をこなします。
フリーランスの特徴は以下の3点です。
- 自分のペースで働ける:勤務時間や場所を自分で決められるため、ライフスタイルに合わせた働き方が可能
- 様々な仕事に挑戦できる:一つの会社に縛られず、様々なプロジェクトに参加することで経験を積める
- 収入が変動する:固定給ではなく、受注した仕事の量や内容によって収入が変わるため、成果次第で高収入を得ることが可能
個人事業主も似たような特徴を持っていますが、税務署に開業届を提出した人を個人事業主と呼びます。
フリーランスのハードルは以前より低くなっている
フリーランス人口は急激に増えつつあると冒頭でお伝えしましたが、最も大きな原因はフリーランスになるためのハードルが以前と比較して格段に低くなったからです。
ハードルが低くなった理由は複数ありますが、以下の3点が主な要因でしょう。
1.オンラインプラットフォームの普及
クラウドソーシングサイトやビジネスSNSの普及により、フリーランスが簡単に仕事を見つけることができるようになった。
2.IT技術の進化
インターネットとPCがあれば多くの仕事が可能になり、特にIT分野ではリモートワークが容易になった。
3.サポートツールの充実
フリーランス向けの会計ソフトやタスク管理ツールなど、業務を効率化するためのツールが増え、自己管理がしやすくなった。
このように、今までと比較してフリーランスを取り巻く環境は劇的に改善されつつあります。
また、働き方改革の影響もあり、以前よりもフレキシブルな働き方を求める人が増えたのも、フリーランス人口が爆発的に増加している原因のひとつです。
フリーランスの語源は中世の傭兵?
少し話は変わりますが、フリーランスの語源についてはご存知でしょうか?
結論からいうと、フリーランスの語源は中世ヨーロッパの傭兵からきています。
しかし、フリーランスの語源を紐解いてみると、意外にもフリーランスの働き方に対する理解が深まります。
ここでは、そんなフリーランスの語源について詳しく解説していきます。
フリーランスの語源は中世のヨーロッパ
「フリーランス」という言葉は、中世ヨーロッパにその期限を遡ります。
フリーランス(freelance)は「free」(自由)と「lance」(槍)を組み合わせたもので、元々は独立した戦士や傭兵を指す言葉でした。
中世ヨーロッパでは多くの戦争が行われており、王や貴族たちは自分たちの軍隊だけでなく、追加の兵力として傭兵を雇うことが一般的でした。
これらの傭兵は特定の国や領主に縛られることなく、自分の戦闘技能を提供して報酬を受け取ることで生計を立てていたのです。
こういった人々のことを、スコットランドの歴史小説家ウォルター・スコットが、1819年の歴史小説『アイヴァンホー(Ivanhoe)』にて「フリーランス」と表現したのが起源と言われています。
フリーは政治的に中立という意味
「フリーランス」の「フリー(free)」は“自由”を意味しますが、政治的に中立であることも意味します。
中世の傭兵は、特定の主君や国家に仕えることなく、自らの意思で契約相手を選ぶことができました。
そのため、彼らは「フリー」(自由)な立場を維持することができたのです。
政治的に中立であることで、彼らは様々な勢力から信頼され、戦闘能力を評価されました。
裏切りや謀略の渦巻く混沌とした中世ヨーロッパにおいて、純粋に戦闘能力だけを売り込み、そして対価に見合う金さえ支払えば信頼のおける仕事をこなす彼らの存在は、ある意味では周囲の仲間たちよりもずっと信頼のおける相手だったのかもしれません。
組織に属せず自由な契約で働くという意味に変化
その後、「フリーランス」という言葉は、時代の変遷とともにその意味が大きく変化していきます。
20世紀に入り、経済や技術の発展とともに、働き方の多様化が進みました。
特に第二次世界大戦後の高度経済成長期には、多くの専門職が誕生し、特定の企業に属さずに独立して活動する人々が現れました。
この時期には、ジャーナリスト、デザイナー、エンジニアなどの職業で「フリーランス」として活動する人々が世界的に増えたといわれています。
21世紀には、オンラインプラットフォームの登場により、フリーランサーは世界中のクライアントと直接繋がることが可能となり、場所や時間に縛られない働き方が一般化しました。
この変化により、フリーランスは特定の企業や組織に属さずに、自分のスキルやサービスを自由に提供する働き方として定着したのです。
どうでしょうか?
意外にも、フリーランスの歴史を紐解くと、昔も今も変わらず最も必要とされているのは、「どこ」で働くかではなく、「何が」できるのかだといえるのではないでしょうか。
フリーランスと似た意味を持つ言葉を紹介
最近では、仕事に対する価値観も以前よりもだいぶ様変わりしています。
こういった背景もあって、フリーランスと似た意味を持つ言葉もたくさん登場しました。
全てを詳細に覚える必要はありませんが、それぞれ若干意味合いが変わってくるので、以下に簡単に紹介していきます。
個人事業主
個人事業主とは、法人を設立せずに自らの名義で事業を営む人を指します。
税務署に開業届を提出することで、個人事業主としての活動を正式に開始します。
収益や経費は個人の所得として扱われ、確定申告が必要です。
業種や規模に関係なく、自由に事業を展開できる一方で、全てのリスクや責任を個人で負うことになります。
一般的には、小規模なビジネスやフリーランス活動、店舗経営などが多いです。
自由業
自由業は、特定の企業に属さず、自らのスキルや知識を活かして独立して活動する職業の総称です。
芸術家、作家、翻訳者、カウンセラーなどがこれに該当します。
仕事の内容やスタイルは多岐にわたり、自由度が高いことが特徴です。
報酬は個々の仕事ごとに受け取るため、収入は一定ではない場合が多いです。
自由業もフリーランスや個人事業主と同様に、自己管理能力と専門的なスキルが求められます。
フリーター
フリーターは、正式な職に就かず、アルバイトやパートタイムの仕事を掛け持ちすることで生計を立てる人を指します。
若者や学生が多く、特定の職業に縛られずに働くため、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
ただし、安定した収入を得ることが難しく、社会保障やキャリア形成の面での課題もあります。
将来的には正社員を目指す場合が多いです。
SOHO
SOHOは「Small Office/Home Office」の略で、自宅や小規模なオフィスでビジネスを行う形態を指します。
インターネットの普及により、自宅からでも効率的に事業を展開できるようになり、IT関連やクリエイティブ業界でよく見られます。
柔軟な働き方が可能で、通勤時間の短縮や家族との時間の確保がメリットです。
業務環境や自己管理能力が成功の鍵となります。
ノマドワーカー
ノマドワーカーは、特定のオフィスを持たず、場所に縛られずに働く人を指します。
ノートパソコンやスマートフォンを使ってカフェ、コワーキングスペース、海外などあらゆる場所で仕事を行います。
IT技術の進展により、リモートワークが可能となり、ノマドワーカーとしての働き方はかなり一般的になりました。
自由な働き方が魅力ですが、自己管理能力と柔軟性が求められます。
インディペンデント・コントラクター
インディペンデント・コントラクターは、特定の企業に雇用されず、契約に基づいて業務を行う個人事業者です。
プロジェクト単位で仕事を請け負い、結果に応じた報酬を受け取ります。
業務内容や契約条件はクライアントと取り決めるため、自由度が高い反面、仕事の獲得や契約交渉が必要です。
法的には独立した事業者とみなされるため、税務上の処理や保険などは自己責任で行う必要があります。
フリーランスの人口はどれくらい?
最近では、フリーランス人口が爆発的に増加しているので、TVCMやインターネット広告でも、フリーランス系のCMを見かけることも多くなりました。
では、フリーランス人口は具体的にどれくらいの規模にまで成長しているのでしょうか?
ここでは、いくつかのデータを元に、国内外のフリーランス人口とフリーランス人口が増加している背景をご紹介します。
日本の就業人口におけるフリーランスの割合
フリーランス専門のクラウドソーシングサービスを運営するランサーズ株式会社の『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』によると、2020年時点での日本のフリーランス人口は約1062万人でした。
2021年に入ると、フリーランス人口は約1577万人(前年比48.5%)にもなり、加速度的に増え続けています。
また、2024年時点の日本の就業人口は、総務省が毎年発表している労働力調査によると6730万人です。
2024年時点でのフリーランス人口のデータはまだ発表されていませんが、2021年以降もフリーランス人気が衰える傾向はありません。
したがって、日本の就業人口におけるフリーランスの割合は、最低でも約23.4%以上となります。
海外のフリーランスの割合
2024年時点での海外の主要国のフリーランス人口のデータを調査してみたところ、以下のような結果になりました。
- アメリカ:約46.6%
- イギリス:約14%
- ブラジル:約25%
- 中国:約13%
- 韓国:約8.5%
こうしてみると、日本は現在フリーランス人口がかなり多い国であることがわかります。
ただし、各国でフリーランスの定義は若干変わってきます。
アメリカでは、フリーランスという考え方自体がかなり古くから定着していたこともあり、さまざまな働き方をフリーランスと定義します。
しかし、中国などの最近経済が急激に発展したような国では、まだフリーランスという概念自体が国民全体に定着していない状況です。
したがって、上記のデータはそういった要素で変動する可能性があることにはご留意ください。
フリーランスが今後も増えると予想される背景
日本でフリーランスを目指す人の数が爆発的に増えていることは前項で説明しましたが、果たして今後も継続して増え続けるのでしょうか?
結論からいうと、今後もフリーランスの数は増え続けることになる可能性が非常に高いです。主な理由は以下の3つです。
1. 働き方改革と法改正
政府は「働き方改革」を推進し、多様な働き方を支援しています。
また、2020年の労働者派遣法改正などにより、企業が柔軟な雇用形態を採用することが容易になり、フリーランスの需要が高まっています。
2. 多様なキャリアパスの志向
現代の労働者、特に若い世代は、一つの企業で長期間働くよりも自分のスキルや興味を活かして多様なキャリアパスを追求する傾向があります。
フリーランスは、自分の専門性を最大限に活かしながら柔軟に働くことができるため、このような志向にマッチしています。
3. 企業側のニーズ
企業もまた、経済の変動や市場の変化に柔軟に対応するため、固定費の高い正社員よりも、プロジェクトごとに専門家をフリーランスとして雇用する方が効率的だと考えるようになっています。
特にITやクリエイティブ分野では、専門性の高い人材をフリーランスとして採用する動きが強まっています。
これらの要因が相まって、日本のフリーランス人口は今後も増加していくと予想されます。
フリーランスとして働くメリット・デメリット
フリーランスが増えているのは、非常に多くの魅力的なメリットがあるからです。
しかし、もちろんデメリットも存在します。
ここでは、フリーランスとメリットとデメリットについて解説します。
フリーランスとして働くメリット
フリーランスとして働くメリットは以下の5点です。
- 仕事を自由に選べる
- 自分の希望するスタイルで働ける
- 収入アップが見込める
- 人間関係のストレスが少ない
- 定年がない
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
仕事を自由に選べる
フリーランスの最大のメリットの一つは、仕事を自由に選べることです。
会社員の場合、上司や会社の方針に従って与えられた仕事をこなさなければなりません。
しかし、フリーランスは自分の興味や得意分野に基づいて仕事を選ぶことができます。
これにより、自分のスキルを最大限に活かせるプロジェクトに集中することができ、仕事の質も向上します。
また、仕事の内容やクライアントを選ぶ自由があるため、モチベーションを高く保ちながら働くことができます。
自分の希望するスタイルで働ける
フリーランスの働き方は柔軟性が高く、自分のライフスタイルやスケジュールに合わせて働くことができます。
例えば、早起きが得意な人は朝早くから仕事を始め、夜型の人は夜遅くまで作業することが可能です。
また、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、働く場所も自由に選べます。
これにより、ストレスを減らし、働きやすい環境を自分で作り出すことができるため、仕事の効率も向上します。
収入アップが見込める
フリーランスは、自分のスキルや実績に応じて報酬を設定できるため、収入アップが見込めます。
会社員のように固定給ではなく、プロジェクトごとに報酬を設定するため、成功すればするほど収入が増える可能性があります。
また、複数のクライアントと契約することで、収入源を多様化し、経済的な安定を図ることも可能です。
さらに、自己研鑽を続けることでスキルを高め、高額な報酬を得られるプロジェクトに参画するチャンスも増えます。
人間関係のストレスが少ない
フリーランスは、自分でクライアントや仕事仲間を選ぶことができるため、不要な人間関係のストレスを減らすことができます。
会社員の場合、職場の同僚や上司との関係がストレスの原因となることがありますが、フリーランスはそうした問題を避けることができます。
また、オンラインでのコミュニケーションが主流となるため、直接対面でのやり取りが減り、自分のペースで仕事を進めることも可能です。
これにより、心の健康を保ちながら仕事に集中することができます。
定年がない
フリーランスには定年がありません。
会社員の場合、一定の年齢に達すると退職を余儀なくされますが、フリーランスは自分のペースで働き続けることができます。
健康であれば何歳になっても仕事を続けることができ、好きな仕事を長く続けられるのは大きなメリットです。
また、経験と実績を積み重ねることで、年齢を重ねても高い評価を受け続けることができます。
これにより、経済的な安定を維持しながら、充実したライフスタイルを送ることができます。
フリーランスとして働くデメリット
フリーランスとして働くデメリットは、主に以下の5点です。
- 収入が安定しない場合がある
- 人との関わりが少なく孤独を感じる
- 会社員に比べて社会的な信用が低い
- スケジュール管理や自己管理が難しい
- 確定申告などの事務作業が必要
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
収入が安定しない場合がある
フリーランスの最大のデメリットの一つは、収入が不安定であることです。
会社員とは異なり、毎月固定の給料が保証されていないため、仕事が途切れた場合やクライアントからの支払いが遅れると収入が減少するリスクがあります。
このため、フリーランスは常に新しい仕事を探し続け、複数の収入源を確保する必要があります。
また、仕事の量や報酬が季節や経済状況に左右されることもあるため、経済的な不安定さを感じることが多いです。
人との関わりが少なく孤独を感じる
フリーランスは一人で作業することが多く、職場での同僚や上司との日常的なコミュニケーションがないため、孤独を感じることが多いです。
人との交流が少ないことで、情報交換やアイデアの共有が難しくなり、モチベーションの低下や精神的なストレスを感じる危険性もあります。
そのため、フリーランスは意識的にネットワーキングイベントやコワーキングスペースを利用し、他のフリーランサーや専門家と交流する機会を作ることが重要です。
会社員に比べて社会的な信用が低い
フリーランスは会社員に比べて社会的な信用が低いと見なされる傾向にあります。
例えば、住宅ローンやクレジットカードの審査では、安定した収入源がないために不利になる場合があります。
また、フリーランスの仕事は理解されにくく、家族や友人からのサポートが得られにくいことも多いです。
このため、フリーランスは信頼性を高めるために、実績を積み重ねたり、クライアントからの推薦状を集めたりすることが重要です。
スケジュール管理や自己管理が難しい
フリーランスは自分自身でスケジュールを管理する必要があるため、自己管理が難しいと感じることがあります。
仕事の量や締め切りを自分で調整する必要があるため、過労や燃え尽き症候群に陥るリスクもゼロではありません。
また、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちで、オンとオフの切り替えが難しくなることもあります。
このため、フリーランスは時間管理のスキルを磨き、バランスの取れた生活を送るための工夫が必要です。
確定申告などの事務作業が必要
フリーランスは確定申告をはじめとする各種の事務作業を自分で行わないといけません。
会社員の場合、給与所得に関する税務手続きは会社が代行してくれますが、フリーランスは自分で収入や経費を管理し、適切に申告する必要があります。
これには非常に多くの時間と労力がかかり、専門知識も求められるため、初めてのフリーランサーにとっては大きな負担となります。
このため、税理士などの専門家に相談したり、会計ソフトを利用したりするのがおすすめです。
フリーランスの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ!
現在では、フリーランス専門の仕事探しをサポートするサービスも数多く存在します。
しかし、「多すぎてどれが自分にあっているのかよくわからない…。」という方も多いでしょう。
そんな時はぜひエンジニアスタイルをご利用ください!
エンジニアスタイルは、数あるフリーランスサイトの中でも業界最大級の30万件以上の求人掲載数を誇ります。
また、リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。
契約前のサポートはもちろん契約後もアフターサポートが充実しているので初心者でも安心なのも嬉しいポイント。
登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルのご利用を検討してみてください!
まとめ
本記事では、フリーランスの語源から始まり、現代におけるフリーランスの意味や日本および海外でのフリーランスの実態、そしてフリーランスとして働くメリットとデメリットについて詳しく解説しました。
フリーランスという働き方は、自由と自己管理のバランスを取ることが求められるため、慎重な計画と継続的な努力が必要です。
今後もテクノロジーの進化や働き方の多様化が進む中で、フリーランスの働き方はさらなる広がりを見せるでしょう。
この記事が、フリーランスとして働くことを検討している方や、既にフリーランスとして活動している方にとって、有益な情報となり、キャリア選択や働き方の改善に役立つことを願っています。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。