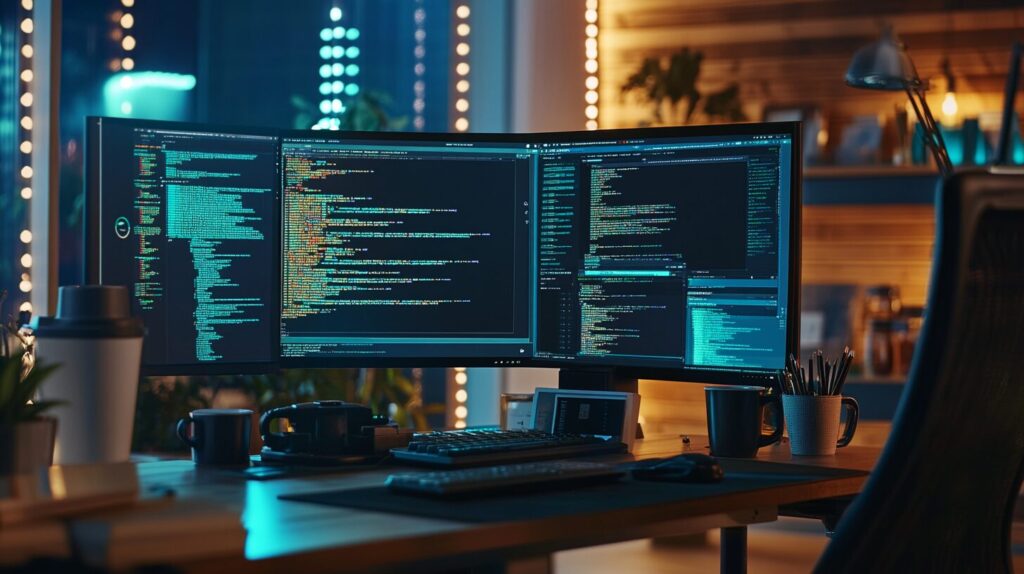フリーランスエンジニアは税理士に依頼すべき?メリット・デメリットとかかる費用の目安
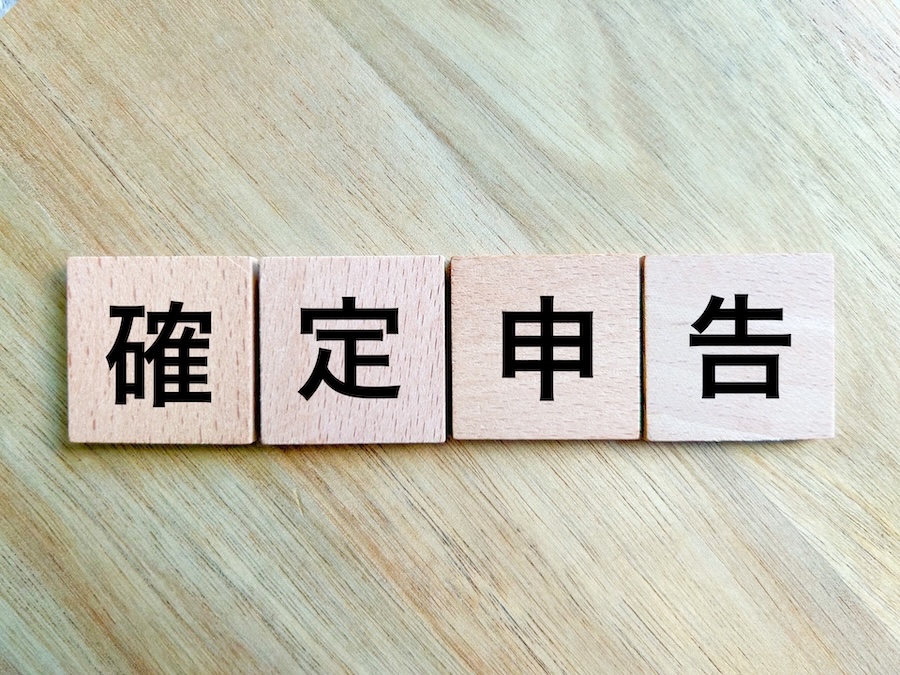
はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
フリーランスエンジニアとして働いていると、確定申告や経費計上、税務処理など、税務に関する手続きが複雑で負担に感じることはありませんか?
税理士に依頼すればこういった税務処理の負担を軽減できますが、依頼する際にはいくつか注意点もあります。
本記事では、税理士に依頼するメリットやデメリット、かかる費用の相場や節約方法、税理士選びのポイントなどをわかりやすく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 税理士に依頼するべきかどうかの判断ができる
- 税理士選びのポイントがわかる
- 税理士費用を節約する方法を知れる
- 税務処理を自分で行う方法も学べる
本記事を参考に、税理士へ依頼するかどうかを見極めましょう!
フリーランスエンジニアは税理士に依頼するべき?
フリーランスや個人事業主にとって避けては通れないのが「確定申告」。
特にフリーランスエンジニアは複数案件を掛け持ちしている人も多いので、なるべく税務処理に費やす時間を少なくしたいというのが本音です。
そのため、多くのフリーランスエンジニアが「税理士」に税務処理を依頼するのを検討しています。
しかし、税理士に依頼する際にはどうしてもコストがかかってしまいます。
では果たして、フリーランスエンジニアは税理士に依頼するべきなのでしょうか?
結論からいうと、以下に当てはまる人は税理士に依頼するべきです。
- 年間の売上が増加し、税務処理が複雑化している人
- 節税対策をしっかりと行いたい人
- 本業に専念したい人
- 税務調査に備えたい人
ここからは、税理士に依頼するメリット・デメリットを見ていきながら、理由を深掘りしていきましょう。
税理士に依頼するメリット
フリーランスエンジニアが税理士に依頼するメリットは以下の5点です。
- 税務処理の時間が大幅に節約できる
- 適切な節税のアドバイスを受けられる
- 確定申告や納税がスムーズになる
- 追徴課税のリスクを回避できる
- 税制改正にも対応してもらえる
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
税務処理の時間が大幅に節約できる
税務処理は非常に時間がかかる作業です。
収支の記録や経費の計算、確定申告書の作成など、税務に慣れていない人にとっては、1日どころか数日を費やすこともあります。
しかし、税理士に依頼すれば税務処理をプロに任せることができ、本業に集中する時間を確保できます。
特にエンジニアはスキルアップや案件対応など、本業に注力することが収入アップにつながるため、税務処理に費やす時間を最小限に抑えられるのは大きなメリットです。
適切な節税のアドバイスを受けられる
フリーランスエンジニアとして活動する中で、節税は収益を最大化する際の重要なポイントです。
しかし、自分で調べるだけでは税制に関する情報が断片的で、どの控除が自分に該当するのか判断が難しい場合があります。
例えば、青色申告特別控除を最大限活用するためには、65万円控除を受けるための複式簿記の記帳が必要です。
税理士に依頼すれば、これをスムーズに対応してもらえます。
また、必要経費の見逃しを防ぐことも重要です。税理士はこうした経費計上のルールを熟知しており、見落としを防いでくれます。
加えて、税制上の特例や地域ごとの補助金制度もアドバイスしてくれるので、フリーランスとしての利益を最大化できます。
確定申告や納税がスムーズになる
フリーランスにとって、確定申告は避けられない業務の一つです。
しかし、多くの人にとって確定申告は「面倒で難しい」と感じる作業ではないでしょうか。
確定申告では、書類の記入ミスや添付資料の不備で申告が受理されなかったり、期限を過ぎてしまったりすると、余計な手間やペナルティが発生します。
こういったトラブルを防ぐためにも、税理士のサポートは非常に有効です。
税理士に依頼すれば、確定申告書の作成から税務署への提出まで、すべてをスムーズに進めることができます。
e-Tax(電子申告)を活用する場合でも税理士が代行してくれるため、自分で複雑な設定を行う必要もありません。
控除の適用や経費の整理など、税法に基づいた正確な処理をしてもらえるので、安心して任せられます。
したがって、税理士に依頼すれば確定申告や納税のストレスから解放されるでしょう。
追徴課税のリスクを回避できる
税務調査が行われると、申告内容にミスがないか徹底的に確認されます。
もしミスが発覚した場合、追徴課税を課されるだけでなく、罰金や延滞税が課されることもあります。
経費の過大計上や収入の記載漏れが見つかると、数十万円以上のペナルティを受ける可能性もゼロではありません。
しかし、税理士に依頼することで税務申告の精度を高め、追徴課税のリスクを回避できます。
また、税務調査が入った際も税理士が代理人として対応してくれるため、自分が税務署と直接やり取りする必要がありません。
税制改正にも対応してもらえる
日本の税制は毎年のように改正されており、その内容は非常に多岐にわたります。
フリーランスエンジニアに関連するものだけでも、所得控除の見直しや消費税の変更、インボイス制度の導入など、例を挙げだしたらキリがないほどです。
しかし、税理士はこうした税制改正について常に最新の情報を収集しており、それに基づいてアドバイスしてくれます。
例えば、2023年から導入されたインボイス制度では、取引先から適格請求書の発行を求められるケースが増えました。
税理士に相談すれば、制度の影響を最小限に抑えるための具体的な対応策を提案してくれるでしょう。
また、将来的な税制の動向についてもアドバイスを受けられるため、計画的な資金運用が可能になります。
税理士に依頼するデメリット
フリーランスエンジニアが税理士に依頼するデメリットは以下の2点です。
- コストがかかる
- 税理士選びが難しい
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
コストがかかる
当たり前のことではありますが、税理士に税務処理を依頼するとコストが発生してしまいます。
税理士にもよりますが、税理士に支払う報酬は年間数十万円に上ることもあり、まだ収益が安定していないフリーランスエンジニアにとっては大きな負担となるでしょう。
また、初回相談料や顧問契約料、決算申告の手数料など、税理士のサービス内容や契約形態によってもコストは変動します。
こうしたコストが収益に見合わないと感じる場合、税理士に依頼することでむしろ負担が増える可能性も考えられます。
税理士選びが難しい
はじめて税理士に業務を依頼する時、多くの人が悩むのが「税理士選び」です。
中にはアタリの税理士もいますが、もちろんハズレの税理士も存在します。
万一ハズレの税理士を選んでしまった場合、コストパフォーマンスを最大化できません。
そのため、税理士選びはフリーランスエンジニアにとって非常に重要な課題と言えます。
こうした問題を防ぐためには、事前に税理士の評判や実績を調査し、自分の業務内容に理解が深い税理士を選ばなければなりません。
合う税理士がなかなか見つからないことも
税理士を選ぶ時、多くの場合で直接会って話を進めていきますが、初心者の場合は判断に迷うことも少なくありません。
税理士と一口に言っても、それぞれ得意分野や料金体系が異なります。
特にフリーランスエンジニアの場合、業種特有の税務処理が発生することもあり、それに詳しい税理士を見つけるのは簡単ではありません。
そのため、自分に合った税理士を見つけるには、それなりの時間と労力がかかることは理解しておきましょう。
税理士と相性が合わない場合の問題点
税理士と相性が合わない場合、以下のような問題が発生してきます。
- 意思疎通がスムーズにいかず、必要な情報共有や相談が滞る
- 税理士からのアドバイスに疑念を抱き、適切な判断ができない
- 対応への不満が精神的な負担となり、業務への集中力が低下
- ミスが生じる可能性が高まり、逆にペナルティを受けるリスクが増える
- 必要なサポートを十分に受けられず、経営判断に支障が出る
このようなリスクを避けるためにも、初回の相談時点で十分に話し合い、自分の価値観や要望を理解してくれる税理士を選びましょう。
税理士報酬の相場はどれくらい?
では、税理士の報酬相場はどれくらいなのでしょうか?
ここからは、いくつかのケースにおける税理士の報酬相場と費用を節約するコツをご紹介します。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
確定申告のみ依頼する場合の料金
税理士に確定申告のみを依頼する場合の料金相場は以下の通りです。
| 依頼内容 | 報酬相場 | 備考 |
| 給与所得者(医療費控除など簡単な申告) | 3万円~5万円 | 医療費控除など、比較的シンプルな内容の場合 |
| 副業所得がある給与所得者(雑所得) | 5万円程度 | FXや投資などの雑所得を含む場合 |
| 副業所得がある給与所得者(事業所得) | 個人事業主の相場に準じる | 青色/白色申告の基準に準じる |
| 個人事業主(白色申告) | 5万円~10万円 | 記帳を自分で行う場合 |
| 個人事業主(青色申告:売上500万円未満) | 7万円~10万円 | 記帳を自分で行う場合 |
| 個人事業主(青色申告:売上500~1000万円) | 10万円~15万円 | 記帳を自分で行う場合 |
| 個人事業主(青色申告:売上1000~3000万円) | 15万円~20万円 | 記帳を自分で行う場合 |
| 個人事業主(青色申告:売上3000万円以上) | 20万円~25万円 | 場合によって応相談 |
| 記帳代行込み(青色申告) | +5万円~10万円 | 記帳を税理士に依頼する場合、基本料金に加算されることが多い |
このように、確定申告のみを依頼する場合でも、フリーランス個人の状況や条件によって相場はかなり変動します。
フリーランスエンジニアの中には、税理士に依頼せずに確定申告をしている人も多くいるので、まずは自分で確定申告をやってみてから検討しましょう。
顧問契約の月額費用の相場
税理士に顧問契約をする場合の月額費用相場は以下の通りです。
| 対象 | 月額顧問料の相場 | 決算申告料の相場 | 備考 |
| 法人(小規模) | 2万円~5万円程度 | 10万円~20万円程度 | 売上や依頼内容により変動。決算申告料は月額顧問料の4〜6か月分が一般的。 |
| 法人(中規模以上) | 5万円~10万円以上 | 20万円~50万円以上 | 売上規模や業務量が増えるため、報酬が高くなる傾向あり。 |
| 個人事業主 | 1万円~3万円程度 | 5万円~10万円程度 | 事業規模や記帳代行の有無により変動。節税対策や経理相談も含まれるケースが多い。 |
| 訪問頻度が多い場合 | 月額3万円~10万円以上 | 依頼内容により変動 | 定期訪問や経営相談が含まれると報酬が高くなる。 |
| 記帳代行込み | 上記金額に+5,000円~1万円程度 | 上記金額に含む場合もあり | 記帳作業を税理士に任せる場合、追加費用がかかることが多い。 |
顧問契約とは、一定期間(通常は月単位や年単位)継続的に税理士から税務や会計に関するサポートを受ける契約です。
確定申告のみを依頼する場合は、特定の期間(通常は年に1回)だけ税理士に業務を依頼しますが、顧問契約の場合は月額払いが一般的です。
また、その分コストもかさんでくるので、顧問契約はある程度の収益規模が確保されている場合のみ検討しましょう。
費用は税理士事務所によってかなり差がある
税理士の報酬相場は、依頼する税理士事務所の規模や特徴によって大きく変動します。
そのため、自分の事業規模に合った税理士事務所を選ぶ必要があります。
なお、費用が高い税理士事務所の特徴は以下の通りです。
- 大規模な税理士事務所・会計事務所
- 専門分野に特化している事務所
- 都市部に拠点がある事務所
費用が低い税理士事務所の特徴は以下の通りです。
- 個人経営の税理士事務所
- 地方に拠点を置く事務所
- オンライン特化型の事務所
したがって、事業規模がすでに大きく安定しており、節税対策次第で非常に大きなリターンを手に入れられる人は、費用が高い税理士事務所を検討した方がよいと言えます。
まだ事業を始めたばかりで基本的な会計ソフトを利用すれば十分に税務処理が可能な人は、費用が低い税理士事務所を選ぶのがおすすめです。
費用を節約する方法はある?
税理士事務所に依頼する場合の料金は、お世辞にも安いとはいえません。
しかし、以下の方法で税理士への依頼費用を節約できます。
- 記帳作業は通常別料金なので、会計ソフトを利用して自分で記帳すれば費用を削減可能
- 税務申告や決算書作成など必要最小限の業務だけを依頼する
- 料金やサービス内容を比較し、最適な事務所を選ぶ
- オンライン特化型の税理士事務所を選ぶ
- 顧問契約を結ばず、確定申告や決算時だけスポットで依頼する
- 地方の税理士事務所を検討する
ただし、費用を節約できても最適なサービスを受けられなかったら元も子もありません。
したがって、費用対効果を事前に把握しておき、損益分岐点を明確にした上で検討しましょう。
税理士に支払う費用は経費にできる?
多くのフリーランスや個人事業主は、事業にかかわる経費を確定申告の際に計上することで節税対策をしています。
では、税理士に支払う費用は経費として計上できるのでしょうか?
結論からいうと、税務や会計に関する業務が事業に関連している場合、税理士への報酬は経費として計上できます。
例えば、以下のようなケースでは税理士費用を経費として計上可能です。
- 確定申告の代行
- 記帳代行や決算書作成
- 税務相談やアドバイス
- 税務調査対応
対して、以下のようなケースは基本的に経費として認められません。
- 相続税や贈与税、住宅ローン控除など個人的な税務対応
- 曖昧な理由で事業関連の証明が難しい場合
なお、税理士報酬は「支払手数料」「支払報酬料」「業務委託費」などの勘定科目で計上するのが一般的です。
このように、一部の例外を除いて税理士費用は経費として計上できるので、確定申告の際は税理士費用を経費に含めた上で書類を提出しましょう。
税理士を選ぶ際のチェックポイント
では、フリーランスエンジニアが税理士を選ぶ時にはどのような点を重視すればよいのでしょうか?
ここからは、税理士を選ぶ際のチェックポイントをわかりやすく解説していきます。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
これまでの実績や口コミを調べる
1つ目のチェックポイントは、税理士の実績や口コミです。
税理士の専門性や対応力を判断するためには、これまでの実績や過去のクライアントの評価が判断指標になります。
税理士事務所の公式サイトやSNS、口コミサイト(例:税理士ドットコム)を活用して、他のフリーランスがどのような評価をしているかを調べましょう。
例えば、「フリーランスエンジニア向けの青色申告サポートに強い」や「対応がスピーディーで、節税についての提案が的確」といった口コミがあれば比較的信頼できます。
反対に、「レスポンスが遅い」や「不明瞭な料金が発生した」といったネガティブな口コミが多い場合は注意が必要です。
ただし、こういった口コミというのは基本的に大手の税理士事務所のみの場合が多いです。
個人経営の税理士事務所などの口コミは探してもほとんど見つからないので、その場合は直接会って判断するしかありません。
フリーランスエンジニア案件に強い税理士を選ぶ
フリーランスエンジニア特有の課題に対応できる税理士を選ぶことも大切です。
フリーランスエンジニアはクラウドソーシングや複数のクライアントからの収入がある場合が多く、雑所得と事業所得の区分、経費計上のルールがかなり複雑です。
このような事情を熟知している税理士であれば、正確な申告や節税のアドバイスが期待できます。
しかし、フリーランスエンジニアを専門にしている税理士は増えつつあるので、できるだけIT業界に特化している税理士を選びましょう。
質問に丁寧に答えてくれる税理士を選ぶ
3つ目のチェックポイントは、質問に丁寧に答えてくれるかどうかです。
たとえ税務の知識が豊富でも、説明が不十分な税理士では適切なサポートを受けられません。
例えば、「青色申告の特別控除を受けるには具体的に何をすればいいか」といった質問に対して、書類の準備方法や提出期限を明確に説明してくれる税理士は信頼できます。
一方で、「調べておきます」と回答を先延ばしにする税理士は避けた方が良いかもしれません。
なるべくその場で即答してくれるような税理士を選びましょう。
契約内容が明確になっているか確認する
最後のチェックポイントは、契約内容が明確であるかどうかです。
料金体系やサービス内容が曖昧な場合、後々トラブルになる可能性があるので契約内容は必ず確認しておきましょう。
特に注意したいポイントは以下の2点です。
契約期間や解約条件を事前に確認する
契約内容でまず抑えておきたいのが、「契約期間」と「解約条件」です。
税理士との契約期間は、スポット契約と月額または年単位の支払いが一般的です。
例えば、確定申告だけを依頼する場合はスポット契約になることがほとんどですが、日常的な税務相談や記帳代行も含む顧問契約の場合は、月額または年単位の契約が基本です。
顧問契約の場合はもちろんコストも高くなってくるので、契約期間は必ず確認しておきましょう。
また、解約条件も明文化しておく必要があります。
例えば、期待していた程のサポートが得られなかった場合や、他にいい税理士を見つけた場合は別の税理士に依頼する可能性も考えられます。
その際に解約条件が明文化されていないと、解約時に違約金を請求される、または一定の期間は契約を続ける義務が生じるなど、想定外のコストやトラブルが発生するかもしれません。
したがって、契約期間が「1年」「自動更新」などで設定されているかと、解約の際の通知期限、違約金やペナルティの有無などを必ず確認しておきましょう。
追加料金が発生するケースを把握する
確定申告のみを税理士に依頼する場合、税理士が担当する業務は、申告書の作成や税額の計算といった基本的な業務に限られます。
しかし、契約内容や依頼する業務の範囲によっては追加料金が発生するケースもあります。
例えば、以下のようなケースが典型例です。
- 記帳代行や資料の整理が必要な場合
- 年末調整や給与計算を依頼する場合
- 税務調査の立会いや修正申告対応が発生した場合
- 緊急対応や特別な相談(スポット契約)が必要な場合
こういったケースでは、ほとんどの場合で追加料金が発生してしまいます。
料金は各税理士事務所によって違うので一概にはいえませんが、記帳代行では少なくとも5万円以上が相場です。
したがって、税理士に税務処理を依頼する場合は、自分がして欲しい業務を本当に代行してくれるかどうかを契約書を通して必ず確認しておきましょう。
税理士に依頼せずに自分で申告するなら
フリーランスエンジニアは、自分で確定申告している人も少なくありません。
事業規模がまだ小さい場合や収入がそこまで高額ではない場合、むしろ自分でやった方がコストパフォーマンスを最大化できるケースも多いのです。
税務処理を自分ひとりでする場合のポイントは以下の2点です。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
会計ソフトを活用するのがおすすめ
現在では非常に多くの種類の会計ソフトがリリースされているので、税務処理を自分でするなら会計ソフトを必ず活用しましょう。
フリーランスエンジニアに人気の会計ソフトは以下の通りです。
| ソフト名 | 特徴 | 料金プラン |
| freee(フリー) |
– 直感的な操作性と自動化機能(銀行口座やクレジットカードと連携)。 – 請求書作成や給与計算など多機能対応。 – クラウドベースで場所を選ばない。 |
– スターター: 月額5,480円(年払い)/ 月額7,280円(単月) – スタンダード: 月額8,980円(年払い)/ 月額11,980円(単月) – アドバンス: 月額39,780円(年払い)/ 月額51,980円(単月) |
| マネーフォワード クラウド |
– バックオフィス業務を一元管理(会計、請求、経費精算、給与計算)。 – 銀行口座やクレカと連携した取引の自動仕訳。 – スケーラビリティが高く、事業成長に対応。 |
– スモールビジネス: 月額2,980円(年払い)/ 月額3,980円(単月) – ビジネスプラン: 月額4,980円(年払い)/ 月額5,980円(単月) |
| やよいの青色申告 オンライン |
– 初心者にも使いやすい操作性。 – 青色申告特化で申告書作成が簡単。 – サポート体制が充実しており、電話やチャットで質問可能。 |
– セルフプラン: 年額8,800円(年払いのみ) – ベーシックプラン: 年額13,200円 – トータルプラン: 年額26,400円 |
(※リンクをクリックすれば各会計ソフトの公式サイトへ飛べます)
上記3種類の会計ソフトであれば、初心者でもすぐに使いこなせるようになるはずです。
無料体験もできるので、まずは実際に触ってみて使用感を確かめてから導入を検討しましょう。
基本的な税務知識を身につける
会計ソフトを使えば、そこまで複雑な税務処理がない限り、基本的に誰でも確定申告を乗り越えられるはずです。
しかし、やはり使用する上で基本的な税務知識を身につけておいた方が作業効率が高くなります。
例として、税務処理でよく使われる用語をチェックリスト形式でリストアップするので、以下の用語がほとんどわからないような人は下調べしておきましょう。
- 所得:収入から経費を引いた金額
- 経費:事業運営に必要な支出(例:通信費、交通費など)
- 控除:課税所得を減らす仕組み(例:青色申告特別控除)
- 課税所得:税金が課される所得の金額(所得-控除)
- 青色申告:特典が多い申告方式(例:特別控除や損失繰越)
- 白色申告:手続きが簡単だが控除が少ない申告方式
- 源泉徴収:報酬から差し引かれる所得税
- 仕訳:取引内容を帳簿に記録すること
- 収支内訳書:白色申告時に必要な収入と経費を記録した書類
- 決算書:青色申告時に作成する損益計算書や貸借対照表などの書類
- 消費税:売上に課される税金(年間売上1,000万円以上で課税)
- 免税事業者:一定条件を満たすと消費税の納税が免除される事業者
- 固定資産:事業で使う長期的な資産(例:パソコン、オフィス家具)
- 減価償却:固定資産の価値を数年に分けて経費として計上すること
- 振替伝票:仕訳を記録するための書類
フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ

フリーランスエンジニアになったばかりの頃は、案件の探し方で悩むことも少なくありません。
もし案件探しでお悩みなら「エンジニアスタイル」をご活用ください!
エンジニアスタイルは、数ある案件検索サイトの中でも業界最大級の30万件以上の掲載数を誇ります。
リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。
契約前のサポートはもちろん、契約後のアフターサポートが充実しているので、初心者でも安心なのもうれしいポイント。
登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルの利用を検討してみてください!
まとめ
本記事では、フリーランスエンジニアが税理士に依頼する際のメリット・デメリット、かかる費用の相場や節約方法、そして税理士を選ぶ際のポイントについて解説しました。
フリーランスエンジニアが税理士を依頼すべきかどうかは、事業の規模や収入、税務処理への負担感によって異なります。
しかし、税理士のサポートが本業に集中できる環境を整えてくれることは間違いありません。
特に、税務調査のリスク軽減や節税の最適化を考えるなら、専門家の力を借りるのは非常に有益です。
本業に集中できる環境を整え、より効率的な事業運営を目指していきましょう!
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。