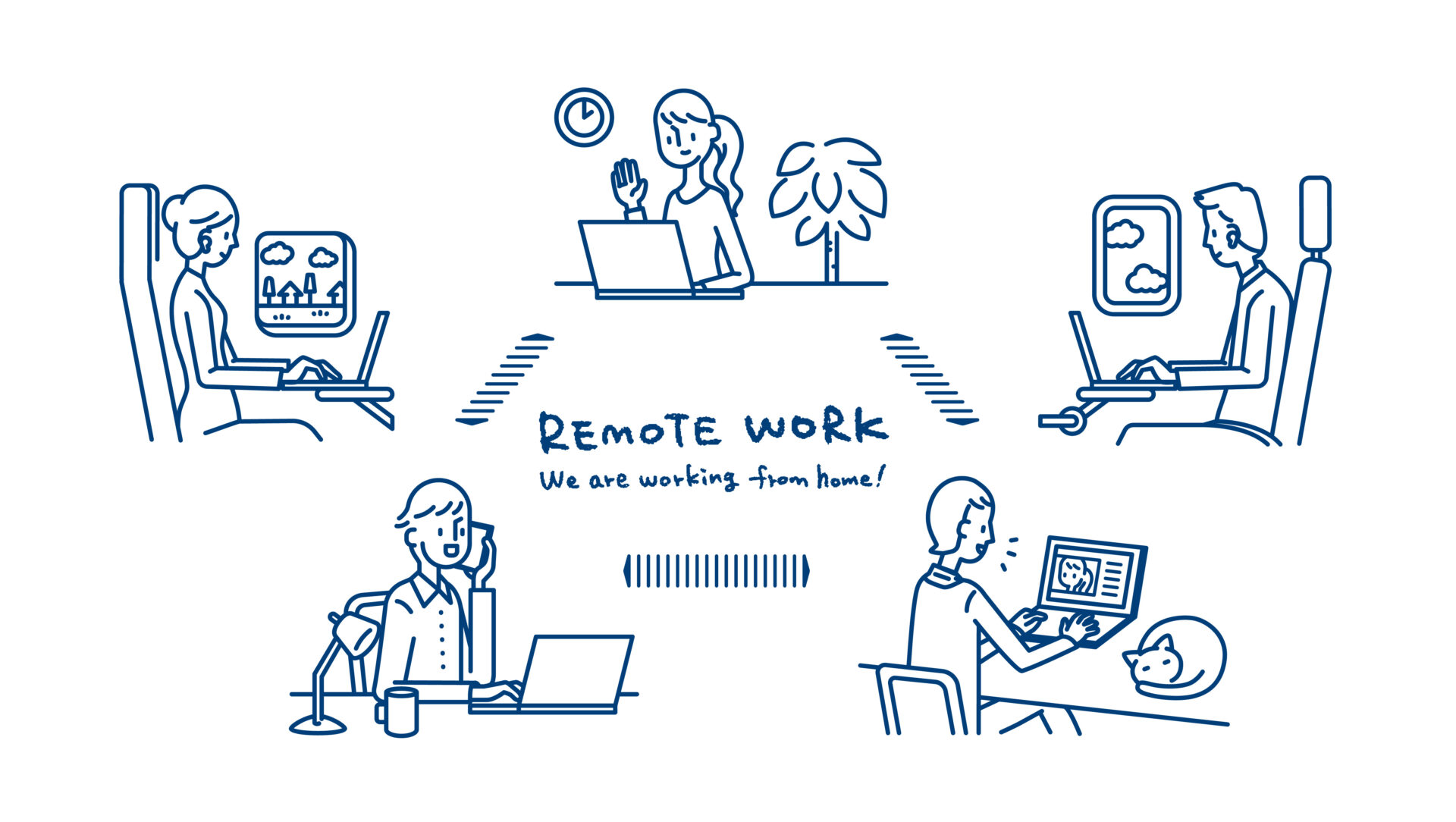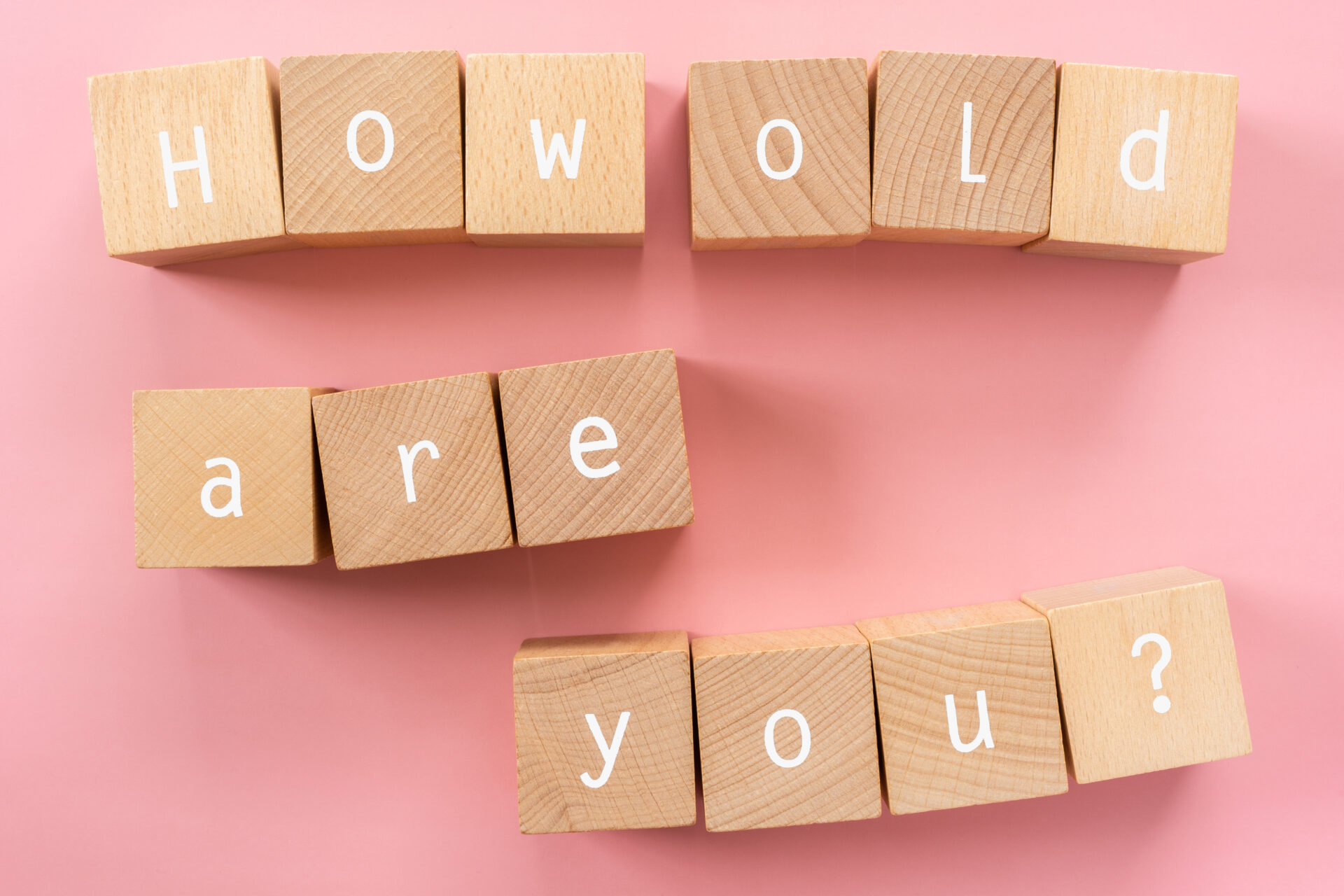【2023年最新】フリーランスエンジニアが知っておきたいインボイス制度と損しないための対策とは
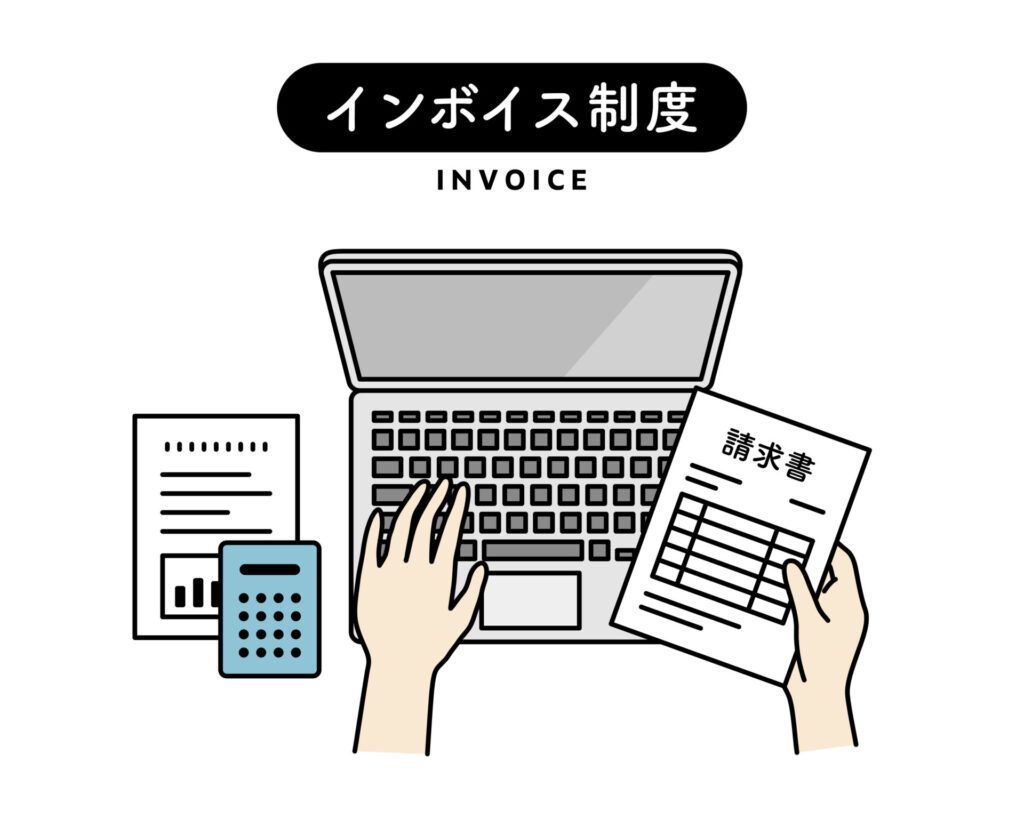
はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。フリーランス・副業案件一覧を以下からご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
2019年10月に実施された消費税10%への引き上げ、およびそれに伴う複数税率の導入をキッカケに、2023年10月からインボイス制度が実施されることになりました。
このインボイス制度なるものが実施されることで、多くの企業や個人事業主に影響がでると考えられています。
インボイス制度はフリーランスエンジニアにとって大きく関わりのある制度です。
そのため、今のうちにインボイス制度についての理解を深め、予測される課題への対策を講じることが重要になってきます。
この記事ではフリーランスエンジニアが知っておくべきインボイス制度の内容について説明し、それについてどのような対策をすればいいのかについて解説をしていきます。
そもそもインボイス制度とは
まず始めに、そもそもインボイス制度とはどのような制度なのかを解説します。
インボイス制度とは、『適格請求書等保存方式』のことをいい、請求書や納品書を作成する際に、定められた要件の記載、および保管をしなければいけないというものです。
ここでいう定められた要件の記載というのは、現行の請求書仕様である『区分記載請求書』に項目の追加をすることにあります。
現行の区分記載請求書の記載事項は以下の通りです。
- 請求書発行者の氏名、または名称
- 請求書受領者の氏名、または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 取引金額
- 軽減税率の対象品目の有無
- 税率ごとに区分後、それを合計した税込額
これらの項目に加え、インボイス制度の実施下では以下の項目の追加記載が必要になります。
- 請求書発行者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
上記項目を追記した『適格請求書』を作成、保存し、適正に消費税を納めることで、仕入税額控除の適用を受けることが可能になります。
つまり、適格請求書が仕入税額控除を適用するための証明書という役割を果たしてくれることになります。
インボイス制度導入の背景と目的
なぜこのような制度が設けられることになったのでしょうか。
インボイス制度施行の主な目的は、正しい消費税額の把握、および適正な納税を促すためです。
現在の消費税率は10%になりますが、食料品などの一部品目については軽減税率の8%が適用されています。
品目によって税率が異なることから、計算が煩雑になり、申告内容にミスが発生するという事態が発生していました。
そのため、どちらの税率が適用されるのかを明確にする必要があったというわけです。
この課題を解決するための方策がインボイス制度です。
インボイス制度が導入されることで、該当する取引ごとの消費税額が可視化され、正確な数値を算出することができます。
また、この課題に加えて、免税事業者は納税の義務がないため、これまで消費税を申告することなく自身の利益としてしまうケースが多くありました。
このような不正を防ぐことも制度導入の背景にあります。
インボイス制度の実施により、申告内容の誤りや不正の防止に繋がり、取引の透明性を高めることが期待されています。
インボイス制度に対応するための準備
インボイス制度に対応するためには、『適格請求書発行事業者』としての登録をする必要があります。
適格請求書発行事業者の登録をしたい場合は、適格請求書発行事業者登録申請書を作成し、インボイス登録センターに書類を提出するという流れになります。
なお、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみであり、免税事業者は適格請求書発行事業者になることはできません。
インボイス制度の開始は2023年10月1日からです。
開始当初から適格請求書を発行できるようにするためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者としての登録を済ませておく必要があります。
なお、この制度には2029年9月30日までの6年間、2つの経過措置対応が設けられています。
免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、上述した適格請求書発行事業者登録申請書に加え、課税事業者になるための届出書の提出が求められます。
しかし上記期間内であれば課税事業者になるための届出書の提出は不要です。
もう1つの経過措置対応は、制度導入後に適格請求書発行事業者が免税事業者と取引をする場合、本来であれば仕入税額控除の適用を受けることができません。
ただし2029年9月30日までの間は、段階的に一定割合の仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
具体的には始めの3年間は80%、残りの3年間は50%の仕入税額控除を適用することができます。
免税事業者と課税事業者の確認
インボイス制度を理解するために、免税事業者と課税事業者の違いについて整理をしたいと思います。
免税事業者とは、特定の条件を満たすことで消費税の納税が免除されている事業主のことをいいます。
詳細については後述しますが、ここでいう特定の条件とは、基準となる期間の課税売上高が1000万円に満たない場合などをいいます。
また、上記に加えて起業後2年間においても免税事業者としての立場でいることが可能です。
次に課税事業者ですが、こちらは消費税の納税をおこなっている事業主のことをいいます。
免税事業者に該当しない場合は必然的に課税事業者という扱いになります。
フリーランスエンジニアの場合、大半の方は免税事業者に該当すると思われます。
従来の消費税課税方式はどのような形か
従来の消費税課税方式については、取引をおこなう際に特定の商品を除き消費税が発生します。
この時、買い手側は売り手側に対し消費税を支払います。
売り手側はその消費税を一時的に預かることで、それを国に納税する義務が生じます。
課税事業者の場合は、この一時預かりの消費税と、仕入時などの際に支払った消費税の差分を納税する必要があります。
例を挙げると、7000円の仕入れをすると700円(10%適用の場合)の消費税を支払います。
その後10000円の販売をした場合、1000円(10%適用)の消費税を受け取ることになりますので、差し引きで300円の消費税を納税する必要があります。
一方で免税事業者の場合は納税の義務がないため、これまでは買い手から受け取った消費税をそのまま自身の利益とすることができました。
上記の例でいうと、販売時に受け取った1000円について、免税事業者は申告不要となります。
インボイス制度が企業にもたらす影響とは
従来の消費税の課税方式は上述した通りになりますが、インボイス制度が導入されることでどのような影響があるのかを解説します。
発注者である企業(課税事業者)やフリーランスの中でも免税事業者であるフリーランスの方(=非適格請求書発行事業者)に発注した場合、消費税の仕入税額控除が受けられず、これまで免税対象とされてきた消費税分を企業側が多く払う必要が出てきます。
例えば、7000円の仕入れに対し10000円の販売をした場合、差し引き300円の納税をする必要があると解説しました。
このケースで仕入税額控除が受けられない場合を例にあげると、仕入時の700円の消費税支払いに加え、販売時の1000円の一時預かり分も全て納税をしなければなりません。
つまり、合計で1700円の消費税を納税する必要があります。
インボイス制度に伴い、課税事業者は適格請求書発行事業者としての登録をしないと仕入税額控除を適用することができず、上述した例のように必要以上に消費税を支払わなければならないことになります。
消費税についてもおさらい。フリーランスエンジニアが消費税の申告をしなければならないケースとは
インボイス制度を更に理解するため、消費税についてもおさらいをしたいと思います。
フリーランスエンジニアはどのような取引状況下の場合に消費税を申告する必要があるのでしょうか。
消費税の納税義務は課税事業者か否かによって決まります。
課税事業者と見做されるケースはいくつかありますので、それぞれの内容について解説します。
前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた
課税事業者と見做されるケースの1つ目は、『基準期間』の課税売上高が1000万円を超えた場合です。
ここでいう基準期間とは前々年度のことを指します。
前々年度の事業期間が12ヶ月に満たない場合は、課税売上高を1年に換算することで課税事業者の区分に該当するかどうかを定めます。
例えば事業期間が9ヶ月、課税売上高が900万円だった場合、1ヶ月当たりの課税売上高は以下のように算出します。
課税売上高900万円÷事業期間9ヶ月=100万円(1ヶ月当たりの課税売上高)
この金額を12ヶ月に換算します。
100万円✖️12ヶ月=1200万円(1年換算の課税売上高)
上記の例の場合は基準期間の課税売上高が1000万円を超えたと見做されます。
よって、課税事業者としての区分に位置付けられます。
前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、給与等支払額が1,000万円を超えた
課税事業者と見做されるケースの2つ目は、『特定期間』の課税売上高が1000万円を超えた場合です。
特定期間とは、前年度の1月1日から6月30日の期間を指します。
特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者と判定されます。
ただし、この判定は同期間中の給与等の支払額に代えて判定をすることもできます。
つまり、特定期間の課税売上高が1000万円を超えていたとしても、給与等の支払額が1000万円を超えていない場合は課税事業者と見做されることはありません。
消費税課税事業者選択届出書を提出した場合
課税事業者と見做されるケースの3つ目は、消費税課税事業者選択届出書を提出することです。
課税売上高が1000万円に満たない免税事業者であっても、この届出書を提出することで課税事業者になることができます。
届出書を提出した翌日から課税事業者としての適用を受けることが可能となります。
なお、課税事業者としての適用をやめることも可能で、その場合は別の届出書を提出する必要があります。
エンジニアスタイルでは、20万件に及ぶフリーランスエージェントの案件をまとめて閲覧することができます。
自分に合った案件を見逃すことなく、じっくり案件を比較することで最適な案件に参画することができるので、ぜひ活用ください。
インボイス制度がフリーランスエンジニアに与える影響とは
インボイス制度の導入にあたり、フリーランスエンジニアにとってどのような影響がでてくるのかを解説します。
インボイス制度は全てのフリーランスエンジニアに影響があります。
ただし、現在免税事業者であるのか、それとも課税事業者であるのかによって影響度合は異なります。
フリーランスエンジニアは『免税事業者』のままで居続けるのか、それとも『課税事業者』に転身するのかを選択しなければなりません。
では免税事業者と課税事業者のどちらを選択すればいいのでしょうか。
この部分についてはどちらを選択してもデメリットが起こり得ます。
ここではそれぞれにどのようなデメリットが生じうるのかを解説します。
「免税事業者」のままの場合、案件が受けにくくなる
免税事業者のままでいる場合のデメリットは、案件が受けにくくなることです。
仕入税額控除を適用するためには、適格請求書発行事業者から適格請求書を受け取る必要があります。
しかし、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみであり、免税事業者にはその資格がありません。
つまり、クライアントが課税事業者の場合、免税事業者から受け取る請求書では仕入税額控除を適用することができないということになります。
そのため、クライアントが免税事業者と取引をする場合は、例え契約額自体が同額であったとしても、消費税を必要以上に納めなければなりません。
このことから、クライアントは免税事業者に対して仕事の発注を控えることが予想され、課税事業者ばかりに案件が寄せられる可能性があります。
業務の質が特別に高い、または長年の信頼関係が築けているなど、顧客満足度が高くない場合は免税事業者は案件の獲得が難しくなってしまうでしょう。
「課税事業者」になった場合、消費税支払いの義務が発生して収益が減る
一方で、免税事業者から課税事業者に転身する場合のデメリットは、消費税の支払い負担が発生することです。
課税事業者は適格請求書発行事業者になる資格があるため、クライアントにとっては仕入税額控除を適用することが可能です。
そのため、上述したようにクライアントとしては消費税の支払い負担軽減のため、免税事業者よりも課税事業者を優先して取引先を選定することが予想されます。
よって、案件を獲得するためには課税事業者になった方が有利であることは確かです。
しかしその一方で、課税事業者になるということは納税の義務が発生するため、免税事業者の時よりも支払う消費税の分だけ収益が減少することになります。
課税事業者になることで案件が獲得しやすくなったとしても、その売上は消費税分で相殺されてしまう可能性は否めません。
フリーランスエンジニアが取れるインボイス制度対策
免税事業者、課税事業者のどちらの立場であってもデメリットがあることを解説しました。
ではこのデメリットを踏まえ、フリーランスエンジニアはどのような対策を講じるべきなのかを解説します。
【免税事業者のままの場合】交渉して消費税分を値下げしてもらう
免税事業者のままでいる場合の対策は、値下げ交渉をすることです。
クライアントは仕入税額控除を適用することができないため、クライアントが負担しなければいけない消費税額と同等分の値下げなど、取引価格の見直しを提案してみるといいでしょう。
価格の見直しにより、クライアントは仕入税額控除を適用できなくとも、実質的に支払う契約金額に差は発生しないことになります。
そうすることで、免税事業者にも案件の提供や取引の継続に応じてくれる可能性が高まります。
本来値下げ交渉はクライアント側からおこなうものですが、こちらから提案をすることで、信頼関係を高める副次的効果も期待できるかもしれません。
税務署で登録して課税事業者になる
もう1つの対策としては、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者として登録をすることです。
免税事業者のままでは、上述したような値下げ交渉をしない限り取引先選定自体から外れてしまう可能性があります。
課税事業者になることでクライアントは仕入税額控除を適用できるので、従来の取引継続が期待できます。
また、新規案件の獲得などについても免税事業者より有利に進めることができると考えられます。
ただし、先にも述べましたが、課税事業者になることで消費税の負担が生じますので、課税事業者になるかどうかは慎重に判断すべきです。
まとめ
最後に今回の記事のまとめです。
今回の記事では以下の内容について解説をしました。
- インボイス制度についての概要
- 従来の消費税納税の仕組みと、インボイス制度導入に伴う消費税納税の仕組みの違いや変更点について
- インボイス制度導入に伴う影響範囲とその対策について
フリーランスエンジニアにとってインボイス制度は非常に大きな影響を及ぼします。
免税事業者のままでいるのか、課税事業者に転身するのかは取引先の事情などにもよるため、一概にどちらがいいのかは判断が難しいと言わざるを得ません。
今回の記事を参考にインボイス制度を正しく理解し、デメリットを最小限にするための行動を選択してください。
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。