フリーランスエンジニアが契約期間を選ぶ際の注意点は?長期契約・短期契約のメリットとデメリット

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
フリーランスエンジニアとして活動する上で、契約期間の選び方はキャリアや働き方に大きな影響を与えます。
長期契約は安定した収入を得られる反面、技術の成長が停滞するリスクが高いです。
一方、短期契約は多様な経験やスキルアップの機会が豊富ですが、収入の安定性には課題が残ります。
本記事では、長期契約と短期契約それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説し、どの契約が自分に合っているかを判断するためのポイントを紹介します。
<この記事を読むメリット>
- 長期契約と短期契約の特徴を比較し、自分に合った働き方が分かる
- 案件を切り替える適切なタイミングが分かる
- 新しい案件を効率的に獲得する具体的な手段を知れる
フリーランスエンジニアとしてのキャリアを描くには、契約期間の選び方が非常に重要になってきます。
本記事を参考に、自分にとって最適な契約期間を見極め、安定した収入とスキルアップの両立を目指しましょう!
フリーランスエンジニアの一般的な契約期間はどれくらい?

フリーランスエンジニアは基本的に企業(または個人)と業務委託契約や請負契約を交わし、その収益で生計を立てています。
しかし、業務委託契約の契約期間は短期契約のものもあれば、長期契約を前提としたものもあります。
では、一般的にフリーランスエンジニアの契約期間はどれくらいなのでしょうか?
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
半年から1年が平均的
結論からいうと、フリーランスエンジニアの契約期間は業務の性質に応じてさまざまですが、半年から1年程度が平均的な期間です。
そもそも、ITプロジェクトというのはアジャイルやスクラム開発を除くと、基本的に長期間を見越して設計されます。
具体的な期間はプロジェクトの規模感によっても違いますが、設計フェーズから運用フェーズに入るまで少なくとも半年以上かかります。
かなり大規模なものであれば3年以上かかるものもありますし、比較的小規模なものであれば1年も経たずして終了することも珍しくありません。
また、フリーランスエンジニアに依頼する業務の中で最も多いのが、開発フェーズやテストフェーズといった下流工程の業務です。
こういった下流工程の業務は、上流工程に比べて要求の変更リスクが少ない場合が多く、契約期間が半年から1年で完結するケースが多いのです。
したがって、フリーランスエンジニアの一般的な契約期間は半年から1年で設定されるケースが多くなります。
フリーランスエンジニアが長期契約をするメリット・デメリット
フリーランスエンジニアはさまざまな働き方を実現できるのが魅力の一つですが、その戦略は人それぞれ違います。
安定性を重視して長期契約のみを受注している人もいれば、短期契約のプロジェクトを複数掛け持ちして収益性を高める人もいます。
しかし、一概にどちらの方がいいとは言い切れません。
そこでここでは、フリーランスエンジニアが長期契約をするメリットとデメリットについて詳しくみていきましょう。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
長期契約をするメリット
フリーランスエンジニアが長期契約をするメリットは以下の2点です。
- 安定した収入を得られる
- クライアントやチームメンバーと信頼関係を構築できる
それぞれについて、以下でわかりやすく説明します。
安定した収入を得られる
フリーランスは会社員のように固定給が保証されているわけではないので、収入が不安定になりやすいです。
しかし、長期契約を優先して受注すれば、こういった収入の不安定さを緩和できます。
短期案件では、案件が終わるたびに次の仕事を探す必要があり、その間に収入が途絶えるリスクがどうしても発生してしまいます。
一方で、長期契約では「来月も安定した収入がある」という安心感が得られるため、技術向上や副業への挑戦といった自己投資の余裕も生まれるでしょう。
また、クライアントが定期的に報酬を振り込む形になるので、急な支払い遅延や報酬トラブルを回避しやすくなる点もメリットです。
クライアントやチームメンバーと信頼関係を構築できる
長期契約を続けることで、クライアントやチームメンバーと深い信頼関係を築くことができます。
こういった信頼関係(または人脈)は、案件終了後のリピート依頼や、他のクライアントへの紹介といった形で次のビジネスチャンスにもつながります。
また、クライアントが柔軟な対応をしてくれるケースも増えてくるので、スケジュールの調整や報酬交渉がスムーズになりやすいです。
加えて、長期プロジェクトではチームメンバーとの協力機会が自然と増えるので、徐々に仕事もしやすくなっていき、業務効率も大幅にアップします。
業務効率が上がれば別のプロジェクトとの掛け持ちも視野に入ってきますし、精神的負担も減ってくるので一石二鳥といえるでしょう。
長期契約をするデメリット
フリーランスエンジニアが長期契約をするデメリットは以下の3点です。
- 仕事が単調に感じやすい
- 新しい技術やトレンドを知る機会が減る
- 途中で契約が打ち切りになる可能性も
それぞれについて、以下でわかりやすく説明します。
仕事が単調に感じやすい
長期契約のプロジェクトでは一般的な会社員と同じように、毎日固定の業務を担当することがほとんどなので、仕事が単調に感じやすいです。
例えば、1年以上の契約で同じプロジェクトの保守運用を担当する場合、日々の業務が「既存システムの不具合対応」や「ルーチン作業の自動化」に偏ることがあります。
最初は新鮮だった作業も、数ヶ月も経てば「刺激が少ない」と感じるようになるかもしれません。
また、固定のクライアントに長く携わることで、業務範囲が広がりにくくなる恐れもあります。
例えば、「フロントエンドだけ」「バックエンドだけ」といった特定領域の作業に留まり続けると、その後のキャリアの選択肢が狭くなってしまいます。
したがって、常に新鮮さを求めているようなフリーランスエンジニアは長期契約には向いていないかもしれません。
新しい技術やトレンドを知る機会が減る
フリーランスエンジニアのメリットの一つは、さまざまなプロジェクトに携わることで新しい技術やトレンドを知って他のエンジニアとの差別化が図れる点にあるといえますが、長期契約の場合はこういったメリットが失われてしまうかもしれません。
例えば、1年間ずっと同じフレームワーク(ReactやLaravelなど)を使用したプロジェクトに関わっていると、その間に業界で新しい技術(Next.jsや新しいクラウドサービスなど)が台頭しても、すぐにシフトするのは難しいと言わざるを得ません。
その結果、自分のスキルが市場のトレンドに後れを取ってしまい、次の案件を探す際に不利になるリスクも考えられます。
特に日本のIT業界は、現場経験を最も重要視する傾向があるので、長期契約ばかりを受注していると次の案件を受注する際に若干不利になる可能性があります。
もちろん、長期契約の中には柔軟に最先端技術を取り入れていくような案件もありますが、仕様書を先に作成する関係上、どうしても柔軟性に欠けてしまいます。
途中で契約が打ち切りになる可能性も
長期契約といえども、クライアントの事情によって途中で契約が打ち切りになる可能性もゼロではありません。
例えば、プロジェクトの予算削減や、クライアント側での組織変更により、契約期間を満了する前に業務を終了するケースが発生することもあります。
こうした場合、急な契約解除によって「次の案件がすぐに見つからない」「収入が途絶える」といった事態に陥るかもしれません。
クライアントが打ち切りを判断した理由が必ずしもエンジニアのスキル不足とは限りませんが、契約終了のタイミングでの不備が自身の評判に影響することも考えられます。
こういったリスクを減らすためにも、契約時に終了条件や通知期間を明確にしておくことが重要です。
フリーランスエンジニアが短期契約をするメリット・デメリット
では逆に、フリーランスエンジニアが短期契約をするメリットとデメリットは何なのでしょうか?
ここからは、短期契約のメリットとデメリットについて詳しくみていきましょう。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
短期契約をするメリット
フリーランスエンジニアが短期契約をするメリットは以下の2点です。
- 多様なプロジェクトを経験できる
- 新しい技術を学ぶことができる
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
多様なプロジェクトを経験できる
短期契約ではさまざまなクライアントと契約できるため、非常に幅広いプロジェクトを経験できます。
そのため、ポートフォリオを構築する際に非常に見栄えの良いポートフォリオを構築できます。
これにより、エンジニアとしての経験値が大幅に増え、「どの分野でも対応できる」という差別化点を持つことができるでしょう。
また、複数のクライアントや業界に触れることで、異なる開発スタイルやプロジェクトマネジメント手法(アジャイルやウォーターフォールなど)を学ぶ機会にも恵まれます。
結果として、技術力だけでなくプロジェクト全体を理解し、柔軟に対応する力も身につきます。
ただし、クライアントの中には「経験年数」を重視する企業も多いので、この点は一長一短といえるかもしれません。
新しい技術を学ぶことができる
短期契約では次々と異なるプロジェクトに関わるため、新しい技術を学ぶ機会に恵まれます。
例えば、ある短期プロジェクトで「最新のクラウド技術(AWS LambdaやGCP)」を使ったシステム開発に携わり、その次のプロジェクトでは「Next.jsやReactの最新バージョン」を使用したフロントエンド開発に取り組むことも可能です。
このように、短期契約では新しいツールやフレームワークを次々と体験できるため、自身のスキルセットを効率的に拡張できます。
技術トレンドが移り変わりやすいIT業界では、新しい技術をキャッチアップし続けることが重要です。
短期契約で得た技術は次の案件でも活かすことができるため、スキルの循環が生まれ、長期的なキャリア形成においても非常に有利に働きます。
短期契約をするデメリット
フリーランスエンジニアが短期契約をするデメリットは以下の2点です。
- 収入が不安定になるリスクがある
- クライアントとの信頼関係が希薄になりがち
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
収入が不安定になるリスクがある
短期契約の最も大きなデメリットは、収入が不安定になってしまう事と言えるでしょう。
プロジェクトを担当していない期間はもちろん収入は発生しないので、生活費や税金の支払いが遅れてしまうリスクも考えられます。
さらに、次の案件が確実に見つかる保証はないため、収入の見通しが立てにくく、計画的な貯蓄や投資も難しいと言わざるを得ません。
また、短期案件は基本的に単価が高めに設定されることが多いですが、案件の頻度や空白期間の影響で、結果的に年間の総収入が長期契約に比べて低くなるケースもあります。
特に、クライアントからの支払いが遅れた場合や、突発的なキャンセルが発生した場合には、大きな影響を受けることになります。
こうした不安定さを緩和するためには、案件の終了時期を見越して早めに次の案件を探したり、副業や複数のクライアントと並行して契約するなどの工夫が必要です。
クライアントとの信頼関係が希薄になりがち
短期契約ではプロジェクトの期間が短いため、クライアントとの関係がどうしても希薄になりがちです。
その結果、クライアントからの評価が「一時的な外注エンジニア」という認識にとどまるので、リピート案件の獲得に繋がりづらいです。
また、短期契約のプロジェクトでは、基本的にビジネスの根幹に関わるような責任ある業務は任せられません。
例えば、現在トレンドのデータサイエンティストなどの職務では、表面的なスキルよりも
クライアントの業界特有の課題やゴールを深く理解し、それを踏まえた提案する能力が求められます。
しかし、短期契約の場合はプロジェクト期間が限られているため、こうした「ビジネスの根幹」に関わる機会が少なくなってしまいます。
したがって、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャー(PM)などの上流工程のエンジニアを目指す人には、短期契約は向いていないかもしれません。
フリーランスエンジニアが案件を変えるタイミングは?
では、フリーランスエンジニアが案件を切り替えるタイミングはどんな時なのでしょうか?
結論からいうと、以下に該当する場合は案件の切り替えを検討してください。
- 単価が自身のスキルや相場に見合わない時
- 業務内容が自分に合わないと感じた時
- 残業や休日出勤が多く休みがとりにくい時
それぞれの理由について、以下で詳しく説明します。
単価が自身のスキルや相場に見合わない時
案件の単価が自身のスキルや相場に見合わないと感じた場合、案件を切り替えた方がいいかもしれません。
特に日本のIT業界では、業界経験が2〜3年を過ぎたあたりからようやく「経験者」とみなされる傾向があります。
この辺りの認識はフリーランスであっても変わらないので、2〜3年を目処に案件をすべて見直した方がよいでしょう。
また、需要が高いスキルも比較的高単価になりやすいです。
例えば、現在トレンドのデータサイエンティストやブロックチェーンエンジニアなどは、経験が浅くても十分に高単価が狙える職種です。
そのため、スキルが市場価値に見合っているかを定期的にチェックし、必要に応じて単価交渉を行うか、新しい案件を探すことで収入をアップさせるチャンスをつかむべきと言えるでしょう。
なお、業務委託案件で働く人の年収相場を以下の記事で詳しく解説しています。自身の単価相場を確認したい場合は、ぜひ参考にしてください。
業務内容が自分に合わないと感じた時
案件の業務内容が自分の興味やスキルに合わないと感じた場合、早めに別の案件を検討するべきです。
例えば、フロントエンドエンジニアとして活躍したいのに、バックエンドの保守運用が中心の業務を任されていると、仕事に対するモチベーションが低下しやすくなります。
また、自分が得意とする分野を伸ばせない環境ではスキルアップの機会が限られ、将来的なキャリアにも悪影響を及ぼしてしまいます。
他にも、業務内容が自分の価値観やライフスタイルに合わない場合も問題です。
例えば、常にクライアント先での作業を求められる案件(客先常駐)では、リモートワークを希望するエンジニアにとってストレスになるかもしれません。
フリーランスエンジニアは自身の健康状態が収入に直結する働き方です。
したがって、自分に合わない業務を無理に続けるよりも、なるべくストレスのかからない働き方を目指しましょう。
残業や休日出勤が多く休みがとりにくい時
フリーランスエンジニアは自由な働き方を実現できることが魅力の一つですが、残業や休日出勤が多い案件では自由が制限されてしまいます。
例えば、納期が厳しい案件や急なタスクが頻繁に発生する案件では、プライベートの時間が削られて心身ともに疲弊してしまいかねません。
特に、契約時点で明確な稼働時間が取り決められていない場合、クライアントからの要求が際限なく増えることも考えられます。
こうした状況が続くと、フリーランスとしてのメリットである「柔軟な働き方」を享受できなくなり、生活の質が下がってしまいます。
そのため、労働環境が過度に厳しいと感じた場合は、新しい案件に切り替えることを検討するべきです。
フリーランスエンジニアが新しい案件を獲得する方法
フリーランスエンジニアは状況に応じて自分の好きな案件を選べます。
では、どのようにして新しい案件を獲得すればよいのでしょうか?
ここでは最後に、フリーランスエンジニアが新しい案件を獲得する方法を5つ厳選してご紹介します。
<エンジニアスタイルで今すぐフリーランス案件を探してみる!>
アグリゲーションサービスを活用する
1つ目は、アグリゲーションサービスを利用して案件を獲得する方法です。
アグリゲーションサービスとは、複数の案件情報を一元的に集約し、ユーザーが自分に適した案件を効率的に探せるサービスです。
エージェントがクライアントとのマッチングや交渉を代行してくれるため、営業が苦手なエンジニアでも比較的簡単に仕事を探せます。
代表的なアグリゲーションサービスは以下の通りです。
- レバテックフリーランス:ITエンジニアやクリエイター向けの案件紹介サービス、高単価案件が多い
- ギークスジョブ:フリーランスITエンジニア向けの案件紹介サービスで、特にWeb開発やアプリ開発の分野に強みがある
- Midworks:フリーランスでも正社員に近い福利厚生を提供しながら案件を紹介するサービス、長期案件が豊富
アグリゲーションサービスのメリットは、高単価案件が多い点と営業活動を代行してくれる点です。
ただし、利用には手数料が発生する場合が多いため、条件をよく確認してから利用しましょう。
クラウドソーシングサイトを活用する
2つ目は、クラウドソーシングサイトを活用して案件を獲得する方法です。
クラウドソーシングサイトとは、オンライン上でクライアントとフリーランスをマッチングさせるプラットフォームです。
幅広い分野の案件が掲載されているので、初期費用を抑えて仕事を始められます。
代表的なクラウドソーシングサイトは以下の通りです。
- クラウドワークス:国内最大級のクラウドソーシングサイトで、エンジニア向けのシステム開発やアプリ開発案件が豊富、初心者向け案件も多い
- ランサーズ:長年運営されている信頼性の高いプラットフォームで、エンジニア向けの案件が豊富
- ココナラテック:スキル販売型のプラットフォームで、小規模なシステム開発やアプリケーションの相談業務などを気軽にできる点が特徴
クラウドソーシングサイトのメリットは、初心者でも案件を獲得しやすい点と、多様な案件が揃っている点です。
一方で、手数料がかかることや競争が激しいことがデメリットとして挙げられるため、プロフィールを充実させたり、提案力を磨くことが重要です。
知り合いや友人から紹介してもらう
3つ目は、人脈を活用して案件を紹介してもらう方法です。
人脈を活用した案件は比較的競争倍率が低く、クライアントとの信頼関係が築きやすいのが特徴です。
信頼できる知人や過去の同僚、取引先からの紹介案件はクライアントの事前審査が省略されることが多く、スムーズに契約が進むケースが多いです。
人脈の構築方法は、同業者が参加するセミナーや交流会イベントに参加するのが効率的といえます。
また、以前の職場の同僚や上司から紹介してもらう方法でも構いません。
ただし、以前の職場で知り得た情報を使って営業をかけると競業避止義務や秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)に抵触する恐れがあるので注意しておきましょう。
過去のクライアントへ営業する
4つ目は、過去のクライアントに営業をかける方法です。
過去に仕事をしたクライアントは、すでにあなたのスキルや仕事ぶりを理解しているため、新しい案件を獲得しやすい対象です。
プロジェクト終了後も良好な関係を維持していれば、案件が発生した際に再び依頼を受けられる可能性が高まります。
例えば、以前ウェブアプリの開発を請け負ったクライアントに「その後の保守運用や機能追加は必要ありませんか?」と提案するだけでも、追加の案件につながることもあるでしょう。
営業のタイミングとしては、プロジェクトが一段落してから1〜3ヶ月後など、適度な間隔を空けて連絡するのが効果的です。
定期的に情報を共有することで、信頼を深めつつ、自然な形で営業につなげることができます。
ただし、提案のし過ぎは逆効果になる可能性も高いので、節度をわきまえて提案しましょう。
SNSを活用する
5つ目は、SNSを活用して効率的に潜在顧客にアプローチする方法です。
多くのフリーランスエンジニアは、TwitterやLinkedIn、GitHubなどのプラットフォームで情報を発信して自己ブランディングしています。
最近では、プロジェクト交渉が進んでいくと「ご自身で運営されているSNSまたはWebサイトなどはありますか?」と聞かれることも多くなってきているので、SNS運営は非常に効果的と言えるでしょう。
ただし、SNSを効果的に活用するためには、継続的な情報発信が重要です。
発信した情報が数年以上前のものばかりだと逆効果になってしまう可能性もあるので、SNSを活用する際には途中で諦めるのだけは絶対にやめましょう。
フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ
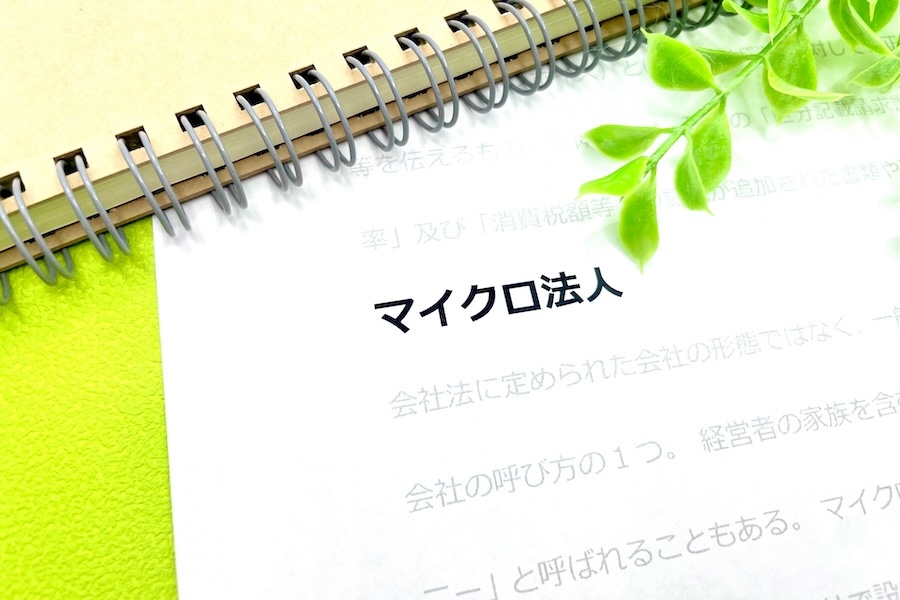
フリーランスエンジニアになったばかりの頃は、案件の探し方で悩むことも少なくありません。
もし案件探しでお悩みなら「エンジニアスタイル」をご活用ください!
エンジニアスタイルは、数ある案件検索サイトの中でも業界最大級の30万件以上の掲載数を誇ります。
リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。
契約前のサポートはもちろん、契約後のアフターサポートが充実しているので、初心者でも安心なのもうれしいポイント。
登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルの利用を検討してみてください!
まとめ
本記事では、フリーランスエンジニアが契約期間を選ぶ際の注意点として、長期契約と短期契約のメリット・デメリットを解説しました。
長期契約は安定した収入や信頼関係の構築に適している一方で、技術の停滞や仕事が単調になるリスクもあります。
短期契約は多様なプロジェクト経験やスキルアップの機会が豊富ですが、収入の不安定さやクライアントとの関係が浅くなりやすい課題があります。
このように、それぞれの契約には一長一短があるため、自分のキャリア目標やライフスタイルに合わせて柔軟に選ぶことが重要です。
安定性と挑戦のバランスを取りながら、フリーランスエンジニアとして理想の働き方を実現してください!
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
-

-

-

-

-

-

-
【Java(Spring) / リモート案件紹介可能】グローバル企業会員管理システムの上流対応の 求人・案件
- 750,000 円/月〜
-
その他
- Java
-
【C#】システムの開発の 求人・案件
- 470,000 円/月〜
-
その他
- C#
-
【上流工程】カード会社向け事務系ツール提供案件の 求人・案件
- 900,000 円/月〜
-
その他
-
【SQL/フルリモート】データ抽出・バッジ処理案件の 求人・案件
- 500,000 円/月〜
-
その他
- SQL
-
【PM】インフラ基盤更改推進案件の 求人・案件
- 1,200,000 円/月〜
-
その他
-
【C言語】一般家庭向け家電開発案件の 求人・案件
- 550,000 円/月〜
-
その他
- C言語
-
【SAP】SAP導入支援案件の 求人・案件
- 800,000 円/月〜
-
品川・お台場
-
某銀行向け勘定系システム開発PJ支援(ITメンバ)/金融のエンジニア求人・案件の 求人・案件
- 1,500,000 円/月〜
-
その他
-
【週5日・首都圏限定】自治体向けシステム更改・結合テスト支援(COBOL)の 求人・案件
- 400,000 円/月〜
-
その他
- COBOL
-
【週5日・首都圏限定】金融機関向け開発支援作業(Java・spring)の 求人・案件
- 550,000 円/月〜
-
その他
- Java SQL
-
【週5日・首都圏限定】建築業システム運用保守(情シス)の 求人・案件
- 600,000 円/月〜
-
新橋・汐留
-
【週5日・首都圏限定】生成AI関連開発(Python)の 求人・案件
- 600,000 円/月〜
-
その他
- Python
-
【週5日・首都圏限定】電力事業者向けシステム開発の 求人・案件
- 600,000 円/月〜
-
その他
- Java
-
【週5日・首都圏限定】クレジット向けシステム更改支援(Javascript)の 求人・案件
- 500,000 円/月〜
-
新宿
- JavaScript Java HTML Shell
-
【週5日・首都圏限定】ECサイトエンハンス開発の 求人・案件
- 650,000 円/月〜
-
その他
- Java SQL
-
【C#.NET(ASP) / リモート案件紹介可能】システム開発支援の 求人・案件
- 650,000 円/月〜
-
大阪府
- C#.NET C# VBA
-
【JavaScript(React) / リモート案件紹介可能】Webシステム開発および保守作業の 求人・案件
- 700,000 円/月〜
-
大手町・丸の内
- JavaScript TypeScript
-
【Oracle / リモート案件紹介可能】通信会社サブシステムリプレイス/Oracle19c構築・移行担当の 求人・案件
- 500,000 円/月〜
-
その他
- Go言語





