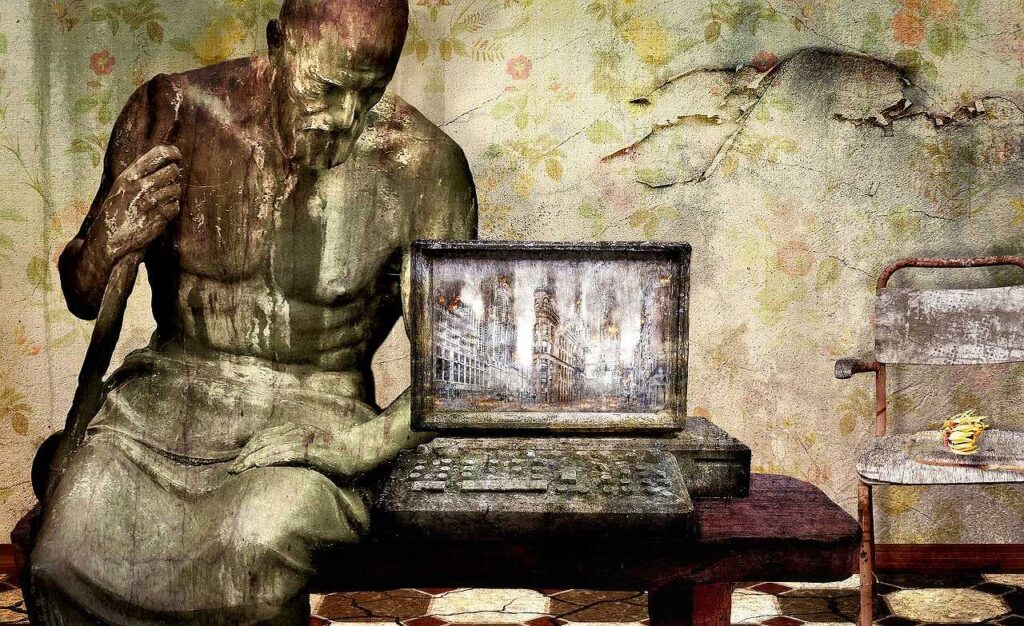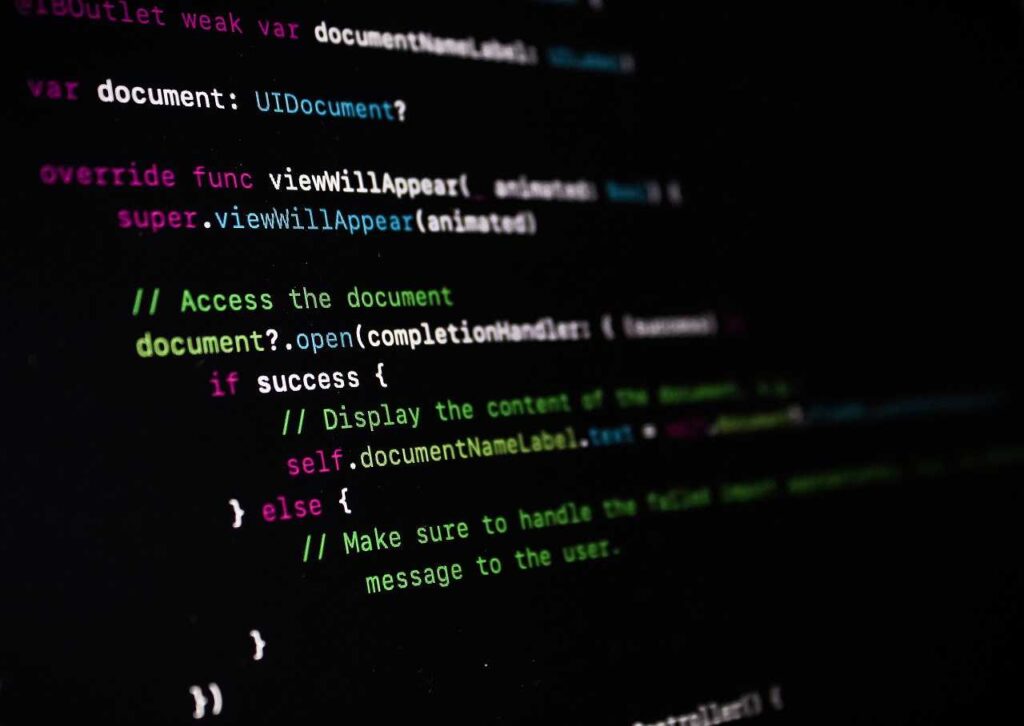ブロックチェーン(block chain)を活用するメリットと活用事例

目次
はじめに
「インターネット以来の技術革新」として世界的に注目が集まっているブロックチェーンですが、具体的にどういった技術なのか疑問を持つ方も多いと思います。
そこでこの記事では、下記について解説します。
- ブロックチェーンの基本的な仕組みや特徴
- ブロックチェーンが注目される理由
- ブロックチェーンの種類
- ブロックチェーンのメリットと課題
- ブロックチェーンとスマートコントラクト
- ブロックチェーン技術の活用例
これからブロックチェーンについて知りたいと言う方はぜひチェックしてみてください。
ブロックチェーンの基本的な仕組みや特徴
ブロックチェーンには次の3つの特徴があります。
- P2P(ピアツーピア)によりシステムダウンに強い
- 暗号技術による高い情報セキュリティ
- コンセンサスアルゴリズムによって改ざんが困難
それぞれの特徴を詳しく解説しながら、その仕組みも説明していきます。
P2P(ピアツーピア)によりシステムダウンに強い
ブロックチェーンによる情報管理はP2Pネットワークを採用しているため、システムダウンへの安全性が高いと言われています。
その理由は以下の2点です。
- 1つのコンピュータがシステムダウンしても全体に影響はない
- 分散保存されるため、データの復元が可能
従来は信頼性の高い組織が管理しているサーバーを介してユーザが利用している状況であるため、仮に故障やハッキングを受けてそのサーバーがシステムダウンしてしまうと、全てのユーザが利用できなくなるトラブルが発生する可能性がありました。しかし、P2Pシステムでは利用しているユーザそれぞれが直接、取引情報を共有する仕組みのため、複数のコンピュータがデータを分散して管理していることになります。
仮に1つのコンピュータが故障したとしても全体には影響がありません。さらに取引データが複数のコンピュータに分散保存されているため、データの復元も可能になります。
暗号技術による高い情報セキュリティ
「ハッシュ」や「電子署名」といった暗号技術によって高い情報セキュリティが実現し、従来の方法よりも安全性が増しています。この理由には「公開鍵」と「秘密鍵」をうまく利用することが挙げられます。ブロックチェーンで利用される暗号技術には「公開鍵」と「秘密鍵」を使用します。2つはペアで利用する仕組みになっており、両方揃わないと暗号化した情報を複合できません。
公開鍵は取引相手がデータの作成者確認を行うために共有されますが、秘密鍵は自分が保持することになっており、本人確認を行いつつ、データの改ざんが外から行えないようになっています。
コンセンサスアルゴリズムによって不正行為が困難
ブロックチェーンではPoWといったコンセンサスアルゴリズムを採用しているため、データの改ざんが困難になり、安全な利用を実現しています。コンセンサスアルゴリズムとはブロックチェーンの基盤となるブロックを追加する際のルールを決めるにあたり、合意(コンセンサス)を行う手法です。
ブロックチェーンでは取引をひとかたまりにしたブロックをつなげていき、チェーンのようにしていきます。分散型のネットワークではそれらのチェーン作成はコンセンサスアルゴリズムに従って行い、お互いに不正がないかを監視しあうシステムになっています。コンセンサスアルゴリズムによって新規の取引の正当性について合意しあい、新たなブロックに正しい取引情報のみを記録していくため、不正を発見しやすいのもブロックチェーンの特徴です。
ブロックチェーンが注目される理由
ブロックチェーンで実現可能なこと、できること
ブロックチェーンで実現できるのは「書き換えできない正確な記録を残すことができる」ことです。これは金融分野だけでなく、シェアリングサービス、著作権管理、美術品の所有権、医療サービスなどにも利用することができます。具体的な利用方法に関しては下の活用事例で詳しく解説しているため、そちらをチェックしてみてください。
ブロックチェーンの市場規模予測
ブロックチェーンの市場規模は世界的にもかなり大きくなっており、今後も拡大の可能性を大いに秘めています。2016年に経済産業省は、ブロックチェーン技術が影響を及ぼす可能性のある市場規模を67兆円と発表しています。(総務省 情報通信白書)この数値は建設64兆円を超えるばかりか、不動産業73兆円や医療福祉68兆円に迫る規模です。
また、他の分野での利用がさらに広がる可能性もあることから、市場規模はこれ以上の伸び率になる可能性も示唆されています。市場規模だけから見ても世界を大きく変えている技術であると分かると思います。
ブロックチェーンの種類
ブロックチェーンは主に以下の3種類存在します。
- パブリックチェーン
- プライベートチェーン
- コンソーシアムチェーン
それぞれ特徴が異なるため、一言でブロックチェーンと言われた時にどれのことを言っているのか理解しておく必要があります。
パブリックチェーン
中央の管理者がおらず、不特定多数のユーザによって管理されているブロックチェーンです。誰でも参加することができ、透明性のあるデータがネット上に公開されるメリットがあります。ただし、不正を考えているユーザも存在することを背景にコンセンサスアルゴリズムによって管理されているため、合意形成に時間がかかってしまうデメリットも存在します。
プライベートチェーン
個人や組織などによって管理されており、参加するためには承認が必要なブロックチェーンです。これにより参加者の管理ができ、不正を考えるユーザが参加するリスクを抑えることができます。また、ルール変更も簡単にでき、取引承認スピードも比較的早いのがメリットになります。
コンソーシアムチェーン
複数の個人や組織で管理しているブロックチェーンになります。プライベートチェーンの仕組みとほぼ同じで、管理する規模が大きくなったものと言えます。
ブロックチェーンのメリットと課題
ブロックチェーンのメリットは大きく分けると以下の3つです。
- 信頼性とセキュリティが担保される
- システムダウンへの耐性が高い
- 運用コストが安価
一方ブロックチェーンのこれからの課題は以下の3つが考えられます。
- スケーラビリティ問題
- 51%攻撃
- 法的問題
ここからはそれぞれのメリットと課題について詳しく解説していきます。
ブロックチェーンのメリット
信頼性とセキュリティが担保される
理由は以下の2つです。
- 「ハッシュ」や「電子署名」といった暗号技術によって高い情報セキュリティが実現
- PoWといったコンセンサスアルゴリズムを採用しているため、データの改ざんが困難
先ほど紹介した「公開鍵」と「秘密鍵」を使用することにより、本人確認を行いつつ、データの改ざんが外から行えないようになっています。このようなブロックチェーン独特の暗号技術により、高いセキュリティを実現しています。また、コンセンサスアルゴリズムによってデータの改ざんが困難になっているため、高い透明性も担保されています。そのような理由から信頼性が高いのがメリットに挙げられます。
信頼性とセキュリティが担保される
先ほど紹介したP2Pネットワークを採用しているため、システムダウンへの耐久性が高いと言われています。従来の中央管理型のサーバーを介した取引ではなく、P2Pのような分散型ネットワークで管理することにより、1つのコンピュータに何か支障が出ても、全体には影響がありません。このようなシステムによってシステムダウンへの耐久性が高いことがメリットとして挙げられます。
システムダウンへの耐性が高い
先ほど紹介したP2Pネットワークを採用しているため、システムダウンへの耐久性が高いと言われています。従来の中央管理型のサーバーを介した取引ではなく、P2Pのような分散型ネットワークで管理することにより、1つのコンピュータに何か支障が出ても、全体には影響がありません。このようなシステムによってシステムダウンへの耐久性が高いことがメリットとして挙げられます。
運用コストが安価
理由は2つ考えられます。
- 大きなサーバーを運用する必要がない
- 人件費の削減
P2Pネットワークを採用しているため、大きなサーバーを管理する必要がありません。
これによりサービスの運用コストを削減することができます。また、全てコンピュータ上のプログラムで運用するため、人の手をほぼ必要としません。これによって人件費の削減にもなります。これら2つの観点から見て、運用コストが安価であることがメリットとして挙げられます。
ブロックチェーンの課題
スケーラビリティ問題
ネットワークが正常に処理できる範囲以上に需要が増加してしまうことによってデータ処理が遅くなったり、手数料が高くなってしまう問題です。ブロックチェーンでは取引データを1つのブロックとしてひとかたまりにし、チェーンのようにつなげていく仕組みになっていますが、実はこのブロックに容量制限があります。
そのため、次のブロックが生成されるまで容量オーバーしたデータは記録できないため、処理が遅れてしまいます。そのような処理データのスケールが大きくなることによって生じる問題をスケーラビリティ問題といいます。
51%攻撃
悪意のあるユーザがマイニング計算能力の51%以上を持ってしまった時に発生する問題です。ブロックチェーンでは取引データを一つのブロックにまとめて、チェーンのようにつなげていきます。PoWでも紹介した通り、チェーンの利用者が膨大な計算問題を解くことで正しい履歴かどうかを判断できるようになっています。この計算のことをマイニングと言ったりします。
この時、もし複数のチェーンが発生した場合は一番長く続いたチェーンが正しいものとして認識するようになっているため、本来の方向に伸びていくはずのチェーンよりも別の方向に伸ばす計算を行うことで発生します。現時点で51%攻撃問題への有効な対策は見つかっていませんが、そもそもかなり膨大な計算を高速で行う必要があるにも関わらず、利益はあまり出ないため、実際は起きにくいとされています。
法的問題
既存の取引では従来の法律に沿って作られているため、従来とは別の方法で取引が行われる場合に対応できない部分が多いこともブロックチェーンによる取引の課題と言えます。現在、ブロックチェーンには法的規制はありませんが、証券や契約の締結など、取引業者と取引自体には法的規制があります。
ブロックチェーンによって取引をすることによって発生するトラブルに現在の法律が対応できていないことが問題になっています。
ブロックチェーンとスマートコントラクト
ブロックチェーン技術の可用性を大きく向上させた要因として、スマートコントラクトへの導入が挙げられます。しかし、「ブロックチェーンとスマートコントラクトってどんな関係にあるの?」という疑問を持つ方もいると思います。そこでここではスマートコントラクトとは何かを解説していきながら、ブロックチェーンとどのような関係にあるのかについて解説していきます。
スマートコントラクトとは
コンピュータ上のプログラムによる自動契約です。これは価格設定などの契約内容の事前定義から決算、商品獲得までの一連の流れをすべて自動で行う仕組みです。ブロックチェーン版の自販機と例えられることがよくあります。
ブロックチェーンと組み合わせることで生まれる可能性
ブロックチェーンが持つ信頼性と取引の透明性がスマートコントラクトの発展を大きく加速させることが期待されています。スマートコントラクトでは人の手を介さずに自動で一連の契約を行う手法でしたが、それには高いセキュリティが必要でした。
そこにはブロックチェーンの仕組みがピッタリです。また、人件費などのコスト削減にもなったりとスマートコントラクトがブロックチェーンの可用性を大きく向上させました。
ブロックチェーン技術の活用事例
ここまでブロックチェーンの仕組みや特徴を紹介してきましたが、どのように私たちの生活を変えていくのかピンと来ない方もいると思います。ここからはそんなブロックチェーンの活用例をご紹介します。
エストニアでの行政活用事例
エストニアでは納税や投票、結婚や離婚の手続き、土地や法人の登記、パスポートの発行までもがインターネットで完結します。驚くことにエストニアではすべての行政サービスのうち99%がインターネットで完結してしまうほど、IT先進国として世界的にも注目を集めています。これらの行政手続きの記録にブロックチェーンを活用しており、国家レベルでの運用も始まっています。
アメリカのOpenBazaar
ユーザー同士がビットコインで自由に商品を売買できる分散型P2PフリマプラットフォームOpenBazaarでもブロックチェーンの仕組みが使われています。世界的にインターネット上でフリーマーケットを展開したり、オークションを行う活動が普及しています。出品者と購入者がサイト上で直接取引を行うため、ブロックチェーンの仕組みを利用することで匿名性を担保しつつ安全な取引を実現しています。
Mastercardの自動決済システム
大手クレジットカード会社であるMasterCardもブロックチェーンの導入を検討しています。目的としては「すべての更新を自動的に記録するというブロックチェーンの特性を活かし、不正行為を未然に防ぐこと」であると考えられ、安全性と利便性の両方が向上する可能性を大いに秘めています。各取引データを永遠に記録しておけて、その透明性が高いことが行政や大手企業にも認められています。
まとめ
ここまでブロックチェーンについて解説してきました。
ブロックチェーンには大きく分けて3つの特徴があります。
- システムダウンに強く改ざんしにくいため、高いセキュリティを持つ
- 計算量が多くなるため認証に時間がかかってしまったり、法律の整備が課題
- 世界的有名な企業のサービスや行政にも利用され始めている
これらにはこんな理由が挙げられます。
- P2P(ピアツーピア)によりシステムダウンに強い
- 暗号技術による高い情報セキュリティ
- コンセンサスアルゴリズムによって改ざんが困難
また、ブロックチェーンにはこんなメリットがあると考えられます。
- 信頼性とセキュリティが担保される
- システムダウンへの耐性が高い
- 運用コストが安価
一方でブロックチェーンにはこんな課題もあります。
- スケーラビリティ問題
- 51%攻撃
- 法的問題
これらの特徴を活かし、ブロックチェーン技術には現在こんな活用例があります。
- エストニアでの行政サービスの電子化
- アメリカのOpenBazaarによるフリマプラットフォーム
- MasterCardの決済システム
ブロックチェーンは世界的な市場規模も既に大きく、今後もさらに拡大する傾向があると考えられるため、今後もチェックが必要です。
- CATEGORY
- 学習
- TAGS
この記事を書いた人

海外旅行と写真が大好き。12歳までイギリス、ロンドンのインターナショナルスクールで過ごす。 学生時代は、オーストラリアでの短期留学を経て現在は東京を拠点に。 大学卒業後、海外での生活経験を活かし、フリーランスとして海外メディアの翻訳・通訳の業務に従事。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。