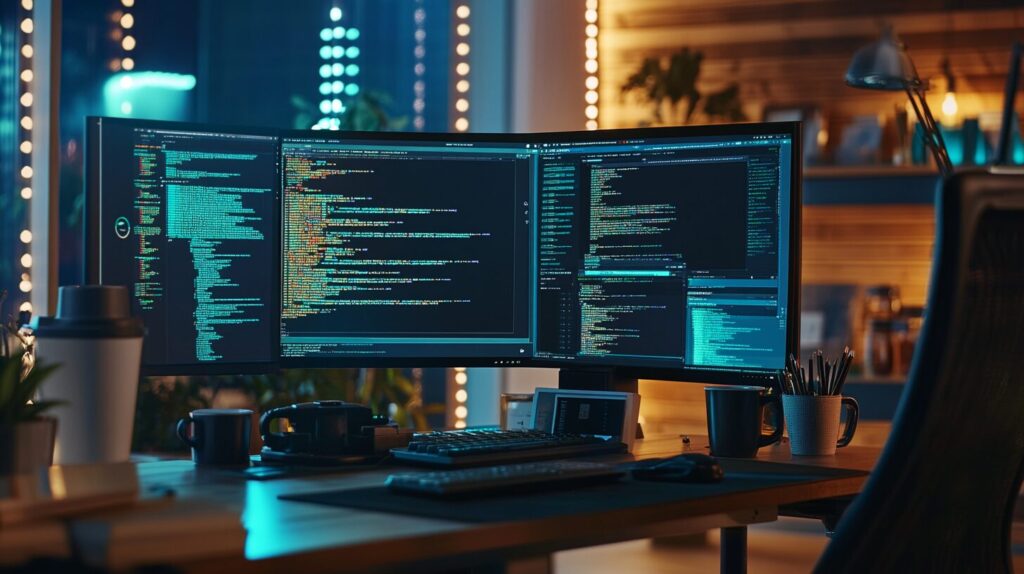プログラマーの服装は自由?業務内容によって違う服装の選び方を詳しく解説

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。プログラマーの案件の一例と、案件一覧を以下からご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
プログラマーの服装はどの程度自由なのでしょうか?
IT業界は服装の自由度が高いといわれていますが、実際には業務内容や勤務形態によって適切な服装は異なります。
本記事では、プログラマーがどのような服装を選ぶべきかを具体的に解説します。
<この記事を読むメリット>
- プログラマーとして適切な服装の選び方がわかる
- オフィスカジュアルとビジネスカジュアルの違いを理解できる
- 面接時に「服装自由」と指定された場合の服装選びのポイントがわかる
服装選びに迷ったときや、自分に適したスタイルを知りたいときに役立つこと間違いなしなので、ぜひ最後までご覧ください。
プログラマーの服装は自由?
InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでプログラマーの投稿をみてみると、フォーマルなスーツを着ている人は多くありません。
そのため、「プログラマーの服装は自由でいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
では、本当にプログラマーの服装は自由でいいのでしょうか?
日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」が公開している「エンジニア白書2023」の調査によると、企業の約7割がカジュアルな服装での面談を許可しています。
つまり、多くの企業ではプログラマーやエンジニアにフォーマルな服装を求めていないのです。
しかしながら、プログラマーであっても重要な会議や公的な場では、フォーマルな服装を着用するのが適切な場面も多々あります。
特に日本では、服装や外見などは他人を判断する上で重要な要素なので、「カジュアル」といっても相手に不快感を与えるような派手すぎる服装は望ましくありません。
服装の自由度は業務内容によって異なる
近年では多くの企業が服装に関する制限を撤廃しつつありますが、どんな場面でも同じ服装をしていては印象が悪くなってしまいます。
そこでここでは、プログラマーの業務内容ごとに適した服装について3つに分けてご紹介します。
クライアントと直接会う業務ならスーツ着用が基本
クライアントと直接対面する業務を担当するプログラマーやエンジニアは、スーツの着用が基本です。
特に金融業界や大手企業のクライアントを持つ場合、服装に関してもクライアントの期待に応えなければなりません。
そのため、クライアントとの初回の打ち合わせや重要なプレゼンテーションの際には、ビジネスマナーとしてスーツを着用するのが適切といえます。
また、クライアント先での勤務が続く場合でも、フォーマルな服装を求められることが多いです。
クライアントとの信頼関係を築くためにも、適切な服装を選ぶことが重要です。
ビジネスカジュアルが許容される場面もありますが、基本的にはスーツの着用が多いことは理解しておきましょう。
クライアントと会わない業務なら服装自由が多い
クライアントと直接会う機会が少ないプログラマーやエンジニアは、服装の自由度が高いのが一般的です。
自社内での開発業務やリモートワークの場合、Tシャツやジーンズ、スニーカーといったカジュアルな服装が許容されます。
特にIT企業やスタートアップ企業では、社員の快適さやパフォーマンスを重視し、服装に対して厳しい規定を設けないことが多いです。
このような企業では、社員が自由な服装で仕事をすることで創造性や効率性が向上すると考えています。
また、リモートワークが増える中で、自宅での業務ではさらに自由な服装が認められることも多くなっています。
客先常駐の場合は常駐先の企業による
客先常駐のプログラマーやエンジニアは、常駐先の企業の服装規定に従う必要があります。
これは、クライアントの企業文化や業界の慣習に適応するためです。
例えば、金融業界や大手企業のクライアント先では、スーツの着用が求められることが一般的です。
一方、IT企業やスタートアップ企業では、比較的カジュアルな服装が許容される場合もあります。
しかし、基本的には常駐先の規定に従うことが求められるので、事前に常駐先の服装規定を確認することが重要です。
基本的にはスーツ着用が多い
なお、客先常駐のプログラマーやエンジニアの場合、基本的にはスーツの着用が求められることが多いです。
これは、常駐先の企業がフォーマルな服装を重視することが多いためです。
特に金融業界や大手企業では、スーツが必須となることが多く、クライアントと対面する機会が多い場合には、ビジネスマナーとしてスーツを着用することが求められます。
常駐先の企業によってはビジネスカジュアルが許容される場合もありますが、初回の訪問時や重要な会議の際にはスーツを着用するのが無難です。
服装自由の場合はどんな服を選んだらいい?
冒頭でも紹介したように、現在ではプログラマーに服装の規定を設けているIT企業は多くありません。
しかし、「服装自由」といわれてもどこまでが「自由」なのかは曖昧です。
そこで以下では、「服装自由」の場合の服装の選び方のポイントについてご紹介します。
服装自由というのは何でも良いわけではない
「服装自由」という規定が定められていても、どんな服装でもいいとは限りません。
例えば、極端にカジュアルな服装や清潔感に欠ける服装は避けるべきです。
Tシャツやジーンズが許容される環境でも、ヨレヨレの服や汚れた靴は避けるのがマナーです。
また、過度に派手なデザインや、他人に不快感を与えるようなメッセージがプリントされた服装も避けるべきです。
良い例としては、シンプルなデザインのシャツやチノパン、清潔感のあるスニーカーなどを選ぶと良いでしょう。
「人は見た目が9割」ともよくいわれますが、アルバート・メラビアン教授が提唱した「メラビアンの法則」によると、人が他者に与える印象は視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%という割合で決まるとされています。
そのため、「服装自由」とはいいつつも、ビジネスであることは忘れないようにしておきましょう。
オフィスの雰囲気やTPOを考えて服装を選ぶ
服装を選ぶ際には、オフィスの雰囲気やTPO(時、場所、場合)を考慮することが重要です。
同じ会社でも、部署やプロジェクトによって求められる服装のスタイルは異なる場合があります。
例えば、クライアントとの打ち合わせが多い部署では、ビジネスカジュアルやフォーマルな服装が多いです。
一方、社内の開発チームなど外部との接触が少ない部署では、よりカジュアルな服装が許容されることが多いです。
また、季節や天候に応じた服装選びも重要です。
夏場には軽やかな素材の服を選び、冬場には適切な防寒対策を行うことで、快適に仕事ができます。
プログラマーによくある服装の例
とはいえ、ファッションにあまり興味がない人は、具体的にどのような服装を着用するべきか悩んでしまう人も多いでしょう。
そこでここでは、プログラマーによくある服装の例をいくつかご紹介します。
オフィスカジュアル
特に服装に興味のない人は、無難にオフィスカジュアルの服をいくつか持っておくと使い回しもできて便利です。
以下では、プログラマーのオフィスカジュアルの基本について解説します。
クライアントと会わない業務ならオフィスカジュアルが多い
上流工程を担当しているプログラマーであれば、クライアントと会うことも多いです。
しかし、中流から下流を担当しているプログラマーは、そこまでクライアントと顔を合わせる機会が多いわけではありません。
そのため、クライアントと会う機会が少ない業務であれば、常日頃からオフィスカジュアルを着用しておくのがおすすめです。
とはいえ、「オフィスカジュアルってどんな服装のこと?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
以下では、一般的なオフィスカジュアルの服装の例についていくつかご紹介します。
上は襟付きのシャツやポロシャツ・ジャケット・カーディガンなど
プログラマーがオフィスカジュアルとして着用する上半身のアイテムは、襟付きのシャツやポロシャツ、ジャケット、カーディガンなどが一般的です。
襟付きシャツやポロシャツは、フォーマルすぎずカジュアルすぎないバランスが取れており、会議やクライアントとの打ち合わせでも好印象を与えます。
また、ジャケットやカーディガンは、温度調整がしやすく、オフィスの冷暖房対策にも便利です。
特にジャケットはシンプルなデザインのものを選ぶことで、よりプロフェッショナルな印象を与えられます。
下はスラックスやチノパンなど
オフィスカジュアルのボトムスとしては、スラックスやチノパンが一般的です。
これらはビジネスシーンでもカジュアルなシーンでも対応できるため、多くの企業で採用されています。
スラックスはきちんとした印象を与えるため、特に重要な会議やクライアントとの打ち合わせに適しています。
一方、チノパンはスラックスよりもカジュアルな印象ですが、カラーやシルエットに気をつけることで、清潔感とプロフェッショナルな雰囲気を保てます。
ジャケットや襟付きシャツとの相性も良く、全体のコーディネートがしやすい点も魅力です。
なお、オフィスカジュアルの基本は清潔感とバランスを保つことですので、過度にカジュアルなアイテムを避けることもポイントの一つです。
靴は革靴でなくてもスニーカーでもOK
オフィスカジュアルの靴としては、革靴に限定されず、スニーカーもOKです。
ただし、スニーカーを選ぶ際にはデザインや状態に注意が必要です。
清潔感があり、シンプルなデザインのスニーカーを選ぶことで、ビジネスシーンにも適応できるカジュアルさを保つことができます。
特に、白や黒などのベーシックなカラーのスニーカーはどんな服装にも合わせやすく、オフィスカジュアルに適しています。
革靴は、特にフォーマルな場面やクライアントとの重要な打ち合わせにおいて信頼感を高めるために有効ですが、普段の業務ではスニーカーでも十分に対応可能です。
快適さと機能性を重視しつつ、見た目の清潔感を保つことが重要です。
ジーンズやTシャツ・サンダルは避けた方が無難
オフィスカジュアルの注意点として、ジーンズやTシャツ、サンダルは避けた方が無難です。
ジーンズはカジュアルすぎる印象を与えるため、ビジネスシーンには適さない場面が多いです。
また、Tシャツはカジュアルすぎるアイテムとして見なされることが多いので、オフィスカジュアルとしては不適切かもしれません。
サンダルは、特にビジネス環境においては安全性や見た目の面で問題があり、不適切です。
オフィスカジュアルとはいえ、一定のビジネスマナーを守り、プロフェッショナルな印象を維持することが重要です。
ビジネスカジュアル
| オフィスカジュアル | ビジネスカジュアル | |
| 目的 | 社内勤務に適したカジュアルな服装 | 社外の人と会う際に適したフォーマルなカジュアル服装 |
| トップス | 襟付きシャツ、ポロシャツ、カーディガン | ジャケット、襟付きシャツ |
| ボトムス | チノパン、スラックス | チノパン、スラックス |
| 靴 | スニーカーやカジュアルシューズ | 革靴、パンプス |
| 許容されるアイテム | Tシャツやジーンズ(過度にラフなものは避ける) | スニーカーやカジュアルすぎる服装は避ける |
| 使用シーン | 自社オフィスでの仕事、外部との接触が少ない場合 | 取引先とのミーティング、外回りが多い場合 |
オフィスカジュアルとよく似たスタイルに「ビジネスカジュアル」というものがあります。
両者の明確な定義は特に決まってはいませんが、ビジネスカジュアルはオフィスカジュアルよりも若干フォーマルな印象の服装です。
しかし、正式なスーツなどよりかはフォーマルすぎないので、オフィスカジュアルとフォーマルスーツの中間的な意味合いでよく使われます。
以下で、プログラマーによくあるビジネスカジュアルの例をいくつかご紹介します。
スーツスタイルをドレスダウンしたスタイル
プログラマーのビジネスカジュアルでは、スーツスタイルをドレスダウンしたスタイルがよく採用されます。
このスタイルは、ジャケットやスラックスなどのフォーマルな要素を保ちつつ、ネクタイを着用しなくてよかったり、シャツをカジュアルなものに変えるなどの工夫が特徴です。
例えば、ジャケットはネイビーやグレーなど落ち着いた色を選び、インナーには襟付きのシャツやポロシャツを合わせます。
これにより、フォーマルさを損なわずにリラックスした雰囲気を演出できます。
クライアントと対面する業務はスーツかビジネスカジュアルが多い
クライアントと対面する業務を行うプログラマーは、スーツかビジネスカジュアルを選ぶことが多いです。
特に、初めてのクライアントとの打ち合わせや重要なプレゼンテーションでは、信頼感が重視されるのでスーツが基本です。
しかし、リピーターのクライアントやカジュアルな会議の場合、ビジネスカジュアルを採用する人も少なくありません。
上はジャケットや襟付きのシャツ
ビジネスカジュアルのトップスとしては、ジャケットや襟付きのシャツが基本です。
ジャケットはネイビーやグレー、ベージュなどの落ち着いた色が多く、季節に応じて素材を変えられるのでおすすめです。
襟付きのシャツは白や淡いブルーが一般的で、ポロシャツも夏場には適しています。
下はセンター入りのパンツ
ビジネスカジュアルのボトムスとしては、センター入りのパンツが一般的です。
これにより、フォーマルな印象を保ちながらも動きやすさと快適さを確保できます。
センター入りのパンツは、シンプルでありながら洗練された印象を与えるため、ビジネスシーンでの信頼感を高めます。
靴は革靴
ビジネスカジュアルの足元は革靴が基本です。
革靴は、フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも対応できるため、ビジネスカジュアルにおいて非常に重宝されます。
色は黒や茶色が一般的で、スリッポンタイプやレースアップタイプなど、デザインも多様です。
これにより、足元までしっかりとした印象を保てます。
グレーやネイビーなど落ち着いた色の服が基本
ビジネスカジュアルの服装においては、グレーやネイビーなどの落ち着いた色を選ぶことが基本です。
グレーやネイビーは、フォーマルさとカジュアルさのバランスが取れており、どんな場面でもビジネスにふさわしい印象を与えます。
また、派手な柄や色使いは避け、シンプルで清潔感のある服装を心がけることが重要です。
面接で服装自由の場合はどうする?
多くの人が困ってしまうのが、面接時に「服装自由」と書いている場合です。
特にスタートアップ系の企業では、服装自由という条件で面接を実施している場合が多いですが、この場合はどういった服装が望ましいのでしょうか?
ビジネスカジュアルを基準に選ぶ
プログラマーの面接において「服装自由」と指定された場合でも、ビジネスカジュアルを基準に選ぶことが望ましいです。
先述したように、ビジネスカジュアルはスーツほどフォーマルではないものの、適度なフォーマルさを保ちつつ、カジュアルな要素を取り入れたスタイルです。
具体的には、ジャケットに襟付きのシャツ、チノパンやスラックスを組み合わせると良いでしょう
カジュアルすぎる服装は印象が悪くなる
面接において、カジュアルすぎる服装は避けるべきです。
普段着や過度にラフな服装は、プロフェッショナルな場面にふさわしくないと見なされることがあります。
例えば、Tシャツやジーンズ、サンダルなどは避けるべきです。
これらの服装は、面接官に対して準備不足や真剣さの欠如といった印象を与える可能性が高いです。
特にIT業界では、自由な社風が多いとはいえ面接はビジネスの一環であり、適切な服装を選ぶことが求められます。
オフィスカジュアルやビジネスカジュアルを基準に、清潔感と適度なフォーマルさを備えた服装を心がけることで、面接官に対して誠実さや信頼感をアピールできます。
スーツを着て行ってもマイナスになることはない
面接で「服装自由」と指定された場合でも、スーツを着て行ってもマイナスになることはありません。
むしろ、スーツはビジネスの場において最もフォーマルであり、安心して選べる服装です。
特に初めての企業との面接や重要な役職の面接では、スーツを選ぶことでプロフェッショナルな印象を与えられます。
やはりスーツはどんな場面でも信頼感や誠実さを示すために効果的であり、面接官に対して真剣さや意気込みをアピールできます。
また、スーツを着ることで自信を持って面接に臨むことができるため、自分自身のパフォーマンス向上にもつながります。
「服装自由」の面接で迷ってしまったのなら、とりあえずスーツを着用して臨めば問題ありません。
フリーランスエンジニアの仕事探しはエンジニアスタイルがおすすめ

デジタルトランスフォーメーション(DX)が最も大きな課題とされている日本では、プログラマーの需要は近年急激に増加しています。
また、需要が非常に高いのでフリーランスプログラマーとして活躍する方も増えてきました。
しかし、「フリーランスになっても自分1人で仕事を見つけられる気がしない…。」と考えてなかなか最初の一歩が踏み出せない方も多いでしょう。
そんな時はぜひエンジニアスタイルをご利用ください!
エンジニアスタイルは、数あるフリーランスサイトの中でも業界最大級の30万件以上の求人掲載数を誇ります。
また、リモートでの作業やテレワーク可能な案件を絞って検索することもできるので、きっと希望に沿った案件が見つかるはずです。
契約前のサポートはもちろん契約後もアフターサポートが充実しているので、初心者でも安心なのも嬉しいポイント。
登録は無料なので、この機会にぜひエンジニアスタイルのご利用を検討してみてください!
まとめ
本記事では、プログラマーの服装の自由度について、業務内容に応じた適切な選び方を詳しく解説しました。
プログラマーの服装は自由である一方で、TPOに応じた適切な服装を選ぶ必要があります。
今後、IT業界の働き方がさらに多様化する中で、服装選びに関する悩みはますます増えていくことになるでしょう。
本記事を通じて、自分のスタイルとプロフェッショナリズムを両立させるための参考にしてください。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

1992年生まれ、北海道出身。トレンドスポットとグルメ情報が大好きなフリーライター。 衣・食・住、暮らしに関する執筆をメインに活動している。 最近のマイブームは代々木上原のカフェ巡り。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。