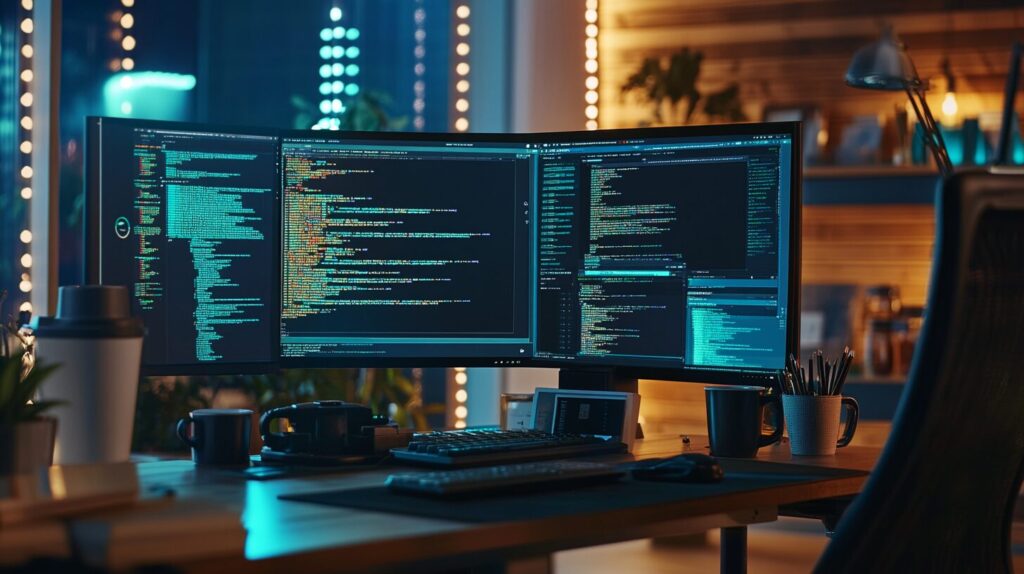簡易課税制度とは?フリーランスエンジニアにとってのメリット・デメリットと検討する際のポイント

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
2023年10月にインボイス制度が正式に導入されて以降、フリーランスエンジニアを取り巻く環境はガラリと変わりました。
特に、消費税の計算方法や負担への意識が高まる中で、「簡易課税制度」を利用するべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、簡易課税制度とはどのような仕組みか、またフリーランスエンジニアにとってのメリットとデメリットを詳しく解説します。
<この記事を読むメリット>
- 簡易課税制度と通常課税の違いが理解できる
- フリーランスエンジニアが簡易課税を選ぶべき理由と注意点がわかる
- 導入を検討する際の判断基準が明確になる
簡易課税制度は、事務負担を減らせる便利な制度ですが、すべての事業者に適しているわけではありません。
この記事を読めば、簡易課税制度と通常課税のどちらを選ぶべきかハッキリわかるようになるので、消費税対応にお悩みのフリーランスエンジニアはぜひ参考にしてください!
簡易課税制度とは?

2023年10月にインボイス制度が導入されたこともあり、フリーランスエンジニアでも消費税を納税しないといけないケースが増えてきました。
こういった背景もあり、多くのフリーランスエンジニアが注目しているのが「簡易課税制度」です。
ここではまず、簡易課税制度とはそもそも何なのかについて、わかりやすく解説していきます。
消費税の計算方法を簡略化するための制度
簡易課税制度は、中小事業者やフリーランスの事務負担軽減を目的とした消費税の特例制度です。
通常、消費税の納税額は以下のように計算します。
納税額 = 売上にかかる消費税 – 仕入や経費にかかる消費税
この計算では、仕入や経費に含まれる消費税をすべて記録しなければならず、計算が非常に手間です。
しかし、簡易課税制度を利用すると仕入や経費の計算が不要になるので、計算が簡略化されて事務処理の負担を軽減できます。
なお、簡易課税制度を利用するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 前々年の課税売上高が5,000万円以下であること
- 事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出していること
なお、フリーランスのインボイス制度の影響については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひあわせてご確認ください。
関連記事:フリーランスが知っておくべきインボイス制度と具体的な影響とは
売上に応じた一定割合を使って仕入控除税額を算出
簡易課税制度では、売上にかかる消費税に「みなし仕入率」と呼ばれる割合を掛けることで、仕入控除税額を算出します。
みなし仕入率とは、簡易課税制度を利用する際に、仕入控除額を計算するために使われる業種ごとの固定割合のことです。
業種別のみなし仕入率は以下の通りです。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業および第5種事業以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
例えば、フリーランスエンジニアは第5種事業(サービス業)に分類されるので、売上にかかる消費税に50%を掛けるだけで消費税の控除額が算出できるので、複雑な計算が不要になります。
もちろん、通常課税を適用して計算した方が控除額が大きくなるケースもあります。
しかし、年収が1,000万円以内の一般的なフリーランスエンジニアでは、大した違いはありません。
むしろ、事務処理にかかる時間を考えると損になるケースの方が多いので、多くのフリーランスエンジニアは簡易課税制度を利用して消費税の控除額を算出しています。
簡易課税と通常課税の違い
| 通常課税(原則課税) | 簡易課税 | |
| 計算方法 | 売上 – 実際の経費に基づく控除額 | 売上 – みなし仕入率で算出した控除額 |
| 仕入控除の考え方 | 実際の仕入や経費にかかる消費税を控除 | 売上に基づくみなし仕入率で控除額を計算 |
| インボイス対応 | インボイスの保存が必要 | インボイス保存は不要 |
| 適用条件 | 課税売上高が1,000万円超 | 前々年の課税売上高が5,000万円以下 |
| 手続き | 手続き不要 | 事前に届出が必要 |
| 事務負担 | 経費の記録やインボイス管理が必要 | 計算が簡単で事務負担が少ない |
簡易課税と通常課税では、手続きや計算の複雑さがかなり違います。
ここからは、簡易課税と通常課税の以下の3つの違いについて詳しくみていきましょう。
- 消費税の計算方法の違い
- 仕入控除の考え方の違い
- 適用条件と手続きの違い
消費税の計算方法の違い
通常課税と簡易課税では、文字通り簡易課税の方が計算が非常にシンプルです。
わかりやすいように、具体的な計算例を通してみていきましょう。
通常課税の場合
通常課税では、消費税の納税額を次のように計算します。
納税額 = 売上にかかる消費税 – 仕入や経費にかかる消費税
つまり、クライアントなどから受け取った「売上の消費税」から、仕事で使った経費や仕入に含まれている「消費税分」を引いた額が納税額になります。
例えば、年間売上が1,000万円のフリーランスエンジニアの場合、売上にかかる消費税は1,000万円の10%なので100万円です。
続いて、仕事に関連する経費に含まれる消費税を合計する必要があります。ここでは、以下のような経費がかかったとしましょう。
- 外注費:300万円(消費税30万円)
- 交通費:20万円(消費税2万円)
- パソコン購入費:100万円(消費税10万円)
つまり、合計の仕入や経費の消費税は、30万円 + 2万円 + 10万円 = 42万円です。
あとは先ほどの計算式に代入すればいいだけなので、
100万円 – 42万円 = 58万円
これが最終的な消費税の納税額ということになります。
計算だけみると非常に簡単なように思えますが、実際には課税対象外の経費もありますし、現在では経費ごとに取引先が発行したインボイスを管理し、消費税額を記録しなければなりません。
簡易課税の場合
対して簡易課税では、消費税の納税額を次のように計算します。
納税額 = 売上にかかる消費税 – 売上にかかる消費税 × みなし仕入率
つまり、実際の経費を計算する必要はなく、売上に応じた固定割合(みなし仕入率)を使って控除額を求める仕組みです。
例えば、年間売上が1,000万円のフリーランスエンジニアの場合、売上にかかる消費税は通常課税の時と同じく100万円です。
続いて、この100万円にみなし仕入率(フリーランスエンジニアの場合は50%)を掛けると、100万円 × 50% = 50万円なので、控除額は50万円ということになります。
したがって、簡易課税の場合の納税額は
100万円 – 50万円 = 50万円
ということになり、非常に簡単に消費税の納税額を計算できます。
仕入控除の考え方の違い
消費税の計算において「仕入控除」の仕組みはとても重要です。
仕入控除とは、事業活動の中で支払った仕入や経費に含まれる消費税を、納税額から差し引くことです。
この仕組みによって、事業者が負担するのは「売上と仕入の差額」に対する消費税だけとなります。
ただし、通常課税と簡易課税では仕入控除の考え方も変わってくるので、以下で詳しくみていきましょう。
通常課税の場合
通常課税では、実際に支払った仕入や経費に含まれる消費税をすべて計算して控除額を求めます。
そのため、経費が発生するたびに細かい記録が必要となります。
この場合の実務の流れは以下の通りです。
- 経費(外注費、事務用品費、交通費など)に含まれる消費税を請求書や領収書から確認
- 消費税率(10%または8%)を確認して金額を計算
- それを合計して、仕入控除額とする
これに加えて、2023年10月のインボイス制度導入以降では、適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。
したがって、担当案件が増えれば増えるほど、フリーランスエンジニアの事務処理の負担が大きくなっていきます。
簡易課税の場合
これに対し、簡易課税では実際の仕入や経費にかかる消費税を計算せず、仕入控除額を算出できます。
これは、先述したように売上にかかる消費税に対して、みなし仕入率を掛ければいいだけだからです。
また、簡易課税制度で消費税の納税をすれば、適格請求書(インボイス)の保存義務もありません。
インボイス制度が導入されてから急いで課税事業者として登録したフリーランスエンジニアも多いため、適格請求書(インボイス)なしで納税できるのは非常に大きなメリットといえるでしょう。
適用条件と手続きの違い
消費税の納税になるべく時間をかけたくないフリーランスエンジニアにとって、簡易課税は非常にありがたい制度です。
しかし、すべてのフリーランスエンジニアが簡易課税制度を利用できるわけではありません。また、手続き方法もそれぞれ異なります。
以下でそれぞれの違いについて、詳しくみていきましょう。
通常課税の場合
通常課税(原則課税)は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者に自動的に適用されます。
なお、基準期間とは個人事業主の場合、前々年の1月1日から12月31日までの課税売上高です。法人の場合、前々事業年度の課税売上高になります。
手続き方法としては、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、基本的に自動的に適用されるので特別な手続きや届出は必要ありません。
前々年の課税売上高が1,000万円以下であっても、自主的に課税事業者となりたい場合は、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
簡易課税の場合
簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度です。
基準期間は通常課税と同じく、前々年(個人事業主の場合は暦年、法人は事業年度)の課税売上高が基準となります。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合、その課税期間では簡易課税を適用できません。
手続き方法としては、まず「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に税務署に提出する必要があります。
提出期限は簡易課税を適用したい課税期間の初日の前日までです。
なお、簡易課税制度を一度選択すると、原則として2年間は継続して適用されます。
簡易課税をやめたい場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、適用をやめたい課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
このように、通常課税は売上規模が大きい事業者に自動適用され、特別な手続きは不要ですが、仕入控除のための記録作業が煩雑です。
一方、簡易課税は基準期間の売上規模が5,000万円以下の事業者が選択可能で、手続きが必要ですが、計算や事務負担が軽減されます。
フリーランスエンジニアにとっての簡易課税制度のメリット
では、フリーランスエンジニアは簡易課税制度を利用するべきなのでしょうか?
結論からいうと、簡易課税制度にはメリットもデメリットもあるので、一概にすべてのフリーランスエンジニアが利用するべきだとはいえません。
しかし、一般的なフリーランスエンジニアであれば、簡易課税制度を利用するメリットは比較的大きいケースが多くなります。
フリーランスエンジニアが簡易課税制度を利用するメリットは以下の4点です。
- 手続きが簡単
- 帳簿管理の手間が省ける
- 経理にかかるコストを抑えられる
- 節税効果がある場合も
それぞれのメリットについて、以下でわかりやすく解説します。
手続きが簡単
1つ目のメリットは、簡易課税制度は手続きが非常に簡単であることです。
通常課税の場合、納税額を計算するためには経費や仕入にかかる消費税をすべて記録し、正確に計算しなければなりません。
一方で、簡易課税制度では、売上に応じた「みなし仕入率」を適用するだけで納税額を計算できます。
また、制度を利用するために必要な手続きもシンプルで、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に一度提出すれば、その後2年間は申請する必要がありません。
事務作業が少なくスムーズに始められる点が、忙しいフリーランスエンジニアにとっては大きなメリットといえるでしょう。
帳簿管理の手間が省ける
2つ目のメリットは、帳簿管理の負担が大幅に軽減されることです。
通常課税では、仕入や経費にかかる消費税を正確に計算するため、すべての経費を細かく記録し、請求書や領収書を保存する必要があります。
特に2023年10月に導入されたインボイス制度では、適格請求書(インボイス)の保存が必須となり、経理の負担がさらに増えました。
一方、簡易課税では実際の経費に基づく消費税額の計算が不要です。売上を基に控除額を算出できるため、帳簿管理の手間が格段に減ります。
インボイスの保存義務がないのは、忙しいフリーランスにとって大きなメリットです。
経理にかかるコストを抑えられる
3つ目のメリットは、経理にかかる費用を削減できる点です。
通常課税では、経理作業が非常に複雑であるため、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。
税務処理を専門家に依頼すると、もちろんコストが発生するので、特にフリーランスエンジニアのような個人事業主には大きな負担となるでしょう。
しかし、簡易課税制度を利用すれば経理作業が簡略化されるため、税理士へ依頼せずとも自分で手続きを完結できます。
結果として、経費削減につながる可能性が高いです。
節税効果がある場合も
4つ目のメリットは、場合によっては節税効果が期待できることです。
簡易課税制度では、売上に応じてみなし仕入率を適用して控除額を計算します。
例えば、フリーランスエンジニアのみなし仕入率は50%ですが、実際の経費がそれ以下であれば、控除額が実際よりも多くなる可能性があります。
例えば、年間売上が1,000万円のフリーランスエンジニアで考えてみましょう。
経費は職種によってかなり変動するので一概にはいえませんが、一般的なフリーランスエンジニアの経費率は10〜30%程度と言われています。
仮に経費率が20%だったと仮定すると、経費は200万円で計上することになります。
この場合、
- 通常課税では、控除額は20万円なので納税額は80万円
- 簡易課税では、控除額は50万円(100万円 × 50%)なので納税額は50万円
という結果になるので、簡易課税制度を利用した方がお得といえます。
もちろんこれはあくまで仮定の話ですが、場合によっては節税対策になるので、そこまで多くの経費を計上しないフリーランスエンジニアは、簡易課税制度を利用するメリットが大きくなる場合が多いです。
フリーランスエンジニアにとっての簡易課税制度のデメリット
フリーランスエンジニアが簡易課税制度を利用するデメリットは以下の3点です。
- 仕入控除税額が過少評価される可能性がある
- 適用期間が2年間で変更できない
- 適用するかどうかの判断が難しい
それぞれのデメリットについて、以下でわかりやすく解説します。
仕入控除税額が過少評価される(税負担が増える)可能性がある
1つ目のデメリットは、場合によっては仕入控除税額が過少評価される可能性がある点です。
簡易課税制度では、実際の経費にかかわらず、売上に基づいて「みなし仕入率」を適用して控除額を計算します。
そのため、経費が多い場合や、みなし仕入率よりも実際の経費割合が高い場合、仕入控除税額が本来の額より少なく計算されることがあります。
ただし、これは年間売上が5,000万円を超えるような非常に高額、つまり超高収入のフリーランスエンジニアに限られます。
一般的なフリーランスエンジニアの場合、年収は300〜800万円が平均値なので、ほとんどのケースで簡易課税制度を利用するメリットの方が大きいといえるでしょう。
適用期間が2年間で変更できない
2つ目のデメリットは、簡易課税制度を一度選択すると2年間は変更できないことです。
簡易課税制度の適用を希望する場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
しかし、一度選択すると原則として2年間は通常課税に戻すことができません。
たとえ途中で「通常課税の方が有利だった」と気づいても、その期間中は簡易課税を続ける必要があります。
毎年申請しなくてもいい点はメリットともいえますが、例えば事業が急に軌道に乗って超高収入になってしまった場合、この点はデメリットとなり得ます。
適用するかどうかの判断が難しい
3つ目のデメリットは、簡易課税を利用すべきかどうかの判断が難しい点です。
簡易課税は「経費が少ない場合に有利」といわれていますが、実際には将来の経費の増減や売上規模、事業の拡大計画を考慮しなければなりません。
また、税法や事務手続きの理解が不十分な場合、正確に判断するのが難しくなることがあります。
例えば、今は経費が少なく簡易課税が有利だと思っても、翌年に外注費や設備投資が増える予定がある場合は、通常課税の方が節税対策になるかもしれません。
この辺りの判断は非常に難しいので、もし簡易課税制度を利用するかどうかを迷っているのなら、専門家に相談するのが最も確実です。
簡易課税制度の導入を検討する際のポイント
フリーランスエンジニアにとって、最も重要なのはスキルを習得してキャリアを構築することであり、税務知識を蓄えることではありません。
そのため、できればこういった税務処理に時間を割きたくないというのが本音でしょう。
そんな方のために、最後に簡易課税制度の導入を検討する際のポイントを2つご紹介します。
収入と経費のバランスを考慮する
収入と経費のバランスを考慮した結果、通常課税よりも節税効果が高くなる、またはほぼ同じなら簡易課税制度を導入するべきだといえるでしょう。
何度もいうように、簡易課税制度では実際の経費を基にした控除額ではなく、売上に「みなし仕入率」を適用して控除額を計算します。
そのため、経費が少ない場合は簡易課税が有利になりやすいですが、経費が多い場合は通常課税が有利になる傾向にあります。
したがって、収入が大幅に変動する可能性が少なく、外注費や設備投資費を増やす予定のないフリーランスエンジニアは簡易課税制度を導入した方が節税効果が高くなりやすいです。
対して、高水準のスキルレベルを有しており、今後大幅に事業を拡張しようと考えているフリーランスエンジニアは、簡易課税と通常課税の費用対効果を綿密にシミュレーションした方がよいでしょう。
プロのアドバイスを受ける
2つ目のポイントは、税理士や専門家からプロのアドバイスを受けることです。
簡易課税制度を選択するかどうかは、事業の性質や将来の計画、収入と経費のバランスによって異なります。
自分だけで判断するのが難しい場合、税務の専門家である税理士に相談することで、より正確で納得のいく判断ができるようになります。
ただし、税理士によっては相談料が高額になる可能性もあります。
すでに顧問契約を結んでいるのなら問題ありませんが、スポット契約で依頼している場合は別料金になることもあるので、この点は注意しておきましょう。
まとめ
本記事では、フリーランスエンジニアに向けて、簡易課税制度の仕組みや通常課税との違い、メリット・デメリット、そして導入を検討する際のポイントについて詳しく解説しました。
簡易課税制度は、事務負担を軽減しつつ、場合によっては納税額を抑えられる便利な制度ですが、経費が多い場合や将来の事業拡大を見据えると、必ずしもすべての事業者に最適とは限りません。
今後、インボイス制度が定着し、消費税に対する取り組み方がますます重要になる中で、自分の事業特性に合った課税方法を選択する重要性も高まるかもしれません。
しかし、最新の税制を常に熟知するのは簡単なことではありません。
自分だけで判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談し、より精度の高い判断をすることをおすすめします。
「エンジニアスタイルマガジン」では、今後もこういったフリーランスエンジニアにとって役立つ最新情報を随時お届けいたします。
それでは、また別の記事でお会いしましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
- CATEGORY
- フリーランス
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。