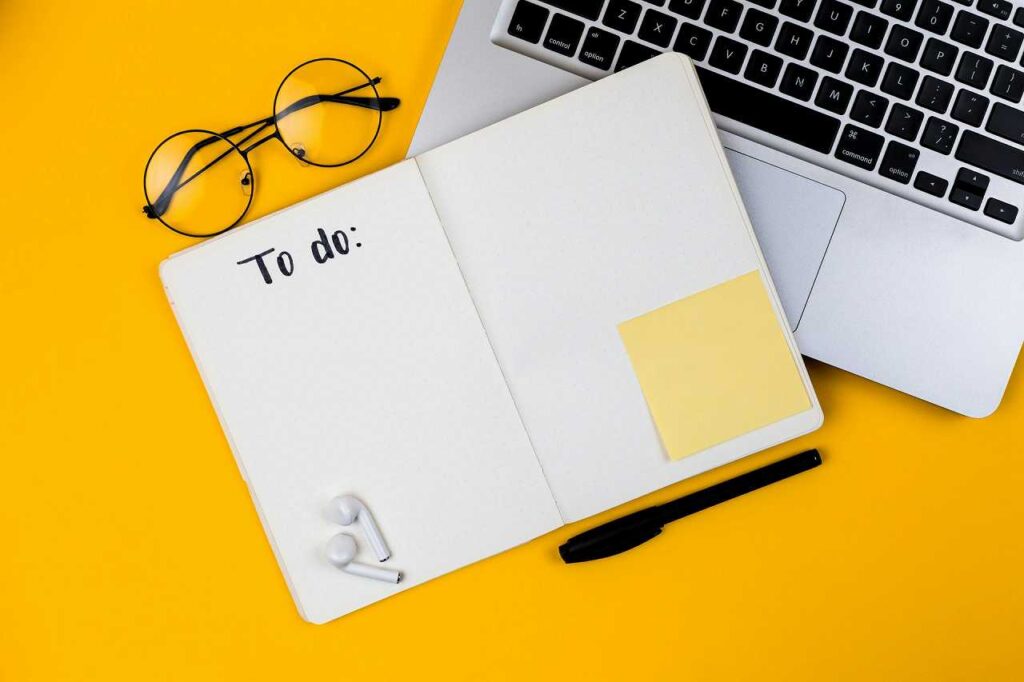副業から始めるフリーランスエンジニア:会社員との両立方法と注意点

はじめまして、エンジニアスタイル編集部です!
コラムページでは、ITフリーランスに向けてお役立ち情報を発信します。Twitterではホットな案件を紹介してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします!
本記事が、皆様の参考になれば幸いです。
経験がまだ少ない方にもわかりやすく説明するために、初歩的な内容も記載しております。記事も長いので、実務経験豊富な方は、ぜひ目次から関心のある項目を選択してください。
エンジニアスタイルは、最高単価390万円、国内最大級のITフリーランス・副業案件検索サービスです。ITフリーランス・副業案件一覧をご覧いただけますのであわせてご確認ください。
目次
はじめに
会社員として働きながらも、新たな収入源やキャリアアップの手段としてフリーランスエンジニアの副業に挑戦する動きが活発になっています。柔軟な働き方が注目される中、個人で案件を受注して収入を伸ばせるメリットは大きいものの、時間管理や契約条件、企業の就業規則との兼ね合いなど、気を付けるべきポイントも少なくありません。ここでは、会社員の立場を保ちながら副業としてフリーランスエンジニアを始めるときのメリットや注意点、実際にプロジェクトを回す際の時間管理法や案件獲得のコツなどを詳しく解説します。会社員という安定を維持しつつ、自分のスキルをさらに磨いて収益を高めたい方にとって、きっと役立つ情報が得られるはずです。
会社員エンジニアが副業を始めるメリット
副業で得られる収入とキャリアアップ
収入の多様化とリスク分散
会社員が副業としてフリーランスの仕事を行う最大のメリットは、収入源を一本化せずにリスク分散できることにあります。景気変動や会社の業績不振など、思わぬ事情で本業収入が減少しても、副業の収入で補うことが可能になります。また、エンジニアとしての市場価値や需要が高ければ、短時間の稼働でもそれなりの報酬を得やすく、結果として生活の安定につながると言えるでしょう。
会社員時代の給与だけに依存せず、複数の案件から得る報酬を組み合わせることで収入の天井が高まり、貯蓄や投資に回せるお金が増える利点もあります。副業で得た収益をさらに自己投資に充てたり、新しい技術領域の勉強資金にするなど、キャリア形成を加速させるサイクルを構築できるのは大きな魅力です。
スキルの幅を広げる機会
会社のプロジェクトでは扱わない技術スタックや開発手法を、副業のフリーランス案件で経験できる点も見逃せません。たとえば会社員としてはJavaメインの仕事をしていても、副業でPythonを使ったデータ分析案件に取り組むことで、全く異なる分野のスキルを獲得できます。こうした経験は本業にも還元され、同僚や上司からの評価が上がる場合や、将来社内転職をする際にもプラスに働くでしょう。
副業を通じて新しい言語やフレームワーク、クラウドサービスなどに挑戦することで、自分の技術的な引き出しが増えていきます。エンジニアとしての成長を加速させるだけでなく、クライアントに対する提案力や柔軟な対応力にも繋がり、結果的にフリーランスとしての案件獲得にも有利になる好循環が生まれます。
副業禁止規定と就業規則
企業就業規則の確認
会社員として雇用されている場合、副業を始める前に必ず自社の就業規則や副業規定を確認しましょう。企業によっては明示的に副業禁止とされているケースがあり、それを破ると懲戒処分を受けるリスクもあります。近年、副業を容認する企業も増えていますが、一部の職種や業務内容によっては副業の制限が残っている可能性があるため、先に人事部や上司に相談しておくほうが安全です。
また、公務員など特定の職種では法律的に副業禁止となっている場合もあり、ステルスで副業を進めると大きなリスクを背負うことになります。自分が所属する組織や業界のルールをしっかり調べたうえで、合法的かつ公認の形で副業エンジニアとして活動する道を探りましょう。
利害衝突(Conflict of Interest)の可能性
会社と競合するビジネスを副業で行うのは、企業倫理や契約に抵触する可能性があります。例えば、会社で開発しているサービスと同様の機能を持つWebアプリを副業で作る案件を受けるなど、明らかにコンフリクトが生じる行為は避けるべきです。コンフリクトが発覚すれば、雇用契約の違反や機密情報漏洩とみなされ、トラブルに発展しかねません。
一方で、まったく別の業種や業界の案件、あるいは会社が扱わない技術領域であれば、利害衝突のリスクは低くなるはずです。ただ、判断が微妙な場合もあるため、可能であれば本業の上司やコンプライアンス担当などにあらかじめ相談したり、就業規則の解釈を確認したりすると安心です。
成功するための時間管理術
スケジュールの可視化
カレンダー連携やタスク管理ツール
本業と副業の両方をうまく進めるには、限られた時間で効率良く作業しなければなりません。まず取り組むべきはスケジュールの「見える化」であり、Googleカレンダーなどを活用して会社での業務時間やミーティング、副業の予定をすべてまとめて把握することが重要です。
一例として、週末に副業の主要作業を集中的に行い、平日は毎日2時間程度だけ副業タスクに割り当てるなど、自分のライフスタイルに合わせた時間配分を決めておくのも効果的でしょう。さらに、タスク管理ツール(TrelloやAsanaなど)を導入して、案件ごとのタスクと優先度を可視化することで、複数プロジェクトを同時に回しやすくなります。
余裕のあるバッファを確保
副業先との契約で納期が設定される場合や、時給制であってもある程度の稼働時間を確保する必要があるケースがあります。しかし、会社員としての残業や突発的なトラブルが起きると副業の時間にしわ寄せが来る可能性が高いです。そのため、納期やスケジュールを設定する際は実稼働時間に余裕を持たせ、急な本業の予定変更にも対応できるバッファを設けておきましょう。
自分の作業スピードを過信してタイトスケジュールを組むと、どちらの仕事も中途半端になってしまい、結果的に評価を下げてしまう恐れがあります。むしろ副業の案件には「納期を少し長めに提案し、その分品質を高める」スタンスで交渉すると、実際の進捗もスムーズに進みやすく、トラブルも少なくなるはずです。
効率化とアウトソーシング
得意分野に集中する
副業として携わる案件は、自分の得意領域にフォーカスするのが理想です。例えば、フロントエンドが得意ならUI実装だけを請け負い、バックエンドやインフラは他のエンジニアに任せるという形です。自分が苦手な分野に時間を多く割かなければならない案件だと、学習コストがかさんで本業との両立が困難になる可能性があります。
得意分野だけに絞ることで短期間でも高い成果を出しやすくなり、クライアントからの評価も上がるため、報酬アップやリピート依頼のチャンスが広がります。「短時間で確実に成果を出せるエンジニア」と思われると、単価を高めに設定できるメリットもあります。
外部リソースやクラウドサービスの積極利用
社内プロジェクトでは認可が難しい先端ツールや外部サービスも、副業なら自由に導入できるケースがあります。例えばCI/CDパイプラインやコンテナオーケストレーションをクラウド上でセットアップして、自動デプロイを実現すれば、毎回のリリース作業をほぼ自動化できるなど、工数削減効果が高いです。
また、特定の作業を外注(アウトソーシング)する手段も検討できます。デザインやテストなど、自分があまり時間をかけたくない作業については他のフリーランスに依頼するなど、コストと時間を天秤にかけながら最適化を図ると、本業と副業の両立がしやすくなります。
直営業とエージェント活用
エージェントを利用するメリット
手間を省ける案件獲得
エージェント(エージェンシー)に登録すると、企業とのマッチングや契約手続き、報酬交渉を代行してくれるため、営業に割く時間が減りやすいです。副業のフリーランスエンジニアには本業があるので、案件探しに時間をかけられないという問題をエージェント活用でカバーできます。
さらに、大手エージェントが取り扱う案件は報酬や条件が整備されていることも多く、週2〜3日勤務やリモート可といった柔軟な働き方を相談しやすい点がメリットです。エージェント担当者とのコミュニケーションも重要で、自分が得意な技術や好ましい契約形態をはっきり伝えておくとスムーズに合う案件を紹介してもらいやすくなります。
報酬面の妥協と割り切り
エージェント経由だとマージンがかかり、直営業よりも手取りが少なくなるリスクがあります。ただし、営業コストや契約リスクをエージェントが負担してくれるため、副業であまり営業活動に時間をかけられない人には大きなメリットでもあります。副業でそこまで高額を目指さなくても良いと思うのであれば、安定した案件をエージェントから得ることで確実に収入を確保する戦略が有効です。
一方、スキルや実績が高いエンジニアはエージェント側も高単価案件を紹介してくれる場合があるため、マージンを引かれても十分に魅力的な報酬となることがあります。自分の市場価値とエージェントが取り扱う案件水準を見比べ、最適なパートナーを見つけるとよいでしょう。
直営業(直接契約)で自由度アップ
高単価を狙うコンサル的役割
直営業の場合、クライアントとの間にエージェントが入らない分、マージンを取られず高い報酬を獲得できる可能性があります。特に、企業が求めるスキルが希少であれば「週2日の稼働であっても月額○○万円」など強気の条件で交渉できるケースもあるでしょう。
さらにコンサルティング要素を含む提案型の副業案件なら、開発業務だけでなくアーキテクチャ設計や要件定義にかかわり、プロジェクト全体をリードする立場を担うことができます。これにより付加価値が上がり、単価がさらに引き上げやすくなるというメリットがあります。
契約書やリスク管理の負担
ただし、直営業では契約書の作成や交渉、トラブル時の対応などを自分で行わなければならず、企業のコンプライアンス部門や法務部とやり取りする手間が発生することも多いです。英語圏や海外企業の場合、英文契約書を正確にレビューしないとリスクが大きいなどの難しさもあります。
会社員としての本業に加え、契約関連の事務作業を全部こなすのは負担が大きいため、場合によっては弁護士や行政書士など専門家に依頼するコストを考慮したり、比較的手軽に進められる形の案件を選ぶと良いでしょう。信頼できる顧客を開拓するまでには時間がかかるので、焦らず自分のペースで契約スキルも高めるのがおすすめです。
具体的なステップと注意点
まずは小さく始める
小規模プロジェクトやスポット案件
初めての副業なら、最初から長期・大規模のプロジェクトに飛び込むよりも、小規模で短期スポットの開発や運用支援を受ける形がおすすめです。時間と難易度が低めなら週末や夜だけでも十分対応でき、会社員のスケジュールと両立しやすいです。
具体的には「LP(ランディングページ)の改修」「小さなWebアプリの追加機能」「クラウド上のサーバー設定」など、短期で完了する案件を探しましょう。成果物が短期間で完成すれば実績として公表しやすく、次の案件を探す際にもポートフォリオとして活用できます。
実績作りと評判獲得
副業をいきなり高単価でスタートするのは難しい面もあるため、最初は相場より少し低めでも構わないと割り切って、小さな実績を積むのも一案です。企業やクライアントに「副業とは思えないくらいしっかり対応してくれる」と好印象を与えれば、追加仕事や紹介を得られる可能性が高まり、結果として高い単価に繋がることも多いです。
SNSやブログで自分の実績を簡単に報告しつつ、徐々に相場に見合った報酬交渉を行う流れが堅実です。クラウドソーシングサイトやエージェントサイトでも評判や評価が上がることで、より条件の良い仕事が舞い込むサイクルを築けるでしょう。
法人化や個人事業主の選択
どのタイミングで独立するか
副業からスタートして業務が順調に拡大してきたら、「個人事業主として開業届を出す」「あるいは法人化をして会社員を辞め、本格的にフリーランスに転身する」といった選択肢が見えてきます。いつ法人成りするのかは収入規模やリスク管理に左右されますが、副業収入が本業給与と同等、もしくはそれを上回る水準に到達した時点で検討する人が多いです。
法人化には初期費用や事務手続きが必要になる一方、信用度や節税面でのメリットを享受できます。対して個人事業主なら手続きがシンプルでリスクを抑えやすい反面、支払う税金が高くなる可能性も出てきます。自分の働き方や将来的なビジョンを考慮して、いつどのように段階を踏むかがポイントです。
複数クライアントとの契約管理
副業が順調になると、複数のクライアントを同時に抱えることになります。各クライアントとの契約期間や納期、報酬形態を整理し、スケジュールがバッティングしないように管理するのは思った以上に大変です。契約書や請求書の発行などバックオフィス作業にも時間がかかります。
法人化してバックオフィス機能を整備するか、あるいは個人事業主のままツールを駆使して業務プロセスを効率化するか、いずれにせよ事務管理の手間を見込んでおかなければ、エンジニアリングの時間が取れなくなる恐れがあります。
まとめ
会社員としての安定収入を得ながら副業のフリーランスエンジニアを始める働き方は、収益面やキャリア面で大きなメリットが期待できます。ただし、企業の就業規則や副業禁止規定を確認したうえで、利害衝突や機密情報の取り扱いに注意することが大前提です。
実際の案件探しでは、安定や手間を重視するならエージェント活用を視野に、報酬を重視するなら直営業で高単価を狙うなど、自分の希望や状況に応じて戦略を立てましょう。特に週末や夜間のみ稼働できる案件を探す際には、スケジュール管理や体調管理が重要になり、効率化のためにクラウドツールや外注も検討すべきです。
初期の段階では実績作りを意識し、無理のない範囲で小さめの案件を成功させてポートフォリオに加えつつ、徐々に単価交渉や契約形態の多様化に挑戦すると、ステップアップしやすいでしょう。最終的に副業を本業にシフトする道もありますが、まずは会社員との両立を上手にこなし、安心感と自由度を両方手に入れる働き方を実現してみてください。
- CATEGORY
- 副業
- TAGS
この記事を書いた人

海外、コスメが好きな東北人。2015年に世界一周一人旅をしたアクティブ女子。 コスメECの運営業務に従事後、独立し。現在は、取材を中心にフリーランスWEBライターとして活動中。
この記事を監修した人
大学在学中、FinTech領域、恋愛系マッチングサービス運営会社でインターンを実施。その後、人材会社でのインターンを経て、 インターン先の人材会社にマーケティング、メディア事業の採用枠として新卒入社し、オウンドメディアの立ち上げ業務に携わる。独立後、 フリーランスとしてマーケティング、SEO、メディア運営業務を行っている。